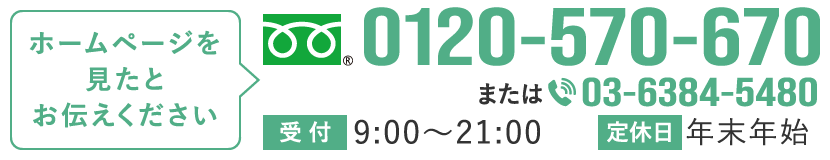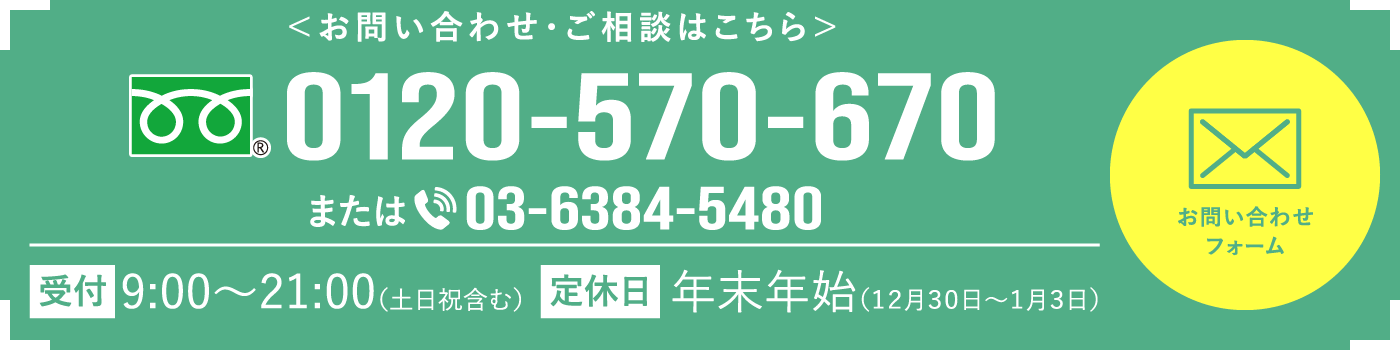今回のテーマは、交通事故で肩腱板損傷を負ってしまった場合の損害賠償についてです。
交通事故は、予期せぬ瞬間に私たちの日常生活を大きく変えてしまう可能性があります。交通事故による負傷の中でも、肩関節周辺の痛みや機能障害を引き起こす「肩腱板損傷」は、その後の生活に大きな影響を与えることがあります。
今回は、交通事故による肩腱板損傷について、その基礎知識から、診断・治療、後遺障害の認定、損害論(慰謝料や逸失利益)、そして弁護士の役割までを詳しく解説します。
【関連記事】
弁護士に依頼することで示談金が増額した事例~右肩腱板損傷・異議申立て・後遺障害12級13号~
このページの目次
1.交通事故における肩腱板損傷とは
交通事故によって肩に強い衝撃が加わると、肩腱板を損傷する可能性があります。
ここでは、まず肩腱板の構造と機能、主な損傷の原因、そして交通事故における症状と影響について解説します。
(1)肩腱板の構造と機能
肩腱板とは、肩関節を構成する4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、肩甲下筋及び小円筋)の腱が集まったものです。
「腱」とは、筋肉の先端部で繊維が細くなって線維化して骨に付着している部分をいい、つまり筋肉と骨とを繋いでいる組織であると考えてください。
これらの腱は、上腕骨頭(腕の骨の先端)を肩甲骨の関節窩(関節を構成する凹状のくぼみ部分)に安定させ、腕を上げたり、回したりする際の滑らかな動きを支える重要な役割を担っています。
腱板が正常に機能することで、私たちは日常生活における様々な動作をスムーズに行うことができます。
(2)主な損傷の原因
肩腱板損傷の主な原因は、加齢による腱の変性、使いすぎ(オーバーユース)、転倒やスポーツなどによる急激な外力などが挙げられます。
交通事故においては、衝突時の衝撃や、体を支えようとした際の無理な力が肩関節に加わることで、腱板が断裂したり、部分的に損傷したりすることがあります。
特に、直接的な打撃だけでなく、予測できない体勢での衝撃は、腱板に大きな負担を与える可能性があります。
ただし、一般的にはいわゆるシートベルト損傷によって、靱帯や腱が切れるということは珍しいとされており、二輪車や自転車などで転倒しているかどうかなどの受傷機転が明確に存在することが重要です。
(3)交通事故での症状と影響
交通事故による肩腱板損傷の症状は、損傷の程度によって様々です。
軽度の場合には、肩の痛みやわずかな可動域制限が見られる程度ですが、重度の場合には、激しい痛みで腕を上げることが困難になったり、夜間に痛みが強くなったりすることがあります。
具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- 肩の痛み(安静時痛、運動時痛、夜間痛)
- 腕を上げる際の痛みやひっかかり感
- 肩関節の可動域制限(特に腕を上げる、外に開く、内側に回す動作が困難になる)
- 肩の力が入りにくい、脱力感
- 特定の動作での肩の不安定感
これらの症状は、日常生活における様々な動作、例えば着替え、入浴、食事、車の運転などを困難にするだけでなく、時には睡眠障害を引き起こし、精神的な負担となることもあります。
2.腱板損傷の診断と治療
交通事故による肩の痛みを感じたら、早期に整形外科を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。
ここでは、腱板損傷の診断方法と検査内容、治療法の選択肢、そして肩関節の可動域制限について解説します。
(1)診断方法と検査内容
腱板損傷の診断のためには、一般的にMRIによる画像検査が必要です。
なぜなら、いわゆるレントゲンやCTなどのX線画像では、骨の状態しかわからないため、骨折を伴わない場合にはそれ以上の説明ができません。
靱帯や腱の断裂や損傷については、MRIでなければ映らないため、靱帯や腱の断裂や損傷が疑われる場合には一般的にMRIによる画像検査が行われます。
なお、肩腱板に損傷や炎症がある場合には、MRIのT2強調画像で損傷や炎症部位が白く(高信号で)映ります。
MRI検査結果等を総合的に判断し、腱板損傷の有無、程度、損傷部位などが特定されます。
ただ、事故から時間が経過してしまうと、事故との因果関係を疑われることがありますので、早期にMRI検査を行う必要があります。
(2)治療法の選択肢
腱板損傷の治療法は、損傷の程度や患者さんの年齢、活動レベルなどによって異なります。
主な治療法としては、保存療法と手術療法があります。
【保存療法】
手術を行わずに、自然治癒力を促したり、症状の緩和を図る治療法です。
- 安静: 損傷した腱板の負担を軽減するため、肩関節を安静に保ちます。
- 薬物療法: 痛みや炎症を抑えるために、鎮痛薬や湿布、内服薬などが用いられます。
- 注射療法: 痛みが強い場合には、局所麻酔薬やステロイド薬を肩関節周囲に注射することがあります。
- リハビリテーション: 痛みが落ち着いてきたら、肩関節の可動域を改善し、周囲の筋肉を強化するための運動療法を行います。理学療法士の指導のもと、段階的に運動を進めていくことが重要です。
【手術療法】
保存療法で十分な改善が見られない場合や、腱板の完全断裂など重度の損傷の場合には、手術が検討されます。手術の方法は、関節鏡視下手術(内視鏡を用いた手術)や、より開放的な手術などがあります。手術の目的は、断裂した腱板を修復し、肩関節の機能を回復させることです。術後も、リハビリテーションを継続して行うことが、良好な回復のためには不可欠です。
(3)肩関節の可動域制限について
腱は筋肉の収縮を骨に伝える役割がありますので、腱に損傷が生じると、関節の可動域に制限が生じることがあります。
なお、先に述べたとおり肩腱板は、肩関節を構成する4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、肩甲下筋及び小円筋)の腱が集まったものですが、交通事故による損傷においては、そのほとんどが棘上筋腱損傷であると言われています。
腱板損傷によって生じる肩関節の可動域制限は、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
特に、腕を上げる、回すといった動作が困難になるため、着替えや洗髪、高い場所の物を取るなどの動作に苦労することがあるでしょう。
3.肩腱板損傷の後遺障害とその認定
交通事故による肩腱板損傷は、適切な治療を行っても、後遺障害が残ってしまうことがあります。
ここでは、後遺障害認定の必要性、後遺障害等級の説明、そして認定を受けるための条件について解説します。
(1)後遺障害認定の必要性
交通事故による怪我で後遺障害が残った場合、加害者の加入する自賠責保険に対して請求を行うことにより、その程度に応じて後遺障害等級が認定されることがあります。
後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償を請求することができます。
肩腱板損傷の場合、肩関節の機能障害の程度によって後遺障害等級が認定される可能性があります。
適切な賠償を受けるためには、後遺障害認定の手続きを行うことが重要です。
(2)後遺障害等級の説明
肩関節の機能障害に関する後遺障害等級は、主に以下の3つに分類されます。
【第8級6号】 肩関節の用を廃したもの
「肩関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 関節が強直したもの
「関節が強直した」とは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものとして、関節可動域が原則として健側(怪我をしていない側)の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものを言います。また、肩関節においては、肩甲上腕関節が癒合し骨製強直していることがX線写真により確認できるものを含みます。
- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
【第10級10号】 肩関節の機能に著しい障害を残すもの
「肩関節の機能に著しい障害を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 肩関節の可動域が健側の可動域確度の1/2以下に制限されているもの
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換し、上記第8級6号に該当しないもの
【第12級6号】肩関節の機能に障害を残すもの
・肩関節の可動域が健側の3/4以下に制限された場合をいいます。
これらの等級は、医師の診断書や関節の可動域測定の結果などに基づいて自賠責保険(損害保険料率算出機構の自賠責保険調査事務所)において判断されます。
(3)認定を受けるための条件
交通事故による肩腱板損傷で後遺障害の認定を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 交通事故と肩腱板損傷の因果関係が医学的に認められること: 事故の状況や受傷時の状態、その後の経過などから、肩腱板損傷が交通事故によって生じたものであると医学的に説明できる必要があります。
- 適切な治療を継続して行ったにもかかわらず、症状が改善せず、後遺症が残存していること: 漫然と治療を受けるのではなく、医師の指示に従い、必要な検査やリハビリテーションを継続して行うことが重要です。
- 残存した症状が、将来においても回復が見込めないと医学的に判断されること: 症状が一時的なものではなく、永続的なものであると医師が判断する必要があります。
- 後遺症の内容が、自賠責保険の後遺障害等級に該当するものであること: 提出された医学的な資料に基づいて、損害保険料率算出機構の自賠責保険調査事務所が各等級に該当するか否かを認定します。
後遺障害の認定を受けるためには、適切な診断書や検査結果などの医学的証拠を揃えることが重要です。
弁護士に相談することで、これらの手続きをスムーズに進めるためのアドバイスやサポートを受けることができます。
4.肩腱板損傷による後遺障害の損害賠償(慰謝料と逸失利益)
交通事故による肩腱板損傷で後遺障害が残った場合、慰謝料や逸失利益の請求を行うことができます。
ここでは、慰謝料の種類と実績、逸失利益とは何か、そして示談金の交渉と流れについて解説します。
(1)慰謝料の種類
交通事故における慰謝料には、主に以下の2種類があります。
- 入通院慰謝料: 怪我の治療のために、入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入院期間や通院期間、治療内容などに基づいて算出されます。
- 後遺障害慰謝料: 後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に支払われる慰謝料です。後遺障害等級に応じて金額が定められており、等級が高いほど慰謝料の金額も高くなります。
慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、一般的に弁護士基準が最も高額になる傾向があります。
過去の裁判例などを参考に、個々の事案に応じた適切な慰謝料額を算定することが重要です。
なお、上記肩関節の機能障害に関する各後遺障害等級に該当する場合の弁護士基準(裁判基準)の一例を記すと以下のとおりです(地域や個別の事情によって異なる場合がありますのでご留意ください)。
- 第8級6号: 830万円
- 第10級10号: 550万円
- 第12級6号: 290万円
(2)逸失利益とは何か
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、将来にわたって得られるはずだった収入が減少してしまう損害のことです。
肩腱板損傷による機能障害が、仕事に支障をきたし、収入の減少につながるとして逸失利益を請求することができます。
逸失利益の計算は、被害者の年齢、職業、事故前の収入、後遺障害等級などを考慮して行われます。
具体的には、「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式を用いて算出されることが一般的です。
労働能力喪失率や労働能力喪失期間は、後遺障害等級に応じて定められています。
なお、こちらも一概には言えませんが、労働能力喪失期間は、始期を症状固定日として、その終期は原則として67歳として計算するのが一般的です。
また、上記肩関節の機能障害に関する各後遺障害等級に該当する場合の労働能力喪失率は一般的には以下の基準によって計算されます。
- 第8級6号: 45%
- 第10級10号: 27%
- 第12級6号: 14%
(3)示談金の交渉と流れ
交通事故による損害賠償金(慰謝料や逸失利益など)の支払いは、加害者側の保険会社との示談交渉によって決まることが一般的です。
保険会社は、自社の基準に基づいて損害額を提示してきますが、その金額が必ずしも適正とは限りません。
なお、弁護士が対応する場合の示談交渉の流れは以下のようになります。
- 損害額の算定: 治療費、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など、発生した損害の総額を正確に算定します。
- 示談案の提示: 算定した損害額に基づいて、加害者側の保険会社に示談案を提示します。
- 交渉: 保険会社から提示された示談案(対案)に対して、増額交渉を行います。お互いの主張をぶつけ合い、合意点を探ります。
- 合意: 双方の合意が得られたら、示談書を作成し、示談が成立となります。
- 賠償金の支払い: 示談書に基づき、加害者側の保険会社から被害者へ賠償金が支払われます。
示談交渉は、法的な知識や交渉力が必要となるため、被害者自身で行うには負担が大きい場合があります。
弁護士に依頼することで、適切な損害額を算定し、有利な条件で示談を進めることが期待できます。
(4)解決の実績
ここでひとつ、解決事例をご紹介します。
【事案】
東京都内在住のAさん(40歳・会社員・年収約800万円)は、バイクで優先道路を走行中、路外から一時停止をせずに侵入してきた自動車と衝突しました。この事故により、Aさんは鎖骨骨折、肩腱板断裂などの重傷を負い、緊急搬送され手術を受けました。その後、約1年にわたりリハビリテーションを中心とした治療を継続されました。
【相談・依頼の経緯】
事故後、相手方保険会社から治療費や休業損害の支払いがありましたが、今後の後遺症や慰謝料について不安を感じたAさんは、当事務所の無料相談をご利用になりました。弁護士がAさんの状況を詳しくお伺いし、後遺障害等級認定の手続きや、適正な損害賠償額の請求についてサポートできることをご説明したところ、Aさんは正式に当事務所に依頼されました。
【弁護士の活動】
①後遺障害等級認定のサポート
Aさんの肩関節の可動域制限は著しく、日常生活や仕事にも支障をきたす可能性がありました。そこで、当事務所の弁護士は、Aさんの主治医と連携を取りながら、後遺障害等級認定に必要な医学的な資料を収集し、適切な等級認定を受けられるよう尽力しました。その結果、Aさんは後遺障害等級10級10号の認定を受けることができました。
②損害賠償請求と示談交渉
後遺障害等級が認定されたことを受け、当事務所は相手方保険会社に対し、以下の項目について損害賠償請求を行いました。※ただし、Aさんにも過失がありましたので、請求できたのは以下の損害に対する相手方の過失割合分となります。
- 治療費: 約200万円
- 交通費: 約20万円
- 入通院慰謝料: 約1年間の治療期間に対する慰謝料
- 後遺障害慰謝料: 後遺障害等級10級相当の慰謝料550万円
- 休業損害: 約3ヶ月の休業期間に対する損害
- 逸失利益: 後遺障害による将来の収入減少に対する損害(約3969万円)
相手方保険会社は当初、自社の基準に基づいた低い金額を提示してきました。しかし、当事務所の弁護士は裁判基準(弁護士基準)に基づいた適正な損害賠償額を算定し、粘り強く交渉を行いました。
特に、後遺障害慰謝料と逸失利益については、過去の裁判例やAさんの年齢、年収などを考慮し、詳細な主張を展開しました。
肩関節の機能障害がAさんの仕事に与える影響についても具体的に説明し、将来の収入減少の可能性を強く訴えました。
③最終的な示談成立
数回にわたる交渉の結果、最終的に相手方保険会社は当事務所の主張をほぼ全面的に認め、合計で約3000万円(自賠責保険金などの既払い金を除く)の示談金が支払われることで合意に至りました。
Aさんは、当初保険会社から説明を受けていた金額よりも大幅に増額された賠償金を受け取ることができ、今後の生活への不安を大きく軽減することができました。
5.交通事故被害者のための弁護士の役割
交通事故による肩腱板損傷は、被害者に大きな精神的・経済的負担を与えます。
弁護士は、このような被害者の被害に対して適切な賠償を得るために様々なサポートを行います。
ここでは、弁護士の選び方と相談方法、無料相談の活用方法、そして弁護士に依頼するメリットについて解説します。
(1)弁護士の選び方と相談方法
交通事故問題を専門とする弁護士を選ぶことが重要です。
ホームページや紹介などを通じて、交通事故の解決実績や専門知識を確認しましょう。
また、実際に相談してみて、親身になって話を聞いてくれるか、説明が丁寧で分かりやすいかなども判断材料となります。
弁護士への相談方法としては、電話、メール、オンライン相談、面談などがあります。
多くの法律事務所では、初回相談を無料で行っているため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
相談の際には、事故の状況、怪我の状況、治療の経過、保険会社とのやり取りなど、できるだけ詳しく伝えることが大切です。
(2)無料相談の活用方法
無料相談は、弁護士に依頼するかどうかを検討する上で非常に有効な手段です。
無料相談を最大限に活用するために、以下の点に注意しましょう。
- 事前に相談内容を整理しておく: 聞きたいことや伝えたいことをメモにまとめておくと、限られた時間を有効に使えます。
- 関係書類を持参する: 事故証明書、診断書、保険会社の提示書など、関連する書類を持参すると、より具体的なアドバイスを受けることができます。
- 弁護士の経験や実績を確認する: 交通事故事件の解決経験や、特に肩腱板損傷のような事例の経験があるかなどを質問してみましょう。
- 費用体系について確認する: 弁護士に依頼した場合の費用(着手金、報酬金など)について、明確に説明を受けるようにしましょう。
(3)弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害者が弁護士に依頼することには、以下のような多くのメリットがあります。
- 適正な損害賠償額の獲得: 弁護士は、法的な知識や過去の判例に基づいて、適正な損害賠償額を算定し、保険会社との交渉を有利に進めます。
- 煩雑な手続きからの解放: 示談交渉や後遺障害認定の手続きなど、複雑で時間のかかる作業を弁護士に任せることができます。
- 精神的な負担の軽減: 保険会社とのやり取りや、今後の見通しなどについて弁護士に相談することで、精神的な不安や負担を軽減することができます。
- 法的サポートによる安心感: 法的な専門家である弁護士がサポートすることで、安心して治療に専念することができます。
- 裁判になった場合の対応: 示談交渉が決裂し、裁判になった場合でも、弁護士が代理人として対応します。
交通事故による肩腱板損傷でお困りの方は、一人で悩まず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、あなたの権利を守り、一日も早い問題解決のために尽力します。
私たち優誠法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談を初回無料でお受けしております。是非お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

これまで、交通事故・離婚・相続・労働などの民事事件を数多く手がけてきました。今までの経験をご紹介しつつ、皆様がお困りになることが多い法律問題について、少しでも分かりやすくお伝えしていきます。
■経歴
2009年03月 法政大学法学部法律学科 卒業
2011年03月 中央大学法科大学院 修了
2011年09月 司法試験合格
2012年12月 最高裁判所司法研修所(千葉地方裁判所所属) 修了
2012年12月 ベリーベスト法律事務所 入所
2020年06月 独立して都内に事務所を開設
2021年3月 優誠法律事務所設立
2025年04月 他事務所への出向を経て優誠法律事務所に復帰
■著書
こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。