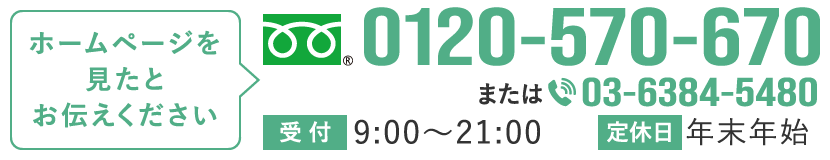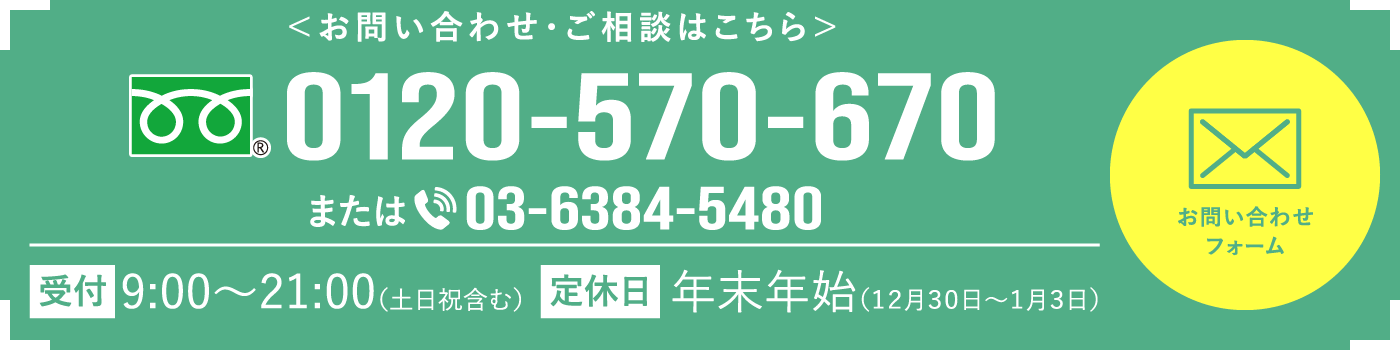突然の交通事故は、私たちの日常を奪い、心身に大きな負担を強いることがあります。
特に、肩関節を構成する重要な腱の集まりである腱板の損傷は、その後の生活や仕事に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
上肢の機能障害にもつながる肩腱板損傷は、痛みだけでなく、肩の可動域制限を引き起こし、時に後遺障害を残すことも少なくありません。
もしあなたが交通事故で腱板損傷を負い、今後の治療や保険会社との交渉、そして適切な慰謝料の獲得について不安を感じているのであれば、この記事が解決への糸口になると思います。
弁護士法人優誠法律事務所は、交通事故の専門知識と豊富な解決事例に基づき、被害者の方々を全力でサポートしています。
この記事では、交通事故における肩腱板損傷の基礎知識から、後遺障害認定の必要性、保険会社との交渉のポイント、そして弁護士に依頼するメリットまでを詳細に解説します。
このページの目次
1.交通事故における肩腱板損傷とは
交通事故によって肩に強い衝撃が加わると、肩腱板を損傷する可能性があります。
ここでは、肩腱板の構造と機能、主な損傷の原因、そして交通事故における症状と影響について解説します。
(1)肩腱板の構造と機能
肩腱板とは、肩関節を構成する4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)の腱が集合したものです。
これらの腱は、上腕骨頭(腕の骨の先端)を肩甲骨の関節窩に安定させ、腕を上げたり、回したりする際の滑らかな動きを支える重要な役割を担っています。
腱板が正常に機能することで、私たちは日常生活における様々な動作をスムーズに行うことができるのです。
(2)主な損傷の原因
肩腱板損傷の主な原因は、加齢による腱の変性、使いすぎ(オーバーユース)、転倒やスポーツなどによる急激な外力などが挙げられます。
交通事故においては、衝突時の衝撃や、体を支えようとした際の無理な力が肩関節に加わることで、腱板が断裂したり、部分的に損傷したりすることがあります。
特に、直接的な打撃だけでなく、予測できない体勢での衝撃は、腱板に大きな負担を与える可能性があります。
(3)交通事故での症状と影響
交通事故による肩腱板損傷の症状は、損傷の程度によって様々です。
軽度の場合には、肩の痛みやわずかな可動域制限が見られる程度ですが、重度の場合には、激しい痛みで腕を上げることが困難になったり、夜間に痛みが強くなったりすることがあります。
具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- 肩の痛み(安静時痛、運動時痛、夜間痛)
- 腕を上げる際の痛みやひっかかり感
- 肩関節の可動域制限(特に腕を上げる、外に開く、内側に回す動作が困難になる)
- 肩の力が入りにくい、脱力感
- 特定の動作での肩の不安定感
これらの症状は、日常生活における様々な動作、例えば着替え、入浴、食事、車の運転などを困難にするだけでなく、睡眠障害を引き起こし、精神的な負担となることもあります。
また、受傷当日には症状が軽度でも、数日経過してから悪化することもあるため、注意が必要です。
鎖骨の骨折など、肩腱板の損傷に加えて骨折を伴うケースもあります。
2.交通事故における証明の重要性
交通事故によって腱板損傷を負った被害者が適切な損害賠償を獲得するためには、その怪我が交通事故によって生じたものであり、かつ後遺障害が残っていることを医学的に証明することが極めて重要です。
ここでは、医師の意見書の役割、証明に必要な書類、そして立証に向けた準備について解説します。
(1)医師の意見書の役割
医師が作成する後遺障害診断書や意見書は、後遺障害認定において非常に重要な役割を果たします。
これらは、被害者の症状が交通事故に起因するものであること、治療の経過、症状固定時の状態、そして将来にわたって残存する後遺症の程度や内容を医学的な見地から客観的に記載するものです。
特に、腱板損傷による可動域制限や痛みが後遺障害として認められるためには、医師が作成する詳細な診断書や意見書が不可欠となります。
弁護士は、医師との連携を通じて、後遺障害認定に必要な情報を的確に診断書や意見書に反映させられるようサポートします。
(2)証明に必要な書類
後遺障害認定の申請や損害賠償請求を行う際には、以下のような書類が必要または有効となります。
これらの書類は、被害者の怪我の状況、治療の経過、そして後遺症の存在を客観的に証明する根拠となります。
- 交通事故証明書:事故の事実を公的に証明する書類です。
- 診断書:初診時からの診断、怪我の部位や内容、症状などが記載されます。
- 診療報酬明細書:治療費の詳細が記載された書類です。
- レントゲン画像、MRI画像、CT画像など:腱板損傷の有無や程度を客観的に示す画像検査のデータです。特にMRIは腱板の損傷状況を詳細に評価する上で重要です。
- 各種検査結果:関節の可動域測定結果など、機能障害の程度を示すデータです。
- 後遺障害診断書:症状固定時に医師が作成する書類で、後遺症の内容や程度が詳細に記載されます。後遺障害認定の申請に不可欠な書類です。
- 意見書:医師が作成する、症状や治療に関する詳細な意見が記載された書類です。
- 診療録:入院していた場合に、身体の状況や介護の必要性などが記載されます。
これ以外の書類も状況に応じて必要になる場合がありますが、被害者自身で全てを収集するには負担が大きいため、弁護士に依頼してスムーズに収集できるようサポートしてもらうことをお勧めします。
(3)立証に向けた準備
後遺障害の立証に向けた準備は、治療中から始まります。
- 早期の受診と継続的な治療:事故後、肩に痛みや違和感を感じたら、速やかに整形外科を受診しましょう。そして、医師の指示に従い、中断することなく治療を継続することが重要です。事故発生から2週間以上経過した段階での受診や、治療中1か月以上の治療の中断は、交通事故と怪我の因果関係を否定される可能性があるため注意が必要です。
- 医師との密な連携:症状の変化や治療の経過について、医師に詳細に伝え、診断書や意見書に正確に反映してもらうよう依頼しましょう。
- 症状の記録:日々の痛みの程度、可動域制限の状況、日常生活での支障などをメモに残しておくことが有効です。これは、後遺障害認定の際の参考資料となり得ます。
- 専門医への紹介:必要に応じて、腱板損傷の専門医や高次医療機関への紹介を受け、より専門的な診断や治療を受けることも検討しましょう。
これらの準備が十分になされていないと、後遺障害が認められなかったり、適切な等級が認定されなかったりする可能性があります。
3.保険会社とのやり取り
交通事故の被害者にとって、保険会社とのやり取りは精神的な負担が大きく、専門知識が必要となる場面が多々あります。
ここでは、保険会社の対応と注意点、交渉のポイント、そして保険金請求の流れについて解説します。
(1)保険会社の対応と注意点
交通事故の後、加害者側の保険会社から連絡が入り、治療費の支払いや休業損害・慰謝料に関する提示が行われます。
しかし、保険会社は営利企業であり、自社の基準で損害額を提示してくることがほとんどです。
この提示額は、弁護士が交渉して獲得できる金額よりも低い場合が多く、特に示談交渉の最終段階で提示される示談金は、被害者にとって不利な内容である可能性があります。
注意点としては、以下が挙げられます。
- 安易に署名・捺印をしない:保険会社から送られてくる書類には、安易に署名・捺印をしないように注意しましょう。
- 安易に症状固定の打診に応じない:保険会社は、治療期間が長引くと、治療費の支払いを打ち切るために「症状固定」を打診してくることがあります。しかし、症状固定の判断は、医師が行うべきものであり、保険会社の都合で決定されるものではありません。
- 安易に示談を了承しない:保険会社からの初期の示談提案は、自賠責保険の基準や任意保険の独自基準(いわゆる相場)に基づくことが多く、裁判基準(弁護士基準)と比較して大幅に低い金額である可能性が高いです。
(2)交渉のポイント
保険会社との交渉を有利に進めるためには、慰謝料の増額も視野に入れた戦略が重要です。以下のポイントを押さえることが重要です。
- 適正な損害額の算定:治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など、発生した損害の総額を正確に算定することが不可欠です。特に後遺障害が残った場合には、後遺障害等級に応じた逸失利益の計算が重要となります。
- 後遺障害等級の認定:肩腱板損傷の後遺障害は、肩関節の可動域制限などによって10級10号などの等級が認定される可能性があり、12級6号が認定される事例もあります。適切な等級認定を受けることが、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益の獲得に直結します。
- 裁判基準(弁護士基準)の適用:保険会社が提示する金額は、自賠責保険基準や任意保険基準であることがほとんどです。しかし、弁護士が介入することで、過去の裁判例に基づいた最も高額な基準である裁判基準(弁護士基準)で交渉を進めることが可能になります。
- 専門家による交渉:弁護士は、法的な知識と交渉経験を活かし、保険会社の主張に対して的確に反論し、被害者の権利を守るために粘り強く交渉します。
(3)保険金請求の流れ
交通事故の損害賠償請求は、一般的に以下のような流れで進行します。
- 事故発生・警察への連絡:事故が発生したら、速やかに警察に連絡し、事故状況の確認を行ってもらいます。
- 病院での診察・治療:痛みや違和感がなくても、必ず病院で診察を受けましょう。腱板損傷などの怪我は、後になって症状が現れることもあります。診断書は必ず保管してください。
- 保険会社への連絡:自身の保険会社と相手方の保険会社に事故が発生したことを連絡します。
- 治療の継続:医師の指示に従い、症状が固定するまで治療を継続します。症状や状況に応じて、整骨院等での治療を検討できる場合もあります。
- 症状固定・後遺障害診断:医師がこれ以上の治療による改善が見込めないと判断した時点で「症状固定」となります。この時点で後遺症が残っていれば、後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害認定の申請を行います。
- 後遺障害等級の認定:損害保険料率算出機構(自賠責保険調査事務所)が提出された書類に基づき、後遺障害等級の審査を行います。等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能になります。
- 示談交渉:後遺障害等級が認定された後、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などの損害賠償額について、保険会社と示談交渉を行います。
- 示談成立・賠償金支払い:示談が成立すれば、示談書を締結し、保険会社から賠償金が支払われます。
この流れの中で、弁護士は被害者の立場に立ち、各段階で適切なアドバイスとサポートを提供します。
4.交通事故後の弁護士の役割
交通事故による肩腱板損傷は、被害者に大きな精神的・経済的な負担を与えます。
弁護士は、被害者の権利を守り、適切な賠償を得るために様々なサポートを行います。
ここでは、弁護士の選び方と相談方法、無料相談の活用方法、そして弁護士に依頼するメリットについて解説します。
(1)弁護士の選び方と相談方法
交通事故問題を専門とする弁護士を選ぶことが重要です。
当弁護士法人のように、交通事故の解決実績が豊富で、専門知識を持つ事務所を選ぶことが重要です。
ホームページや紹介などを通じて、弁護士の専門性や実績を確認しましょう。
また、実際に相談してみて、親身になって話を聞いてくれるか、説明が丁寧で分かりやすいかなども判断材料となります。
弁護士への相談方法としては、電話、メール、オンライン相談、面談などがあります。
多くの法律事務所では、初回相談を無料で行っているため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
相談の際には、事故の状況、怪我の状況、治療の経過、保険会社とのやり取りなど、できるだけ詳しく伝えることが大切です。
(2)無料相談の活用方法
無料相談は、弁護士に依頼するかどうかを検討する上で非常に有効な手段です。
無料相談を最大限に活用するために、以下の点に注意しましょう。
- 事前に相談内容を整理しておく:聞きたいことや伝えたいことをメモにまとめておくと、限られた時間を有効に使えます。
- 関係書類を持参する:事故証明書、診断書、保険会社の提示書など、関連する書類を持参すると、より具体的なアドバイスを受けることができます。
- 弁護士の経験や実績を確認する:交通事故事件の解決経験や、特に肩腱板損傷のような事例の経験があるかなどを質問してみましょう。
- 費用体系について確認する:弁護士に依頼した場合の費用(着手金、報酬金など)やその理由について、明確に説明を受けるようにしましょう。
複数の弁護士に相談してみることも、自分に合った弁護士を見つけるためには有効な方法です。
(3)弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害者が弁護士に依頼することには、以下のような多くのメリットがあります。
- 適正な損害賠償額の獲得:弁護士は、法的な知識や過去の判例・裁判例に基づいて、適正な損害賠償額を算定し、保険会社との交渉を有利に進めます。
- 煩雑な手続きからの解放:示談交渉や後遺障害認定の手続きなど、複雑で時間のかかる作業を弁護士に任せることができます。これにより、被害者は治療に専念することが可能となります。
- 精神的な負担の軽減:保険会社とのやり取りや、今後の見通しなどについて弁護士に相談することで、精神的な不安や負担を軽減することができます。
- 裁判になった場合の対応:示談交渉が決裂し、裁判になった場合でも、弁護士が代理人として対応します。
交通事故による肩腱板損傷は、症状が重い場合、後遺障害として残る可能性も十分に考えられ、損害賠償額も高額になるケースが多くなります。
弁護士費用が気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士費用特約に加入していれば、費用は保険で賄われることがほとんどです。
特約がない場合でも、着手金無料や成功報酬型の料金体系を採用している事務所もありますので、まずは無料相談をご利用いただき、費用について確認してみましょう。
交通事故による肩腱板損傷でお困りの方は、一人で悩まず、まずは当弁護士法人にご相談ください。
経験豊富な弁護士が、あなたにとってより良い問題解決となるよう尽力いたします。
投稿者プロフィール

これまで、交通事故・離婚・相続・労働などの民事事件を数多く手がけてきました。今までの経験をご紹介しつつ、皆様がお困りになることが多い法律問題について、少しでも分かりやすくお伝えしていきます。
■経歴
2009年03月 法政大学法学部法律学科 卒業
2011年03月 中央大学法科大学院 修了
2011年09月 司法試験合格
2012年12月 最高裁判所司法研修所(千葉地方裁判所所属) 修了
2012年12月 ベリーベスト法律事務所 入所
2020年06月 独立して都内に事務所を開設
2021年3月 優誠法律事務所設立
2025年04月 他事務所への出向を経て優誠法律事務所に復帰
■著書
こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。