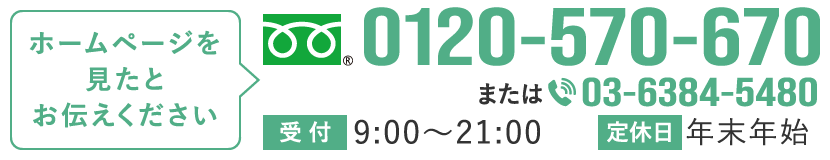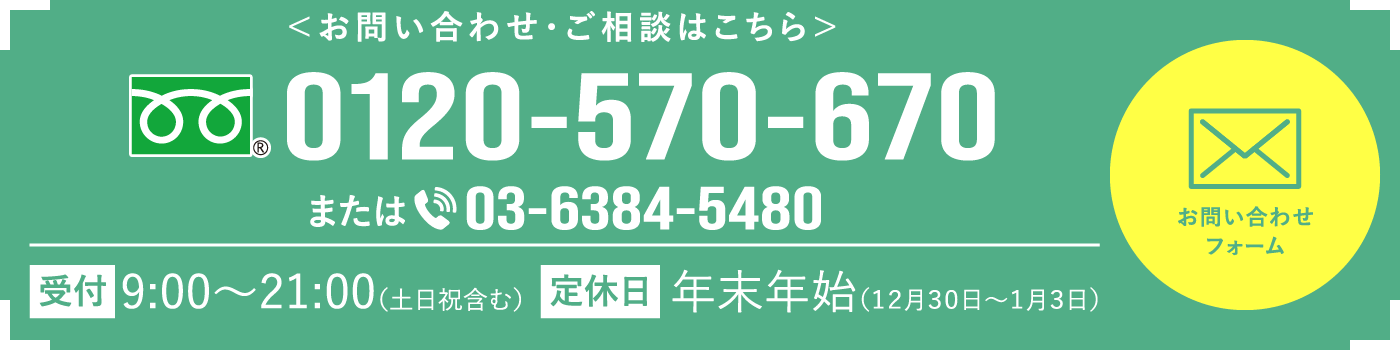今回は、交通事故による肩腱板損傷の後遺障害について、裁判例を交えて解説いたします。
肩腱板損傷は、肩の腱板(棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋という4つの筋肉の腱)が傷ついたり、部分的に、あるいは完全に断裂したりする損傷を指します。
この損傷は、日常生活において様々な苦労をもたらすことがあります。具体的には、痛み、可動域制限、筋力低下や脱力感等です。
このように、腱板損傷は、日常生活において大きな苦労を伴う損傷といえます。
したがって、交通事故や労災事故等によって肩腱板損傷を負った場合、その苦労に見合った適正な賠償額が保険会社から支払われなければなりませんし、そのための知識をつけておくこと重要です。
このページの目次
1.過去の裁判例から学ぶ~後遺障害認定の傾向と注意点~
冒頭で触れたように、交通事故によって負った肩腱板損傷は、その後の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
適切な補償を受けるためには、後遺障害の認定が極めて重要ですが、その判断は非常に複雑です。
特に、事故前から存在した加齢による変性との区別が争点となるケースが多く、この争点について判断している裁判事例もあるところです。
後遺障害の等級は、症状の程度、治療経過、そして医学的所見等に基づいて総合的に判断されます。
肩腱板損傷の場合、主に以下の等級が検討の対象となります。
<8級6号>
肩関節の可動域が健側の10%程度以下に制限されている場合。
「関節の用を廃したもの」とされ、重度の機能障害が認められるケースに適用されます。
<10級10号>
肩関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されている場合。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とされ、比較的重度の機能障害が認められるケースに適用されます。
<12級6号>
肩関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されている場合。
「関節の機能に障害を残すもの」とされ、10級10号ほどではないものの、機能制限が存在する場合に該当します。
<12級13号>
痛みが「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められる場合。
他覚的所見(MRIなど)で痛みの原因となる腱板損傷が確認でき、その痛みが継続している場合に認定されます。
<14級9号>
痛みが「局部に神経症状を残すもの」と認められる場合。
他覚的所見(MRIなど)で痛みの原因となる腱板損傷が確認できないものの、その痛みが継続している場合に認定されます。
これらの等級認定をするにあたり、裁判所が重視しているポイントをいくつかピックアップいたします。
① 肩腱板損傷と交通事故との因果関係に関する立証
肩腱板損傷は、外傷以外にも加齢による変性や日常生活での負荷によっても発生し得るため、事故によって生じた損傷であることの証明が最も重要です。事故直後からの症状の一貫性、事故態様と受傷内容の整合性、そして事故以前に同様の症状がなかったことの証明が重要です。
② 医学的所見の存在
特にMRI画像は、腱板損傷の有無、断裂の程度、損傷の新鮮さ、筋萎縮や脂肪浸潤の有無などを客観的に示す上で決定的な証拠となります。医師による診断書だけでなく、画像所見そのものが後遺障害認定に大きく影響します。そのため、事故直後にMRI検査を行うことが重要です。
③ 治療経過の一貫性と適切性
これは特に、神経症状に関する後遺障害等級において関連しますが、受傷直後から症状固定に至るまでの治療内容、治療効果、そして症状固定の時期の適切性です。漫然とした治療や、症状の訴えに一貫性がない場合は、認定が難しくなることがあります。
2.腱板損傷の慰謝料相場は?
慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。以下にそれぞれの目安を紹介します。
・入通院慰謝料の目安
入院や通院日数・期間に応じて計算されます。
- 例えば、6か月通院した場合:約50万円〜116万円(自賠責基準・弁護士基準で異なります)
- 慰謝料の計算は治療の必要に応じて通院をした結果に基づくものではありますが、自賠責基準では通院回数が少ないと慰謝料が低く算定されるため、その点からも継続的な通院は大切です。
・後遺障害慰謝料の目安(等級別)
腱板損傷が後遺障害と認定されれば、慰謝料の金額は一気に上がります。
| 等級 | 慰謝料(弁護士基準) | 逸失利益の考慮 |
| 10級 | 約550万円 | 収入の27% |
| 12級 | 約290万円 | 収入の14% |
| 14級 | 約110万円 | 収入の5% |
3.慰謝料請求の流れと損害賠償の注意点
事故後は以下のような流れで進めるのが一般的です。
- 事故後すぐに通院:初診が遅れると事故との因果関係を疑われます。
- 診断書の取得:腱板損傷の診断が明記されたものが必要です。
- 症状固定の判断:ある程度(一般的には6ヶ月程度)治療を続けた後、医師により”これ以上の回復が見込めない”と判断された時点です。
- 後遺障害等級の申請:自賠責保険(損害保険料率算出機構)に申請します。
- 示談交渉:保険会社との間で慰謝料などを決定。専門家がいないと過少評価されるリスクが高いです。
4.裁判例に基づく後遺障害認定の可能性の評価~あなたのケースはどうなる?~
ご自身の肩腱板損傷が後遺障害として認定される可能性を評価する際には、裁判事例から見えてくる基準とご自身の状況を照らし合わせることが有効です。
裁判事例を踏まえ、後遺障害が認められる可能性が高いと考えられるケースの一般的な特徴は、次のとおりです。
① 受傷直後からの明確な症状
これは特に、神経症状に関する後遺障害等級において関連しますが、事故後、速やかに医療機関を受診し、その後も一貫して肩の痛みを訴えて症状が継続していること。
② 客観的な画像所見の存在
MRI画像において、明らかな腱板の断裂(完全断裂、部分断裂を問わず)や損傷が確認できる場合。新鮮な損傷を示す所見(出血、浮腫など)があれば、事故との因果関係がより強く裏付けられます。
③ 可動域制限の正確な測定
医師による正確な計測によって、肩関節の自動運動(自分で動かせる範囲)だけでなく、他動運動(他人に動かしてもらう範囲)にも明らかな制限が認められる場合。これにより、痛みのために動かせないだけではない器質的な問題があることが裏付けられます。
④ 主治医の積極的な意見
主治医が、後遺障害診断書に具体的に症状や他覚的所見を記載するとともに、事故との因果関係や症状の程度について医学的な見地から肯定的な意見を示している場合。
一方、後遺障害が認められる可能性が低いと考えられるケースの一般的な特徴は、次のとおりです。
① 事故から医療機関の受診までに時間が空いたケース
そもそも事故との因果関係が問題視されてしまうリスクが高いです。
② 事故前に肩に何らかの症状があった、または加齢による変性が顕著なケース
事故による新たな損傷か、既存の症状の悪化かを区別することが難しくなります。
③ 他覚的所見が確認できないケース
他覚的所見が無いため、可動域制限に関する後遺障害等級の認定は難しくなります。もっとも、神経症状に関する後遺障害等級14級9号については、他覚的所見が無くても認定される可能性が残ります。
④ 後遺障害診断書において、因果関係や症状の程度等が曖昧にされているケース
後遺障害診断書は、後遺障害等級を判断するにあたり非常に重要な書類であるため、その記載内容が不十分であると不利に影響します。
ご自身の状況がこれらのいずれに該当するかを確認し、特に「事故との因果関係の証明」と「客観的な医学的所見の提示」に力を入れることが、後遺障害認定の可能性を高める上で重要です。
5.事例紹介とその解説~具体的な裁判例から学ぶ~
それでは具体的な裁判事例を通して、肩腱板損傷の後遺障害認定がどのように判断されているかを見てみましょう。
これらの事例は、実際の裁判所での判断基準を理解する上で非常に参考になります。
【事例1:可動域制限の後遺障害を主張したものの14級9号が認定されたケース】
<事案概要>
50代男性(原告)がタクシーを運転して交差点を右折しようとしたところ、対向車線を直進してきた相手車両と衝突したことにより交通事故が発生しました。原告は、右肩腱板損傷に基づく可動域制限を主張し、その後遺障害等級に該当することを主張しました。
<裁判所の判断(東京地裁平成30年11月20日判決)>
「右肩甲部から右上肢の疼痛に関しては、①原告は、本件事故後から右肩関節部の疼痛、圧痛、運動時痛を一貫して訴えており、本事故以前にそのような痛みが生じていたものとはうかがわれないこと、②平成24年7月10日に実施された右肩のMRI検査の結果、右肩関節棘上筋腱に脂肪抑制T2WIにて高信号域が見られ、損傷の所見があるものとされ、右肩関節腱板損傷との所見が示されており、丁山四郎医師の意見書や戊田五郎医師による鑑定報告書においても、右肩棘上筋の損傷や関節唇の損傷がみられるとの所見が示されていること、③本件事故態様や衝撃の程度等からすると、原告には、本件事故により、右肩に腱板損傷が生じ、右肩の疼痛が生じたものと推認される。もっとも、右肩の可動域は、自動値については制限がみられるものの、他動値では大きな制限はみられず、右肩関節の機能障害が生じたものとまでは認めるに足りない。」、「原告には症状固定後も、①右肩甲部から右上肢の疼痛・・が残存したものと認められるところ、①については後遺障害等級14級9号・・に該当・・したものと認めるのが相当である。」
<解説>
この事例から、自動運動が制限されていても、他動運動が制限されていなければ、可動域制限に関する後遺障害等級が認定されることは難しいことが分かります。
【事例2:被告からの反論を退けて12級6号が認定されたケース】
<事案概要>
50代男性(原告)が自動二輪車に乗車して直進していたところ、対向車線から転回してきた相手車両に衝突されたことにより交通事故が発生しました。これにより、原告は、左肩腱板損傷等の傷害を負い、自賠責保険会社から、左肩関節機能障害について12級6号の認定を受けていました。これに対し、被告側は、左肩関節の可動域制限と本件事故との因果関係について反論をしていました。
<裁判所の判断(神戸地裁令和元年6月26日判決)>
「原告はE自賠責損害調査事務所によって後遺障害等級併合12級と認定されているところ、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、原告には、本件事故によって受傷した左肩腱板損傷後の左肩関節について、健側(右肩関節)の可動域と比較して3/4以下の可動域制限が残存するという機能障害とともに、右足関節外果部に瘢痕があり・・原告には、後遺障害等級12級6号及び14級5号にそれぞれ該当する後遺障害が残存し、これを併合12級と評価するのが相当である。」、「この点、被告らは、原告の左肩関節の可動域制限と本件事故との因果関係に疑問を呈するとともに、その実質は疼痛という神経症状の範疇に止まる旨主張するところ、なるほど、事故から約7ヶ月が経過した平成30年2月26日のC整形外科の診療録において初めて左肩可動域制限に関する記載があると認められ、それまでのB病院の診療録では可動域制限なしとされ、他に上記日時までは可動域制限に関する記載がC整形外科の診療録にも見当たらず、また原告は事故後2ヶ月余が経過した平成29年9月ころに左肩の痛みがやや軽減し、又はほぼない旨医師に告げていることが認められる。」、「もっとも、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件事故から2日後の平成29年7月13日にC整形外科においてMRI検査を受けた結果、左肩、肩甲下筋腱に損傷があると診断されており、そのころ相当程度の疼痛を訴えていたこと、腱板損傷による疼痛等のため、原告は左肩をできるだけ動かさず、安静にする必要があったこと、医学的知見として、①腱板損傷が生じると時間の経過とともに断裂は拡大し、筋の萎縮が進行する、②関節可動域の制限には発生進行に関節の不動が影響するものであり、関節の不動によって拘縮が発生し、不動期間が長期化するほど拘縮が進行する、とされていること等の事実が認められ、これらの事実に徴すると、原告には、損害保険料率算出機構が認定したとおりの左肩関節の機能障害が残存し、その程度は後遺障害等級12級6号に該当するとの認定は覆らない。」
<解説>
この事例は、診療録に可動域制限なしと記載されていても、左肩関節の機能障害が残存していると評価された点が重要です。このように、裁判所は、様々な事情を総合考慮した上で、可動域制限の後遺障害等級について判断していることが分かります。
6.まとめ
このように、肩腱板損傷の後遺障害等級認定は、様々な事情を総合考慮した上で審査が行われます。
そのため、肩腱板損傷を負った被害者としては、後遺障害等級認定に有利な事情を主張立証しなければなりません。
一般の方が、これらの主張立証をすることは難しいと思われるため、適切な主張立証をされたい場合には、交通事故を専門とする弁護士に相談するべきであるといえます。
弁護士法人優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。
全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事が、肩腱板損傷でお困りの被害者の皆様の解決に少しでもお役に立てれば幸いです。
投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。