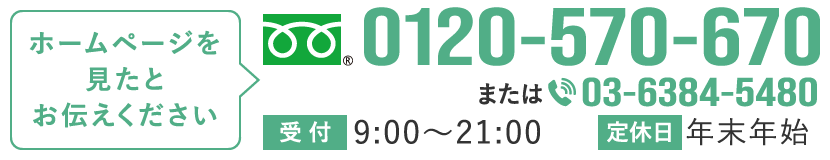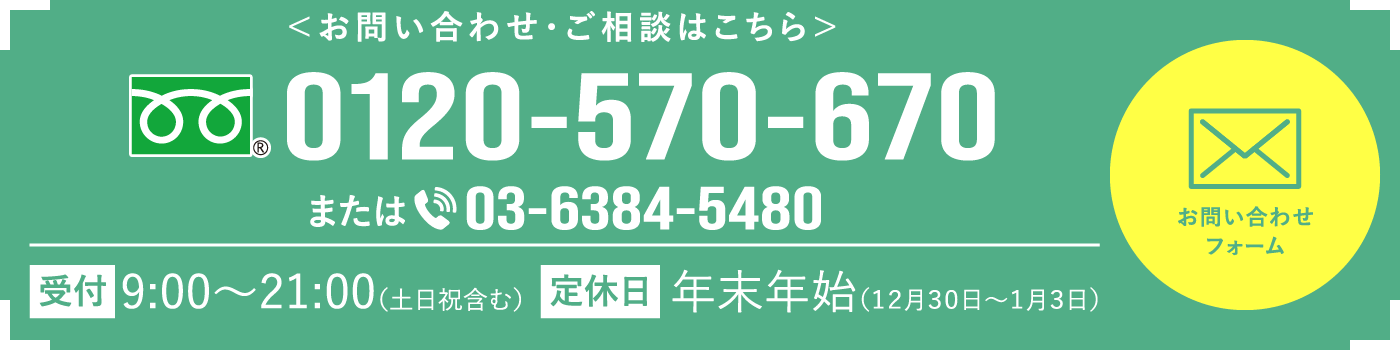交通事故に遭ってしまい、お怪我をされた被害者の方にとって、治療に専念することは何よりも重要です。
しかし、治療の途中で保険会社から「治療費の打ち切り」を打診されたり、提示された慰謝料や治療費の金額に納得がいかなかったりするケースは少なくありません。
適切な賠償金を受け取るためには、治療の期間や慰謝料の計算方法、そして保険会社との交渉の進め方について、正しい知識を持っておく必要があります。
本記事では、交通事故後の治療における「打ち切り」や「減額」への具体的な対処法、そして適切な治療・通院期間を確保するための交渉術について、詳しく解説します。
このページの目次
1.打ち切りや減額への対処法と期間延長のコツ
交通事故後、治療を続けていると、保険会社から「そろそろ治療を打ち切りませんか?」と打診されることがあります。
これは、保険会社が支払う治療費や慰謝料などの損害賠償金を抑えたいという意図が背景にあることがほとんどです。
しかし、まだ痛みが残っているのに治療を中断してしまうと、後遺症が残る可能性や、本来受け取れるはずの慰謝料が大幅に減額されてしまう可能性があります。
【治療継続の重要性】
- 適切な治療を受ける権利:被害者には、交通事故による怪我が完治するまで、あるいは症状固定となるまで治療を受ける権利があります。
- 後遺障害の適正な認定:治療を適切に継続し、症状が残った場合に後遺障害の認定を申請することで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの高額な賠償金を請求できる可能性があります。
- 慰謝料の増額:入院や通院の期間が長いほど、それに伴い慰謝料の金額も計算上高くなる可能性があります。
【減額リスクを回避する方法】
保険会社からの打切り打診に安易に納得せず、以下の点に注意して対処することが重要です。
- 医師との連携:治療の必要性を一番理解しているのは医師です。保険会社から打ち切りを打診されたら、まず主治医に相談し、治療の継続が必要であるという診断・見解を明確にしてもらいましょう。
- 弁護士への相談:保険会社は交渉のプロです。被害者が個人で交渉を進めるのは非常に困難な場合が多いため、交通事故案件に強い弁護士に相談し、交渉を依頼することで、治療費の打ち切りを阻止し、適切な治療期間を確保できる可能性が高まります。
2.保険会社からの治療打ち切り打診への対応策
保険会社が治療の打ち切りを打診してくる時期の目安として、むちうちなどの軽傷の場合で事故から2~3ヶ月程度、骨折などの場合は6ヶ月程度が多いと言われています。
しかし、これはあくまで保険会社の「独自の基準」であり、医学的な治療の必要性とは異なります。
【保険会社の言い分に対する対処法】
- 治療の必要性を具体的に主張する:まだ痛みが残っており、日常生活に支障がある場合は、その症状を具体的に保険会社に伝えましょう。「まだ痛みが残っていて、仕事や家事に支障がある」「夜眠れない」といった具体的な症状を説明することが大切です。
- 医師の意見書・診断書:主治医に現在の症状や今後の治療の必要性について記載された診断書や意見書を作成してもらえるのであれば有用です。特に「治療を継続する必要性がある」といった内容が記載されていると、保険会社も治療の打ち切りを強行しにくくなります。MRIなどの検査結果も、症状の証明として有効です。
- 安易な同意はしない:保険会社から「そろそろ症状固定ですね」と言われても、医師がまだ治療の継続を必要と判断している場合は、絶対に安易に同意してはいけません。症状固定は、医師が医学的に判断するものであり、保険会社が決めることではありません。
- 弁護士に依頼する:保険会社との交渉が困難だと感じたら、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士が代理人となることで、保険会社は被害者本人への直接の打ち切り打診ではなく、弁護士と交渉せざるを得なくなります。弁護士は、医学的な知識と法律的な知識に基づき、治療の継続の必要性を保険会社に強く主張し、適切な期間の治療を勝ち取るための交渉を行います。
- 自賠責への被害者請求を行う:以上のような方策をとったとしても、相手損保が治療を強行的に打ち切ってくることはあります。そのような場合は、加害者加入の自賠責保険へ被害者請求と呼ばれる方法をとることによって、治療費を確保できる可能性があります。
3.慰謝料や治療費の減額リスクを回避する方法
慰謝料や治療費が不当に減額されることを防ぐためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
【適切な通院と治療の記録】
- 適切な頻度での通院:治療費や慰謝料は、通院の期間や日数が計算の基準となるため、医師の指示に従い、適切な頻度で通院することが重要です。通院頻度が少ないと、「症状が軽度である」と保険会社に判断され、慰謝料の減額につながる可能性があります。
- 自己判断での治療中断は避ける:症状が一時的に改善したように感じても、医師の指示なく治療を中断してはいけません。治療の中断は、保険会社に「もう治療の必要がない」と判断される原因となり、治療費の支払いを打ち切られたり、慰謝料が大幅に減額されたりする可能性があります。
- 治療経過の記録:ご自身の症状の変化、通院状況、治療内容、日常生活への支障程度などを細かく記録しておくことが重要です。これは、後の損害賠償請求において、症状の継続性や治療の必要性を証明するための有力な証拠となります。
【慰謝料計算の基準と弁護士の必要性】
慰謝料の計算には、主に以下の3つの基準があります。
①自賠責基準:自賠責保険で定められた基準で、3つの基準の中で最も金額が低いです。被害者の最低限の救済を目的としています。
②任意保険基準:各任意保険会社が独自に設定している基準で、自賠責基準よりは高いですが、次に述べる弁護士基準よりは低い金額になることがほとんどです。
③弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づいた基準で、3つの基準の中で最も高額になる可能性があります。
保険会社は、基本的に任意保険基準か自賠責基準で慰謝料を提示してきます。
しかし、弁護士が交渉を行う場合は、弁護士基準での慰謝料を請求することが可能になります。
これにより、慰謝料の増額を獲得できる可能性が大きく高まります。
弁護士に依頼することで、慰謝料が2倍、3倍になるケースもあり得ます。
【後遺障害等級認定の重要性】
症状固定後も痛みや痺れなどの症状が残ってしまった場合は、後遺障害の等級認定を申請することが重要です。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになり、賠償金の金額が大きく変わります。
- 医師への正確な症状の伝え方:後遺障害の認定には、医師が作成する「後遺障害診断書」の内容が非常に重要です。痛みや症状を具体的に、正確に医師に伝え、診断書に記載してもらうようにしましょう。
- 専門家によるサポート:後遺障害の認定は複雑な手続きを伴います。弁護士は、後遺障害の認定手続きのサポートも行っており、適正な等級が認定されるよう、必要な書類作成のアドバイスや、異議申立ての手続きなどを支援します。
4.治療・通院期間の決定や延長を勝ち取るための交渉術
治療の打ち切りを打診されたり、保険会社から「そろそろ症状固定なので治療を終了してください」と促されたりする場合、被害者側としては、適切な治療期間を確保するために、毅然とした交渉が必要になります。
【交渉のポイント】
- 医師の診断が最優先:治療期間の決定において、最も尊重されるべきは医師の医学的な診断です。保険会社がいくら治療の打ち切りを主張してきても、主治医が「まだ治療が必要である」と判断している場合は、その医師の意見を保険会社に明確に伝えましょう。
- 治療計画の具体化:主治医に、今後の治療の必要性、見込まれる治療期間、どのような治療を続けるのかといった具体的な治療計画を記載した書類を作成してもらえるのであれば、保険会社との交渉がスムーズに進む可能性があります。
- 症状固定の時期の慎重な判断:症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態」を指します。症状固定の判断は、究極的には事後的に裁判所が行うものですが、医師の判断が重視されます。保険会社が早急に症状固定を主張してきても、安易に応じることなく、ご自身の症状と医師の診断に基づいて慎重に判断しましょう。特にむちうちの場合、数ヶ月経過しても痛みが残るケースは少なくありません。
- 治療費の支払いを継続させる交渉:保険会社が治療費の支払いを打ち切りたいと主張してくる場合でも、弁護士が介入することで、治療費の支払いを継続させられるケースは多くあります。弁護士は、過去の裁判例や医学的な知見に基づき、治療の継続の必要性を保険会社に主張します。
5.当事務所での治療期間延長の具体例
当事務所でも、治療期間の延長について相手損保と交渉することは多くあります。
まずは、ご依頼者様の症状や治療状況を伺い、主治医が治療期間について何か意見をおっしゃっていないかを把握します。
場合によっては、主治医に治療期間についての意見照会を行うこともあります。
その上で、相手損保に対し、ご本人の症状、医師の意見などを伝え、治療期間の延長を交渉します。
無制限の延長申入れは相手損保もなかなか受け入れないことが多く、期間を明示して延長の申入れを行うことも多くあります。
事案にもよりますが、1~2ヶ月程度であれば延長できる事例が多く、少しずつ延長させて結果的に数ヶ月延ばすことができた事例もあります。
保険会社から治療費の打切りを打診されてお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
6.まとめ:弁護士への相談・依頼が解決への近道
交通事故の被害者は、怪我の痛みや精神的な負担を抱えながら、保険会社との交渉という大きなストレスに晒されます。
保険会社は示談交渉のプロであり、法律や医学に関する専門知識も豊富です。
そのため、被害者個人で交渉を行うと、不利な条件で示談が成立してしまう可能性が非常に高いのが実情です。
弁護士に依頼する最大のメリットは、被害者に代わって保険会社と交渉することで、被害者の負担を軽減し、適正な賠償金の獲得のサポートを受けられる点です。
- 弁護士費用特約の活用:ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、弁護士費用を保険でまかなえる可能性があります。この特約を利用すれば、自己負担なしで弁護士に依頼できるケースも多いため、まずはご自身の保険契約を確認してみましょう。
- 無料相談の利用:多くの法律事務所では、交通事故の無料相談を実施しています。治療の打ち切りや慰謝料の金額に不安がある場合は、気軽に相談してみることをお勧めします。
交通事故の被害者が直面する問題は多岐にわたりますが、弁護士のサポートを得ることで、治療に専念し、適正な損害賠償金を獲得できる可能性が高まります。
一人で抱え込まず、専門家に相談することで、より良い解決へと導かれることでしょう。
当事務所では、交通事故のご相談は全国から無料でお受けしております。
投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。
突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。