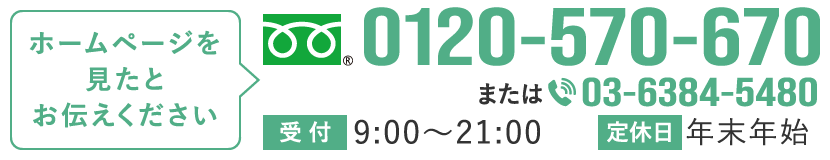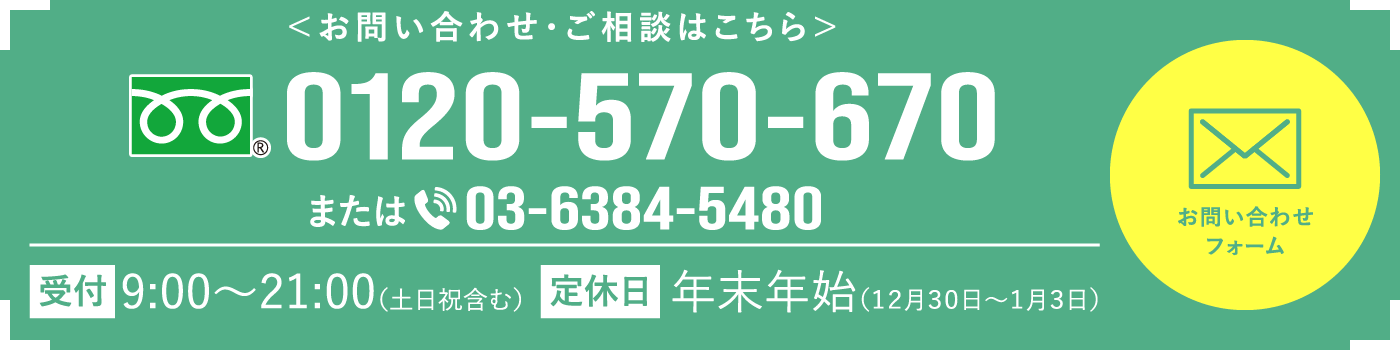交通事故に遭って怪我をした被害者の多くが、むち打ち(むちうち)の症状を負っています。
むち打ちは、レントゲンやMRIでは異常が見つかりにくいことも多いですが、その症状や後遺症が深刻なケースもあります。
また、MRIなどで自覚症状の客観的裏付けとなる所見が得られることが少ないため、加害者の保険会社が早期に治療費を打ち切ることもあり、適切な補償(慰謝料など)を受け取るためには、正しい知識と手続きが不可欠です。
この記事では、むち打ちによる後遺症が残ってしまった場合に、どのように慰謝料を請求すれば良いのか、そのポイントを詳しく解説します。
今回の記事が、むち打ちの被害に遭われた方の助けになれば幸いです。
このページの目次
1.後遺障害認定と等級別の慰謝料・逸失利益
交通事故によるむち打ちで症状が長引き、後遺症として残ってしまった場合、適切な慰謝料や逸失利益を受け取るためには「後遺障害認定」を受けることが非常に重要になります。
後遺障害認定とは、交通事故によって負ってしまった症状が、これ以上治療しても改善の見込みがないと判断された場合に、その症状を「後遺障害」として認定する制度です。
この認定を受けることで、精神的苦痛に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)や、後遺障害によって将来得られるはずだった収入の減少分(逸失利益)を請求できるようになります。
後遺障害には、その症状の重さによって1級から14級までの等級が定められており、それぞれの等級によって慰謝料の金額や逸失利益の算定方法が異なります。
むち打ちの場合、一般的には14級9号が認定されるケースが多いですが、症状によっては上位の12級13号の等級が認定されることもあります。
なお、症状が残っていれば必ず後遺障害等級が認定されるという訳ではなく、非該当と判断されるケースも多いです。
後遺障害認定を受けるためには、医師による適切な診断書やカルテ、検査画像などの医学的な証拠を揃えることが不可欠です。
また、医師に適切な診断書等を作成してもらうためには、治療期間中に自覚症状を具体的に、かつ、継続的に伝えることも重要になります。
後遺障害の申請手続きは複雑で、適切な証拠を揃えるためには専門的な知識が必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。
弁護士は専門家として、適切なサポートと助言を行い、後遺障害申請の手続きだけでなく、示談交渉や訴訟においても、被害者が適切な賠償を受けられるよう尽力します。
2.後遺障害申請・認定の流れと症状固定のタイミング
後遺障害の申請・認定は、治療の経過と密接に関わっています。
ここでは、一般的な後遺障害申請・認定の流れと、「症状固定」という重要なタイミングについて解説します。
⑴ 治療の継続と症状の経過観察
交通事故後、まずは医療機関で適切な治療を受け、症状の改善に努めます。
この期間中は、定期的に医師の診察を受け、症状の変化や痛みの状態などを具体的に伝えることが重要です。
治療経過の記録は、後遺障害申請の際に重要な証拠となります。
また、症状によって整形外科でリハビリや投薬治療が行われますが、整形外科だけでなく、必要に応じて脳神経外科やペインクリニックの受診を検討すべき場合もあります。
病院での治療費は、通常、加害者側の任意保険会社が負担しますが(これを「一括対応」といいます)、保険会社が対応してくれない場合には、健康保険の利用も可能です。
⑵ 症状固定の判断
一定期間治療を継続した後、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断する時点を「症状固定」と言います(症状固定と判断された時点までが交通事故の賠償範囲となりますので、治療費や慰謝料の支払いはこの時点までとなります。)。
この症状固定の判断は、後遺障害申請において非常に重要なタイミングです。
症状固定と判断された時点で、残ってしまった痛み・しびれなどの症状が「後遺障害」として評価される対象となります。
むち打ちの場合、症状固定の時期には個人差がありますが、一般的には事故から6ヶ月程度が目安とされています。
しかし、改善が見込めるのであれば、無理に症状固定とせず、症状が改善するまで治療を続けるという判断もあり得ます。
医師と十分に話し合い、ご自身の症状を考慮して症状固定のタイミングを判断してもらうようにしましょう。
⑶ 後遺障害診断書の作成
症状固定後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
この診断書は、後遺障害の有無や等級を判断する上で最も重要な書類となります。
後遺障害診断書には、自覚症状、他覚所見(神経学的所見、画像所見など)、今後の緩解の見通しなどが詳細に記載されます。
医師には、ご自身の症状を正確に伝え、具体的な記載をお願いすることが重要です。
特に、神経症状の検査結果や治療経過が詳細に記されていることが望ましいです。
⑷ 後遺障害の申請手続き
後遺障害診断書が作成されたら、いよいよ後遺障害の申請を行います。
申請方法は大きく分けて以下の2種類があります。
- 事前認定(加害者側の保険会社による申請): 加害者側の任意保険会社が、被害者に代わって自賠責保険に申請を行う方法です。手間はかかりませんが、保険会社が主体となるため、被害者にとって不利な認定になる可能性もゼロではありません。保険会社からの連絡や示談交渉は、この認定後に本格化します。
- 被害者請求(被害者側による申請):被害者自身や代理人の弁護士が、自賠責保険に直接申請を行う方法です。必要な書類を全て被害者側で集める必要がありますが、ご自身で有利な証拠を提出できるため、より適切な認定を受けられる可能性が高まります。弁護士に依頼すれば、書類収集や申請手続きのサポートを受けられます。
⑸ 損害保険料率算出機構による審査
自賠責保険に提出された書類は、「損害保険料率算出機構」に送られ、専門家による審査が行われます。
審査では、提出された書類に基づき、場合によっては医療機関に医療照会を行うなどして、残存する症状が後遺障害に該当するか、該当するとして何級に相当するかを判断します。
機構は中立な立場で、提出された医学的資料から客観的に判断を行います。
⑹ 後遺障害等級の認定
審査の結果、後遺障害に該当すると判断されれば、後遺障害等級が認定されます。
認定された等級は、書面で被害者に通知されます。
もし、認定された等級に不服がある場合は、「異議申立て」を行うことも可能です。
そして、この後遺障害申請の結果通知を受けた後、加害者側の任意保険会社との本格的な示談交渉に入ります。
賠償金の計算もこの後遺障害等級を基に行われます。
この一連の流れの中で、特に重要なのが「症状固定のタイミング」と「後遺障害診断書の記載内容」です。
適切な後遺障害認定を受けるためには、これらの段階で慎重に対応し、必要であれば専門家である弁護士の助言を仰ぐことが賢明です。
3.等級(14級・12級)別の慰謝料金額と判例
後遺障害等級は、交通事故による精神的苦痛を金銭的に評価する際の重要な基準となります。
ここでは、むち打ちで認定される可能性のある主な等級(14級、12級)について、それぞれの慰謝料の目安と、関連する判例の傾向を解説します。
⑴ 後遺障害慰謝料の算定基準
後遺障害慰謝料には、主に以下の3つの算定基準があります。
- 自賠責保険基準:自賠責保険が定める最低限の基準です。他の基準より低額ですが、被害者側に過失がある場合でも、7割未満であれば減額されることなく、被害者が全額を受け取れます。過失が7割以上になると、重過失減額が適用されます。
- 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定めている基準です。自賠責基準よりは高額になることが多いですが、保険会社によって金額に差があります。保険会社からの提示額は、この基準に基づいていることが多いです。
- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づいて算定される基準で、最も高額になる傾向があります。弁護士が交渉する際や、裁判になった場合に適用される基準です。適正な賠償金を受け取るには、この基準を目指すことが重要です。
【後遺障害等級別の慰謝料目安(弁護士基準)】
以下に示す慰謝料額は、弁護士基準の目安です。
自賠責保険基準や任意保険基準では、これよりも低額になることが多い点にご留意ください。
後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)
- 慰謝料目安:約110万円
- 特徴:むち打ちでは多くの場合、この等級が認定されます。神経症状が残存していることが要件となり、客観的な画像所見などがない場合でも、医学的に説明がつく場合に認定されます。例えば、頚部や肩の痛み、しびれなどが断続的に続くケースなどが該当します。頚椎捻挫、腰椎捻挫といった診断名が多く、外傷性頚部症候群もこれに該当します。
- 判例の傾向:14級9号の認定には、自覚症状の一貫性、治療経過、神経学的所見(例えば、ジャクソンテスト、スパーリングテストの陽性反応など)や画像所見(椎間板の変性など)などが考慮されます。明確な他覚所見がなくても、一貫した自覚症状と治療の継続性が認められれば認定される可能性があります。通院期間や通院頻度も重要な要素となります。
後遺障害12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
- 慰謝料目安:約290万円
- 特徴:14級9号よりも症状が重く、神経症状が「頑固」に残存していると認められる場合に認定されます。14級9号と異なり、画像所見や神経学的所見など、客観的な医学的所見による裏付けが求められます。
- 判例の傾向:12級13号の認定には、MRIやCTなどの画像診断で神経根の圧迫や損傷が明確に確認できること、神経伝導速度検査(NCV)や針筋電図(EMG)などの検査で神経症状の裏付けがあること、あるいは神経学的な所見(筋力低下、反射異常、感覚障害など)が明確であることが重視されます。これらの客観的な証拠が不足している場合、12級の認定は極めて困難になります。
⑵ 判例から見る慰謝料額の傾向
慰謝料の金額は、上記目安をベースに、個別の事案によって増減することがあります。
例えば、以下のような要素が考慮されます。
- 治療期間と内容:長期間の治療や、手術などの侵襲的な治療を受けた場合は、慰謝料が増額される可能性があります。
- 症状の重篤性:痛みの程度や日常生活への影響が大きいほど、慰謝料は高額になる傾向があります。
- 就労への影響:後遺障害によって仕事に大きな支障が出た場合、逸失利益とは別に慰謝料が増額されることがあります。
- 過失割合:被害者にも過失がある場合、その過失割合に応じて慰謝料が減額されます。
- 増額事由の有無:ひき逃げや飲酒運転など、加害者側に問題が大きい場合などは、慰謝料が通常よりも増額される傾向があります。
⑶ 慰謝料の種類と違い(通院・入院・後遺障害)
交通事故で請求できる慰謝料には、次の3種類があります。
・入通院慰謝料(傷害慰謝料):治療のために通院・入院を強いられた精神的苦痛に対する補償
・後遺障害慰謝料:治療後も症状が残った場合の精神的苦痛への補償
・死亡事故慰謝料:被害者が亡くなった場合に支払われる慰謝料
これらの慰謝料は、治療期間や後遺障害の等級に応じて大きく異なります。
重要なのは、裁判所基準の慰謝料もあくまで目安・相場であり、個別の事案によって判断が異なるということです。
特に、高額な慰謝料を請求するためには、弁護士に依頼し、適切な証拠を揃え、交渉を進めることが非常に重要になります。
4.後遺症が残った場合の逸失利益の請求方法
後遺障害が残ってしまった場合、精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、「逸失利益」も請求することができます。
逸失利益とは、後遺障害によって、将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償のことです。
むち打ちの後遺症によって、仕事に支障が出たり、以前のように働けなくなったりした場合に重要となります。
⑴ 逸失利益の計算方法
逸失利益は、以下の計算式で算出されます。
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
- 基礎収入
- 原則:事故前年の年収を基礎とします。源泉徴収票や確定申告書などで証明します。
- 個人事業主:原則としては、事故前年の確定申告の所得額を基礎として算定されます。
- 主婦・学生など:収入がない場合でも、賃金センサス(厚生労働省が発表する賃金に関する統計データ)の平均賃金を基礎収入とすることができます。主婦の場合、女性の全年齢平均賃金が用いられることが多いです。学生の場合、卒業後の就労状況を考慮して算定されます。休業損害の計算にもこの基礎収入の考え方が適用されます。
- 労働能力喪失率
後遺障害によって、どれだけ労働能力が失われたかを示す割合です。それぞれの後遺障害等級に応じて設定されます。むち打ちで認定される可能性のある等級の目安は以下の通りです。
・後遺障害14級9号:5%程度
・後遺障害12級13号:14%程度
※これはあくまで目安であり、実際の職業や業務内容、残存する症状が仕事に与える影響などを総合的に考慮して判断されることもあります。減収の実態を客観的に示すことも重要です。 - 労働能力喪失期間
後遺障害によって労働能力が喪失する期間です。原則として、症状固定時から67歳までの期間とされます。ただし、むち打ちによる後遺障害の場合、症状の経過や年齢によって、喪失期間が限定されるケースもあります。例えば、14級9号の場合、症状の継続期間が短いと判断され、5年間程度に限定されることが多いです。 - ライプニッツ係数
将来の収入減少分を現在の一括払いに換算するための係数です。将来受け取るはずだった金銭を前倒しで受け取るため、その期間の利息分を割り引くためのものです。労働能力喪失期間に応じて係数が決まっています。
⑵ 逸失利益請求のポイント
- 正確な基礎収入の証明
事故前年の収入を証明する書類を確実に準備しましょう。
転職したばかりの場合や、個人事業主の場合は、複数年の収入実績を示すことでより正確な基礎収入を算定できます。 - 労働能力喪失率の適正な主張
労働能力喪失率は、等級によって目安はありますが、個々のケースで実際の労働への影響を具体的に主張することが重要です。
医師の診断書や、仕事内容の詳細、実際に支障が出ている業務内容などを具体的に説明できるように準備しましょう。 - 労働能力喪失期間の交渉
むちうちのケースでは、将来にわたる症状の継続性について争われることがあります。
医師の意見書や治療の継続状況、症状の一貫性などを示すことで、より長い期間の喪失期間を主張できる可能性があります。 - 弁護士への相談
逸失利益の計算は複雑であり、保険会社との交渉においても専門知識が不可欠です。
特に、将来の収入減少をどのように評価するかは、個別の事情によって大きく異なります。
弁護士に相談することで、適正な逸失利益の算定と、有利な交渉を進めることが可能になります。
弁護士費用は着手金や報酬金などがありますが、多くの弁護士事務所で無料相談を行っており、弁護士費用特約がある場合は、自己負担なく依頼できることも多いです。
5.被害者請求による異議申立てで14級9号が認定された頚椎捻挫の事例
さて、ここからは当事務所にご依頼いただいた依頼者様の具体的な事例をご紹介します。
⑴ 事案の内容~事前認定で後遺障害を申請するも非該当~
Hさんは、地元の北海道で自動車を運転中、信号待ちで停車している際に、後方から走行してきた後続車に追突される事故に遭いました。
加害者は、よそ見をしていて衝突の直前まで赤信号に気が付いておらず、かなりのスピードで追突したため、Hさんの車両の後部は大きく損傷しました。
この交通事故で、Hさんはむち打ち(頚椎捻挫)の怪我を負い、整形外科と整骨院で治療をしていましたが、事故から6ヶ月で加害者側保険会社が治療費を打ち切ったため、主治医もそのタイミングで症状固定の診断をしました。
しかし、その時点でも首の痛みや手のしびれなどの症状が残っていました。
そのため、Hさんは、加害者側保険会社の説明を受けて、主治医に後遺障害診断書を作成してもらった上で、そのまま保険会社に任せて事前認定で後遺障害の申請をしました。
ところが、非該当の結果となり、それを前提に加害者側保険会社から示談金として約120万円を提示されました。
これに納得できなかったHさんは、インターネットで検索して、当ホームページの異議申立てで後遺障害等級が認定された事案の記事をご覧になったとのことで、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。
⑵ 異議申立てで14級9号を獲得
Hさんからご依頼を受け、担当弁護士は、主治医にカルテ開示の依頼や医療照会を行って、Hさんの治療状況や症状経過に関する証拠を収集し、Hさんからも事故後からの症状の推移や残存している痛みやしびれの症状などについて聞き取りを行いました。
そして、自賠責保険に対して被害者請求で異議申立てをしました。
その結果、異議が認められ、頚椎捻挫について14級9号が認定されました。
⑶ 保険会社と裁判所基準で示談交渉
後遺障害等級の認定後は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などを計算して、加害者側保険会社と示談交渉を行いました。
Hさんの症状固定までの治療期間は約6ヶ月でしたので、裁判所基準で入通院慰謝料は約89万円、後遺障害慰謝料は14級の110万円を請求しました。
逸失利益については、Hさんが専業主婦でしたので、平均賃金(賃金センサス)を基礎収入として、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年間の計算で、約91万円を請求しました。
そして、交渉の結果、通院交通費や家事従事者の休業損害なども加え、総額で約420万円(治療費を除く)での示談となりました。
この示談金約420万円のうち、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計約200万円は、後遺障害等級が認定されていなければ受け取ることができなかったものになります。
また、入通院慰謝料や休業損害などの後遺障害以外の部分についても、当事務所へのご依頼前に保険会社が提示していた金額は約120万円でしたので、弁護士が裁判所基準で交渉したことによって100万円ほど増額できたことになります。
このように、Hさんの事例は、後遺障害等級の認定と慰謝料を裁判所基準で交渉することで、最終的な示談金を大きく増額させることができました。
6.まとめ
むち打ちは、一見軽微に見えても、後遺症が残ると日常生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。
そして、適切な慰謝料や逸失利益を受け取るためには、適切な後遺障害認定を受ける必要があります。
そのためには、医師に治療段階から症状を正確に伝え、医師との連携を密にし、適切な書類を準備することが不可欠です。
また、交通事故の被害に遭い、むち打ちによる後遺症で悩まれている方は、決して一人で抱え込まず、交通事故問題に強い弁護士に早めに相談することをお勧めします。
弁護士は、後遺障害認定のサポートから保険会社との交渉、そして万が一の訴訟まで、あなたの権利を守るために最善を尽します。
結果的に、損害賠償額についても、弁護士が間に入ることで適正な金額(裁判所基準)での解決が期待できます。
当事務所では、交通事故のご相談を無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【関連記事】
投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。