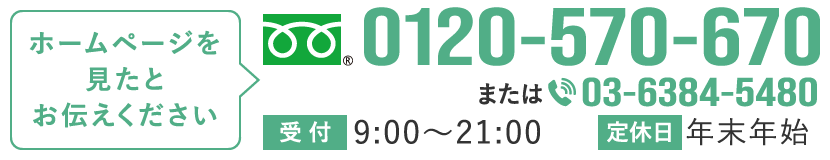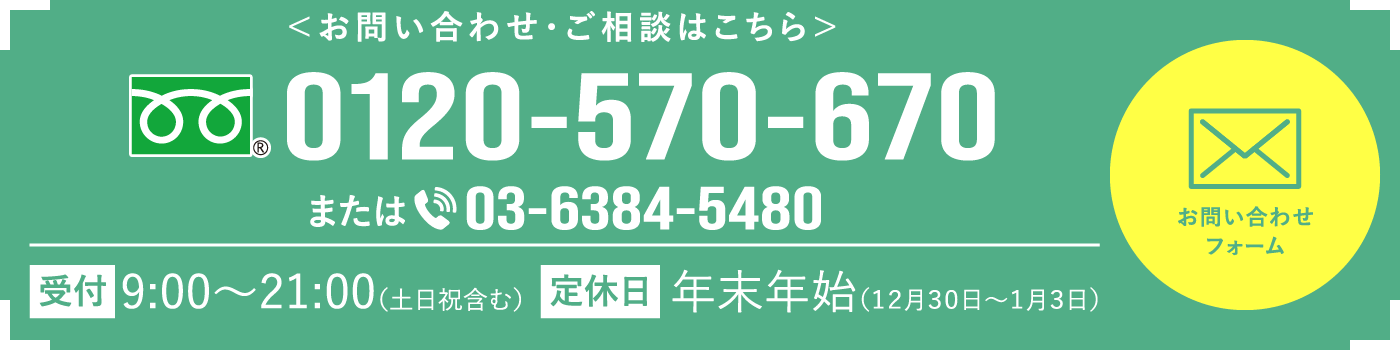今回は、「肩腱板損傷の示談交渉で気をつけたい慰謝料金額の落とし穴」について、ご紹介いたします。
交通事故で腱板損傷(肩腱板断裂など)を負った場合、日常生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。
治療を終え、いざ保険会社との示談交渉が始まると、「提示された慰謝料が適正な金額なのか?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
このケガは、慰謝料や示談金の金額が後遺障害等級の認定によって大きく変わるため、早い段階で正しい知識と対策が必要です。
この記事では、交通事故による肩腱板損傷の被害者が、示談交渉で損をしないために知っておくべき慰謝料のポイントを解説します。
後遺障害の認定基準から、保険会社の提示額の落とし穴、そして弁護士に相談するメリットまで、被害者の方の解決に必要な情報が満載です。
適切な慰謝料を受け取り、安心して治療後の生活を送るためにも、ぜひ最後までお読みください。
このページの目次
1.交通事故における肩腱板損傷の慰謝料と示談金の基礎知識
⑴ 腱板損傷とは何か
肩の関節は、「上腕骨」「肩甲骨」「鎖骨」という3つの骨で構成されていますが、覆っている骨の部分が少なく非常に不安定です。
この安定性を保つ上で、腱板が非常に重要な役割を担っています。
腱板は、「棘上筋」「棘下筋」「肩甲下筋」「小円筋」という4つの筋肉の腱で構成され、上肢の複雑な可動を可能にする重要なものです。
腱板損傷とは、これらの腱の一部、または全てが損傷したり、裂けたりする症状を指します。
交通事故の強い衝撃によって、肩が不自然にひねられたり、直接的な打撃を受けたりすることで、腱板に過度な負荷が生じ、損傷することがあります。
損傷の程度は、部分的なものから完全に断裂するものまで様々です。骨折や脱臼を伴うケースもあります。
⑵ 肩腱板損傷の主な症状と事故による受傷例
腱板損傷の主な症状は、次のとおりです。
①肩の痛み:特に腕を上げたり、特定の動きをしたりする際に痛みが強まります。夜間に痛みが悪化することも少なくありません。
②腕が上がらない:腕を上げる動作が制限されたり、まったくできなくなったりすることがあります。
③可動域の制限:肩の動き全体が制限され、日常生活に支障をきたすことがあります。
交通事故による受傷例としては、バイク事故や自転車事故で肩を地面に強打したケースなどが挙げられます。
事故直後から肩の痛み等の症状が出たという被害者の方も多いですが、事故直後には「むちうち」による首の痛みと混同されやすく、腱板損傷が認められないまま見過ごされてしまう可能性もあります。
見過ごされている期間が長ければ長いほど不利になってしまうので、事故後、少しでも肩に違和感がある場合は、速やかに整形外科を受診し、MRI検査など精密な検査を受けた方が良いでしょう。
⑶ 慰謝料の計算方法と示談金の相場
腱板損傷に直接関連する慰謝料として、以下の2種類が挙げられます。
①入通院慰謝料(傷害慰謝料):事故による怪我の治療のために病院に通院・入院したことに対する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
②後遺障害慰謝料:治療を継続しても完治せず、後遺障害が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。請求にあたっては、予め自賠責保険会社によって後遺障害等級の認定がなされていることが重要です。
腱板損傷の場合、治療期間や後遺障害の有無によって、これらの慰謝料が算定されることになります。また、慰謝料の計算には、以下の3つの基準があります。
①自賠責保険基準:自賠責保険会社が定める最低限の基準で、最も低い金額になります。
②任意保険会社基準:各任意保険会社が独自に定めている基準で、自賠責保険会社基準よりは高いものの、裁判所基準より低いことが殆どです。
③裁判所基準(弁護士基準): 過去の判例・裁判例に基づいており、最も適正な金額とされる基準です。弁護士に依頼した場合に適用されることが多く、示談の金額も高額になる傾向があります。
示談金は、これらの慰謝料に加えて、治療費、休業損害、後遺障害逸失利益などが含まれた総額となります。
腱板損傷の示談金の相場は、損傷の程度、治療期間、後遺障害等級、そしてどの慰謝料基準で計算するかによって大きく変動します。
⑷ 腱板損傷の後遺障害慰謝料相場早見表(等級別)
※この表は目安額です。実際の金額は症状・交渉内容で変動します。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
| 10級 | 187万円 | 550万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
2.後遺障害認定:肩腱板損傷で注意すべきポイント
腱板損傷の治療を続けても症状が改善せず、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害として認定される可能性があります。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった補償が受けられますが、その認定には注意すべきポイントがいくつかあります。
⑴ 後遺障害等級と可動域制限の関係
後遺障害は、その症状の重さによって1級から14級までの等級に分類されます。
腱板損傷の場合、肩関節の可動域制限が問題となることが多いです。
肩関節の可動域が、健常な方の可動域と比較してどの程度制限されているかによって等級が診断されます。
例えば、「肩関節の機能に著しい障害(可動域が健常の方の2分の1以下に制限される状態)」を残した場合は10級10号、「肩関節の機能に障害(可動域が健常の方の4分の3以下に制限される状態)」を残した場合は12級6号が認定される可能性があります。
後遺障害の等級認定には、医師の作成する後遺障害診断書が非常に重要です。
この診断書には、肩の痛みだけでなく、具体的な可動域の測定値などを正確に記載してもらう必要があります。
⑵ 後遺障害が非該当になるケースとその対策
腱板損傷による後遺障害について後遺障害等級の申請を行っても、残念ながら非該当となるケースはあります。非該当となる主な理由としては、以下のようなものが考えられます。
①症状の一貫性がない:事故直後から症状が出ていなかったり、治療を中断していたりする場合。
②医師の意見書が不十分:後遺障害の症状を裏付ける客観的な所見や詳細な記載がない場合。
③他覚的所見の不足:MRIなどの画像検査で腱板損傷が確認できない場合や、神経学的検査で異常が認められない場合。
④事故との因果関係が不明確:事故以外の要因(加齢など)による腱板損傷であると診断される場合。
後遺障害等級が認定される確率を上げるためには、以下の対策が重要です。
・事故後、すぐに医療機関を受診し、継続して治療を受ける。
・医師に症状を正確に伝え、記録に残してもらう。
・MRI検査など客観的な画像検査を必ず受ける。
・後遺障害診断書の内容を精査し、不足がないか確認する。
⑶ 後遺障害等級の判例・事例紹介
裁判では、腱板損傷の後遺障害等級について様々な判例が出されています。
例えば、可動域制限が器質的損傷によるとは認められないが痛みの症状は医学的に証明しうる神経症状(12級13号)だと判断した事例や、明確な器質的損傷が認められないが機能障害(12級6号)として判断した事例などがあります。
これらの事例は、個別の症状や治療経過、提出された証明などによって判断が異なります。
自分のケースがどの等級に相当するかを知るためには、交通事故に詳しい弁護士に相談し、過去の事例を踏まえたアドバイスを受けることが有効です。
3 示談交渉で損をしないための保険会社対応術
交通事故の被害に遭い、治療が終わると、加害者側の保険会社から示談金の提示があります。
しかしながら、この提示額は、必ずしも適正な金額であるとは限りません。
損をしないためには、保険会社との交渉術を身につけることが重要です。
⑴ 保険会社が提示する慰謝料の落とし穴
保険会社が最初に提示する慰謝料は、多くの場合、任意保険会社基準または自賠責保険会社基準に基づいて計算されており、裁判所基準(弁護士基準)よりも低く設定されています。
保険会社は営利企業であるため、できるだけ支払う金額を抑えようとします。
特に注意すべきなのは、治療期間が長引いてしまったり、後遺障害が残ったりした場合です。
保険会社は、治療の必要性や症状固定の時期について異議を唱えたり、後遺障害の認定を否定したりして、低い金額を提示することがあります。
⑵ 適切な対応・主張・立証の方法
保険会社との交渉を有利に進めるためには、以下の点に注意して適切な対応をとることが重要です。
①医療機関での適切な治療:事故直後から症状が改善するまで、担当医の指示に従い治療を継続し、中断しないようにしましょう。
②症状を伝える:問診の際、痛みや可動域の制限などを適切に伝えましょう。
③客観的な証明の収集:診断書、診療報酬明細書、画像データ(MRI、X線など)など、怪我の状況を裏付ける全ての書類を取り寄せ、保管しておきましょう。
④保険会社とのやり取りの記録:電話や書面でのやり取りは、日時、内容、担当者名を記録しておくか、書面で行うようにしましょう。
これらの情報が、示談交渉におけるあなたの主張を裏付ける重要な証明となります。
⑶ 増額交渉のためのポイントと流れ
保険会社からの提示額に納得できない場合は、増額交渉を行うことになります。
増額交渉の主なポイントは以下の通りです。
①裁判所基準(弁護士基準)の適用を主張する:保険会社の提示額が低い場合は、裁判所基準での計算を求めましょう。ただ、弁護士に依頼していないケースでは、保険会社が裁判所基準を認めることは少ないのが実情です。
②後遺障害の適正な評価:後遺障害が残っているにもかかわらず認定されなかった場合や、等級が低いと感じる場合は、異議申立てを検討しましょう。
③具体的な根拠の提示:増額を求める際には、ただ「もっとほしい」と主張するのではなく、治療の必要性、症状の重さ、日常生活への影響などを具体的に示し、必要があれば証拠を提示しましょう。
④専門家への相談:示談交渉は専門的な知識が必要となるため、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。
示談交渉は、通常、治療終了後または後遺障害認定後に行われます。
納得できない場合は安易に示談書にサインせず、専門家である弁護士のアドバイスを仰ぎましょう。
⑷ 示談交渉を有利に進める3つのチェックリスト
交通事故で腱板損傷を負い、慰謝料や示談金をできるだけ有利に獲得するためには、交渉の前段階での準備が何より重要です。
この3つを押さえるだけで、慰謝料増額の可能性が大幅に上がります。
1.治療継続
なぜ必要か:保険会社は「治療期間が短い=症状が軽い」と判断する傾向があります。途中で通院を中断すると、適切な期間継続した場合と比べて慰謝料額が大幅に下がる恐れがあり、後遺障害等級の認定も難しくなります。
そのため、痛みが軽くなっても自己判断で通院をやめず、医師が「症状固定」と判断するまで治療を継続しましょう。
2.診断書確認
なぜ必要か: 後遺障害等級の認定は、医師が作成する「後遺障害診断書」の内容に大きく左右されます。
しかし、医師は自賠責の認定要件までは熟知していないことも多く、重要な計測値や症状の記載が漏れるケースがあります。
診断書を受け取ったら、
・肩関節の可動域(健側との比較角度)が正確に記載されているか
・MRIやレントゲンの所見が反映されているか
を必ず確認し、必要なら追記依頼を行いましょう。
3.証拠保全
なぜ必要か:示談交渉では、口頭での主張よりも客観的な証拠の有無が金額に直結します。
腱板損傷の場合、以下の証拠をそろえておくと有利です。
- MRIやレントゲン画像データ
- 通院記録(診療明細書)
- 日常生活での不自由さを示すメモや写真(例:家事・仕事ができない様子)
- 保険会社とのやり取り記録(メール・書面・通話メモ)
これらは後遺障害等級の申請や増額交渉の際、強力な裏付け資料となります。
4 弁護士に依頼するメリットと選び方
相手方保険会社との示談交渉は、専門知識が必要な上、精神的な負担も大きいです。
そのため、交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼することは、多くのメリットをもたらします。
⑴ 法律事務所選びの基準
弁護士に依頼する最大のメリットは、裁判所基準(弁護士基準)での示談金獲得の可能性が高まることです。
また、保険会社との煩わしい交渉を全て任せることができるため、精神的な負担が軽減し、治療に専念できます。
弁護士を選ぶ際には、以下の基準を参考にしましょう。
①交通事故案件の実績:交通事故、特に人身傷害案件の取り扱い実績が豊富であるかを確認しましょう。腱板損傷のような専門的な知識が必要なケースでの経験があるかどうかも重要です。
②専門性と得意分野:交通事故に注力している法律事務所を選びましょう。
③費用体系:弁護士費用特約が利用できるか、着手金や報酬料が明確かを確認しましょう。無料相談を受け付けているかも重要なポイントです。
④担当弁護士との相性:実際に面談や電話などで話してみて、親身になって相談に乗ってくれるか、信頼できると感じるかを確認しましょう。
⑵ 無料相談・初回面談時のチェックポイント
多くの法律事務所では、交通事故の無料相談を実施しています。この機会を有効活用し、以下の点をチェックしましょう。
①質問への明確な回答:疑問に思っていることに対して、分かりやすく具体的な回答がもらえるか。
②見通しの解説:慰謝料の見込み額、後遺障害認定の可能性、今後の手続きの流れなどについて、具体的な見通しを解説してくれるか。
③費用に関する解説:弁護士費用について、分かりやすい説明がなされているか。追加費用が発生する可能性についても確認しましょう。
④契約を急がせないか:相談だけで終わり、考える時間を与えてくれるか。無理に契約を勧めないかどうかも重要です。
交通事故による腱板損傷は、その後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
適切な損害賠償を受けるためにも、早期に交通事故に強い弁護士に相談し、解決に向けた対応をとることを強くおすすめします。
⑶ 弁護士法人優誠法律事務所について
当事務所(弁護士法人優誠法律事務所)では、交通事故のご相談は無料です。
所属している全ての弁護士が、交通事故事件について豊富な経験を有しており、その経験や知識を生かし、治療中のフォローから、後遺障害の申請、相手方との示談交渉、ADRや裁判まで、各場面で適切なサポートを致します。
弊所は全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。
【関連記事】
投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。