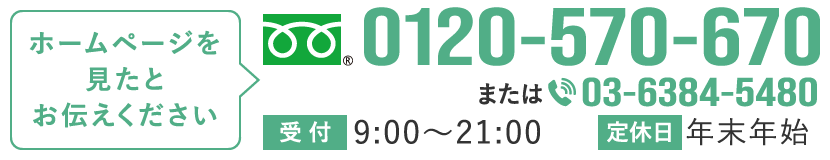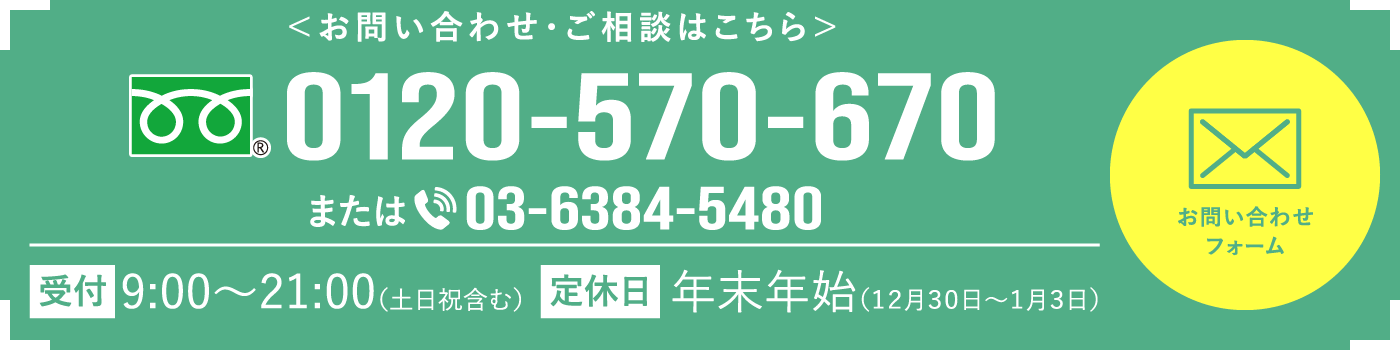交通事故に遭われた際、身体には大きな衝撃が加わり、事故直後には自覚症状がなくても、時間が経ってから様々な不調が現れることがあります。
中でも「むちうち」は、交通事故被害者に特に多く見られる症状です。
むち打ちは、交通事故の衝撃で首に負担がかかることで生じる神経症状のことで、「外傷性頚部症候群」や「頚椎捻挫」とも呼ばれます。
主な症状は、首やその周辺の筋肉、靭帯、神経などの損傷によって引き起こされます。
被害者自身が軽傷だと考えていても、少し時間が経過してから症状が現れるケースも少なくないため、早めの受診と継続的な通院が非常に重要です。
この記事では、むち打ちの主な症状とその影響、慰謝料の種類と計算方法、そして診断書の重要性とその記載内容について詳しく解説します。
【関連記事】
このページの目次
1.むち打ちの主な症状と影響
むち打ちとは、交通事故などの衝撃により首に負担がかかって生じる神経症状のことを指します。
むち打ちの症状は多岐にわたり、人によって現れ方が異なります。
最も典型的な症状は、首や肩の痛み、こり、違和感です。
これは、事故の衝撃で首が前後左右に激しく揺さぶられ、頚部の筋肉や靭帯が過度に伸展したり、損傷したりすることによって生じます。
寝違えのような軽い症状から、頭を動かすことが困難になるほどの強い痛みまで、その程度は様々です。
また、痛みやこりだけでなく、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気といった症状を伴うことも珍しくありません。
これらは、頚部の損傷が自律神経に影響を与えたり、脳への血流に影響を及ぼしたりすることによって引き起こされると考えられています。
さらに、腕や指のしびれ、脱力感が生じることもあります。
これは、頚部から腕へと伸びる神経が圧迫されたり、損傷を受けたりすることによるものです。
場合によっては、集中力の低下や不眠といった精神的な症状が現れることもあり、日常生活に大きな影響を及ぼします。
これらの症状は、事故直後には現れず、数時間後、あるいは数日経ってから徐々に現れるケースも少なくありません。
そのため、「事故に遭ったけれど、特に痛いところはないから大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは非常に危険です。
被害者自身は軽傷だと思っても、後に症状が悪化することもあり、通院の継続や専門医による診断が重要です。
症状が軽いうちに適切な治療を開始しないと、慢性化して後遺症として残ってしまう可能性もあります。
また、事故直後に通院を行わないことによって、後の示談交渉の際に、事故と症状の因果関係を争われることにもなりかねません。
むち打ちは、レントゲン検査では異常が認められにくいことも多く、その診断が難しいとされています。
骨折や脱臼のように骨そのものに異常がないため、レントゲン画像では異常が見つかりにくいのです。そのため、症状の訴えと医師の診察が診断の重要な要素となります。
交通事故によるむち打ちは、単なる身体的な不調にとどまらず、精神的な苦痛や経済的な負担も伴います。
仕事に支障が出たり、趣味の活動ができなくなったりすることで、精神的なストレスも大きくなるでしょう。
また、治療費や休業による収入減など、経済的な負担も無視できません。
このような状況において、適切な治療を受けることはもちろんのこと、慰謝料や損害賠償といった法的な側面についても理解しておくことが重要です。
特にむち打ちの場合、その症状の特性から、適正な慰謝料の算定が争点となることも少なくありません。
2.慰謝料の種類と計算方法の違い
⑴ 慰謝料の種類と算定基準
交通事故の慰謝料には、大きく分けて以下の3種類があります。
- 入通院慰謝料:治療のために入院・通院した期間・日数を元に計算
- 後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合に発生
- 死亡慰謝料:死亡事故に該当する場合
慰謝料の計算方法には”基準の違い”があります。
- 自賠責基準(国の最低限保障)
- 任意保険基準(各保険会社の独自基準)
- 弁護士(裁判)基準(過去の裁判結果に基づく)
適正な金額を得るには、弁護士基準での請求が最も有利とされています。
慰謝料の内訳として「入通院慰謝料(入院・通院日数ベース)」や「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があり、例えば【自賠責】では通院1日あたり4,300円(2023年4月以降の基準)、また弁護士基準では1ヶ月:約15〜20万円、3ヶ月:約53〜73万円、6ヶ月:約89〜116万円が目安です(すべて一例で、症状や日数、固定のタイミングにより増減)。
詳細な金額は表などで示されることも多く、被害者側の過失割合によって減額される場合があり、賠償金の計算には通院日数、症状固定日、後遺障害の有無など多くの要素が影響します。
また、保険ごとの対応の違いとして、
- 【自賠責保険】:最低限の補償として入院・通院慰謝料、交通費、休業損害など
- 【任意保険】:示談代行サービスや契約内容で補償範囲や金額に違いあり、自分に過失がある場合も一定額がもらえるケースあり
- 【人身傷害特約】:自分が加害者でも一定の保険金を請求できる
といった特徴があります。
⑵ 実際の事例における任意保険基準と弁護士基準の慰謝料の差~当事務所の依頼者の事例~
各基準による慰謝料金額の具体的な違いについて、当事務所で実際に取り扱った事案から以下のAさんの事例をご紹介いたします。
Aさんは、北海道札幌市在住で、タクシー乗車中に後方からの追突を受け、頚椎捻挫・腰椎捻挫のいわゆる「むち打ち」と言われる症状を発症しました。
その後、コルセット着用や病院でのブロック注射、リハビリ等を経たうえで、事故から約6か月半が経過した時点で症状固定となりました。
症状固定となって間もなく相手損保から示談金額の提示がありましたが、慰謝料金額については60万円程度の提案でした。
この相手損保の慰謝料の提案額が低いのではないかとお考えになったAさんは、当事務所にご相談され、当事務所の弁護士が相手損保に対する示談交渉を行うことになりました。
幸いAさんは、ご自身が所有されている自動車の保険に弁護士費用特約を付けていましたので、弁護士費用のご負担なくご依頼いただくことができました(今回のように、弁護士費用特約は、保険契約している車両での事故でなくても使えるケースが多いです。)
本件をお引き受けした後、当方から、相手損保に対して最初に弁護士(裁判)基準の満額である93万円程度を提示したところ、相手損保からはその8割の金額である74万円程度の再提案がありました。
なお、相手損保が弁護士に対しても弁護士基準の8割の金額を提案してくることはよくあります。
この時点で、既にご依頼前の約60万円から約74万円に増額できていましたが、担当弁護士は増額交渉を継続しました。
そうしたところ、休業損害等の慰謝料以外の争点もあったため多少時間を要しましたが、1か月程度の交渉にて、最終的に慰謝料については90万円程度を獲得することができました。
この事案では、ご依頼前の約60万円から約90万円まで増額できましたが、このように任意保険基準と弁護士基準では30万円以上も金額の違いがあったことになります。
⑶ 症状固定前の治療費打切りには要注意!
交通事故の治療を続けていると、相手損保が治療の打切りを打診してくることが多いですが、この任意保険による「症状固定前の打切り」には注意が必要で、保険会社の治療費打切りの時点で通院をやめてしまうと、治療費や慰謝料などの賠償範囲がその時点までとなってしまいます。
適切な賠償金を得るためには、たとえ保険会社から打切りの打診があっても、医師が治療の必要性を認めている間は病院を継続受診することが必要です。
また、医師が症状固定の診断をするまでの治療費を認めてもらえるよう延長の交渉をするなどの対応も必要です。
交通事故の被害に遭った場合、弁護士への早期相談が勧められていますが、弁護士に相談すると、治療終了後の慰謝料や賠償金の増額交渉だけでなく、治療費の延長交渉や必要な診断書の取得の代行など多くのメリットがあります。
「弁護士費用特約」で弁護士費用が実質無料となる場合もありますし、着手金無料や成功報酬型の法律事務所も増えていますので、気軽に弁護士の活用を検討してみてください。
3.診断書の重要性と書き方
交通事故に遭い、むち打ちの症状が現れた場合、最も重要となるのが「診断書」です。
診断書は、ご自身の症状が交通事故によって引き起こされたことを医学的に証明する、場合によっては唯一の書類であり、加害者側や保険会社に対して損害賠償請求を行う上で不可欠な証拠となります。
⑴ 診断書の重要性
診断書の重要性は、以下の点に集約されます。
- 因果関係の証明:診断書は、交通事故とご自身の症状との間に医学的な因果関係があることを証明します。これがなければ、「事故とは関係のない症状ではないか」と加害者側や保険会社に主張され、適切な補償を受けられない可能性があります。
- 治療の必要性の証明:診断書には、医師が診断した傷病名や症状、それに対する治療方針が記載されます。これにより、行われる治療が交通事故による症状に対するものであることが明確になり、治療費の請求根拠となります。
- 後遺障害認定の基礎:むち打ちの症状が長期化し、後遺症として残ってしまった場合、後遺障害の等級認定を申請することになります。その際、診断書の内容は後遺障害の有無や等級を判断する上で極めて重要な資料となります。症状の推移や治療経過が詳細に記載されていることが、適切な等級認定につながります。
- 慰謝料算定の根拠:交通事故における慰謝料は、入通院期間や症状の程度によって算定されます。診断書に記載された傷病名、症状、治療期間などが、慰謝料の金額を決定する上で重要な要素となります。
⑵ 診断書に記載されるべき主要な項目
- 傷病名:「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」など、医師が診断した具体的な病名が記載されます。
- 初診日:交通事故後、初めて医療機関を受診した日が記載されます。事故発生から初診までの期間が短いほど、事故との因果関係が認められやすくなります。
- 負傷の原因:「交通事故による」と明確に記載されていることが重要です。
- 主要な症状:患者が訴える症状(首の痛み、頭痛、しびれなど)が具体的に記載されます。医師が客観的に確認できる所見(可動域制限、圧痛など)も記載されます。
- 治療内容と期間:どのような治療が行われているか(投薬、リハビリ、物理療法など)や、今後の治療方針、治療期間の見込みなどが記載されます。
- 全治の見込み:症状が完全に回復するまでの見込みが記載されます。症状が残存する可能性がある場合は、その旨も記載されます。
⑶ 医師への症状の伝え方と注意点
診断書の内容は、患者自身の訴えに基づいて医師が作成します。
特に、むち打ちの場合には、自覚症状が主となり、他覚的に確認できる可動域制限等の所見がないことも珍しくありません。
そのため、医師に正確かつ具体的に症状を伝えることが非常に重要です。
- 発生時の状況を正確に伝える:交通事故がどのように発生し、ご自身の身体にどのような衝撃があったのかを具体的に伝えます。例えば、「追突されて首がガクンとなった」「横からぶつかられて身体が横に振られた」など、状況を詳細に説明しましょう。
- すべての症状を具体的に伝える:痛みだけでなく、しびれ、めまい、吐き気、耳鳴り、不眠、集中力の低下など、自覚するすべての症状を具体的に伝えます。痛みの程度(ズキズキする、重い、ピリピリするなど)、頻度、症状が現れる時間帯なども詳しく伝えましょう。
- 症状の変化を記録する:毎日、ご自身の症状の変化を記録することをお勧めします。痛みの強さ、症状が出た時間、改善したこと、悪化したことなどを記録し、診察時に医師に提示することで、医師はより正確な診断を下しやすくなります。
- 遠慮せずに伝える:医師に遠慮して症状を軽めに伝えたり、伝え忘れてしまうことがないようにしましょう。ご自身の身体のことですから、気になる症状はすべて正直に伝えてください。
- 既往歴や持病も伝える:以前からの持病や既往歴がある場合は、それがむち打ちの症状に影響を与える可能性もあるため、医師に伝えておきましょう。
- 複数の医療機関を受診しない:原則として、診断書は一つの医療機関で作成されるべきです。複数の医療機関を受診すると、診断書の内容に矛盾が生じたり、治療の一貫性が失われたりして、保険会社から不当な評価を受ける可能性があります。ただし、専門医のセカンドオピニオンが必要な場合は、主治医と相談の上で検討しましょう。
⑷ 診断書が作成された後の確認
診断書が作成されたら、必ず内容を確認しましょう。
ご自身が訴えた症状がすべて記載されているか、病名や初診日、負傷の原因が正確に記載されているかなどを確認します。
もし、誤りや不足している点があれば、すぐに医師に申し出て訂正してもらいましょう。
交通事故の被害に遭われた方が、適切な慰謝料や補償や後遺障害等級の認定を受けるためには、正確で具体的な診断書が不可欠です。
4.弁護士に依頼するメリット
交通事故に関する手続きは、上でご説明した診断書の内容だけでなく、その後の示談交渉や後遺障害の申請など、非常に複雑で専門的な知識が求められます。
そして、多くの場合、加害者側の保険会社はできるだけ支払う慰謝料や賠償額を抑えようとします。
提示された金額が相場と比較して適切かどうか、ご自身で判断することは非常に困難です。
特にむち打ちの場合、自覚症状が中心となるため、その程度や慰謝料の相場を巡って争いになることも少なくありません。
そのような時に頼りになるのが、弁護士です。弁護士は、法律の専門家として、被害者の方の権利を守り、適正な慰謝料や賠償額を獲得できるようサポートします。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 示談交渉の代行:保険会社との煩雑な交渉を弁護士が全て代行します。これにより、精神的な負担が軽減され、治療に専念することができます。
- 適切な慰謝料の算定:裁判例に基づく適切な慰謝料の相場を把握しているため、保険会社が提示する金額が不当に低い場合には、増額交渉を行います。弁護士基準といわれる高い基準で慰謝料を請求できます。
- 後遺障害認定のサポート:後遺障害の等級認定は、非常に専門的な知識が必要です。弁護士は、適切な資料収集や申請手続きをサポートし、適正な等級認定が受けられるよう尽力します。
- 訴訟対応:交渉が決裂した場合でも、民事訴訟を提起して適切な賠償を得られるよう尽力します。
- 法律相談:疑問や不安な点をいつでも弁護士に相談できるため、安心して手続きを進めることができます。
5.まとめ
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、これまで数多くのむち打ち事案を解決して参りました。
被害者の方々が抱える痛みや不安に寄り添い、適正な解決へと導きます。
もし、交通事故に遭われてむち打ちの症状でお悩みの場合、また、保険会社との交渉でお困りの場合は、一度、当法律事務所にご相談ください。
初回の相談は無料で行っております。
早期にご相談いただくことで、より有利な解決に繋がる可能性が高まります。
ご自身の権利を守り、事故の被害から一日も早く回復するためにも、弁護士のサポートをぜひご検討いただければと思います。
投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。
突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。