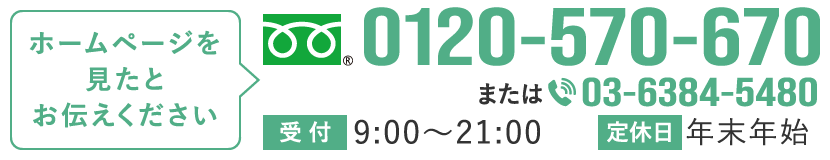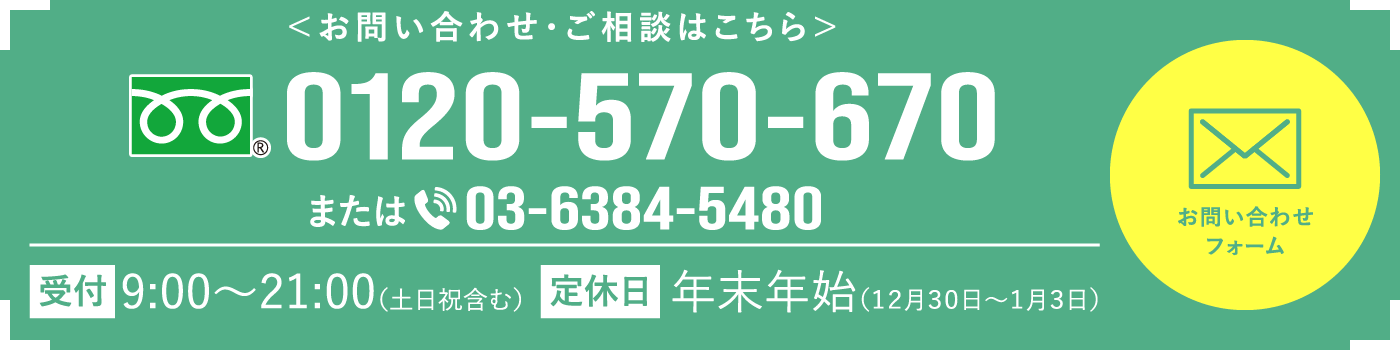Archive for the ‘後遺障害’ Category
バイク事故で脊髄損傷|慰謝料・逸失利益が数百万円変わる分岐点とは
今回のテーマは、バイク事故による「脊髄損傷」です。
交通事故の中でも、身体が剥き出しの状態であるバイク事故は、重篤な怪我につながるケースが少なくありません。
中でも脊髄損傷は、手足の麻痺や感覚障害など、被害者の将来にわたって深刻な影響を残す重大な傷害です。
脊髄損傷の被害者が適切な補償を獲得するためには、後遺障害の等級認定が極めて重要です。
認定される等級が1つ違うだけで、慰謝料や逸失利益が数百万円、あるいは数千万円単位で変わることもあります。
本記事では、交通事故・バイク事故を多く取り扱ってきた弁護士の視点から、脊髄損傷の基礎知識、賠償額が決まる仕組み、そして解決へのポイントを解説します。
【関連記事】
1.交通事故による脊髄損傷とは?症状・後遺症・被害者に生じる障害を解説
まずは、医学的な観点から脊髄損傷がどのような状態を指すのか、その症状と診断の基礎知識を確認しましょう。
・脊髄損傷が起きる仕組みと主な原因(交通事故事例を中心に解説)
脊髄とは、脳から背骨(脊椎)の中を通って伸びる太い神経の束のことです。
バイク事故では、転倒時の強い衝撃などにより、背骨の骨折や脱臼が生じ、その中の脊髄が圧迫されたり傷ついたりすることで損傷が起きます。
特にバイクは、ヘルメットで頭部は守られていても、首(頚椎)や腰(腰椎)は衝撃を受けやすい部位です。
事例としても、交差点での出会い頭の衝突や、ガードレールへの激突などで、頚髄(首の神経)を損傷するケースが多く見られます。
2.脊髄損傷の症状・種類・部位別の違い|頚髄損傷が重くなりやすい理由
交通事故による脊髄損傷では、損傷した部位や損傷の程度に応じて、様々な症状が現れます。
代表的なのは、麻痺・感覚障害・運動制限であり、これらの症状がどの程度残るかによって、後遺障害等級や慰謝料額が大きく左右されます。
脊髄損傷では、脳からの指令が神経を通じて伝わらなくなることで、手足が動かしにくくなる「麻痺」や、痛み・温度を感じにくくなる「感覚障害」が生じることがあります。
また、歩行や階段昇降が困難になるなど、日常生活や労務に支障をきたす「運動制限」が残るケースも少なくありません。
これらの症状は、損傷の程度だけでなく、どの部位の脊髄が損傷したかによっても大きく異なります。
特に頚髄(首の脊髄)を損傷した場合には、上肢・下肢の双方に障害が及びやすく、重症の場合には介護が必要となる後遺症が残ることもあります。
一方、胸髄や腰髄の損傷では、主に下半身に麻痺や感覚障害が現れ、歩行困難や日常生活動作の制限が問題となるケースが多く見られます。
さらに、脊髄損傷が「完全損傷」か「不完全損傷」かによっても、症状の重さや生活への影響は大きく異なります。
完全損傷では神経機能がほぼ失われるのに対し、不完全損傷では一部の運動機能や感覚が残ることがあります。
この違いは、後遺障害等級や賠償額にも大きく影響します。
次に、こうした症状や損傷の違いが、後遺障害等級としてどのように評価されるのかを解説します。
3.交通事故による脊髄損傷|後遺障害等級(1級〜12級)の一覧と認定ポイント
脊髄損傷による損害賠償において、最も重要なのが「後遺障害等級」です。
この等級によって、保険会社から支払われる金額の基準が決まります。
⑴ 後遺障害等級(1級~12級など)の違いと認定基準・理由
脊髄損傷の後遺障害は、麻痺の範囲や生活への支障の程度に応じて、主に以下の等級に分類されます。
| 等級 | 状態の目安 |
| 第1級 | 常に介護が必要な状態。 |
| 第2級 | 随時介護が必要な状態。 |
| 第3級 | 終身労務に服することができない状態。 |
| 第5級 | 特に軽易な労務以外の労務に服することができない状態。 |
| 第7級 | 軽易な労務以外の労務に服することができない状態。 |
| 第9級 | 服することができる労務が相当な程度に制限される状態。 |
| 第12級 | 局部に頑固な神経症状を残す状態。 |
重い等級であれば、将来の介護費用も認定されやすくなるため、賠償額が非常に高額になります。
⑵ 等級認定に必要な資料・画像・診断書と申請手順
後遺障害認定の流れとしては、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責保険(損害保険料率算出機構)へ申請を行います。
この際、単に診断書を提出するだけでなく、MRI画像や、日常生活に関する状況報告書(日常の困難さを伝える書類)などをセットで提出することが、適正な等級を受けるために有効です。
⑶ 等級非該当・低い等級と異議申立て|成功・解決のコツ
例えば、弁護士に依頼しないで自賠責保険に申請した際,非該当にされたり、想定よりも低い等級が認定されたりしてしまったとします。
この場合、手続上は「異議申立て」を行うことが可能です。
ただ、同じ資料で再審査しても、結果が変わる可能性は低いといえます。
そこで、有効な異議申立てを行うためには、新たな医学的証拠を用意したり、医師や弁護士による意見書を添えるなどの必要があります。
一般論としては、異議申立てで後遺障害等級が変更される確率は低いですが、新たな医学的証拠などを添付して再審査を求めることで、認定結果が覆るケースもあります。
4.脊髄損傷の後遺障害認定に必要な診断書・検査内容と医師の所見
交通事故による脊髄損傷で後遺障害認定を受けられるかどうかは、医師が作成する診断書と検査結果の内容によって左右されます。
実際、症状が残っていても、診断書の記載や検査結果が不十分な場合、後遺障害非該当や、想定より低い等級にとどまってしまうケースも少なくありません。
特に重要なのが、MRIや神経学的検査による客観的な所見です。
これらの検査結果がなければ、症状があっても医学的に裏付けられず、後遺障害として認定されないことがあります。
また、診断書に記載される医師の所見次第で、後遺障害等級が大きく変わる点にも注意が必要です。
5.自賠責保険と保険会社の対応|脊髄損傷はどこまで認められるか
交通事故による脊髄損傷で補償を受ける際、自賠責保険と任意保険会社がどこまで損害を認めるのかは、被害者にとって非常に重要なポイントです。
実務上は、
「症状があるのに認められない」
「後遺障害等級が想定より低い」
といったトラブルが多く発生します。
ここでは、自賠責保険の役割と保険会社の対応の実態、そしてなぜ認められないケースがあるのかを解説します。
(1) 自賠責保険とは|脊髄損傷で請求できる補償の範囲
自賠責保険は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている保険で、交通事故被害者に対する 最低限の補償 を目的としています。
脊髄損傷の場合、自賠責保険では主に次の補償が対象となります。
- 治療費・入通院慰謝料・休業損害などの傷害部分の損害
- 後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
ただし、自賠責保険には 後遺障害等級ごとに支払限度額 が定められており、脊髄損傷のような重い後遺症では、補償額が実際の損害に比べて不足するケースが多いのが実情です。
(2) 脊髄損傷は自賠責保険でどこまで認められるのか
自賠責保険では、脊髄損傷が客観的資料によって裏付けられているかどうかが支払いの前提となります。
認定されるためには、
- 事故と症状との因果関係が明確であること
- 症状が将来にわたって残存していること
- MRIなどの検査結果や医師の所見がそろっていること
が必要です。
一方で、
- 「画像上、明確な損傷が確認できない」
- 「症状が医学的に説明できないと判断された」
といった理由で、脊髄損傷と診断されていても非該当と判断されるケースもあります。
(3) 保険会社(任意保険)の対応と注意すべきポイント
任意保険会社は、自賠責保険で認定された等級を前提に、独自の基準で賠償額を算定・提示してきます。
実務上、保険会社の対応として問題になることが多いのが、
- 労働能力喪失率や喪失期間を限定した逸失利益の提示
- 「症状が軽い」「日常生活に支障が少ない」との主張
- 治療費の早期打ち切り要請
といったケースです。
保険会社は、支払額を抑える立場にあるため、被害者に有利な判断を自発的に行うことはほとんどありません。
(4) 脊髄損傷が認められないケースと正当な補償を受けるためのポイント
脊髄損傷で補償が十分に認められない背景には、いくつか共通する理由があります。
例えば、
・診断書の記載内容が抽象的で、症状の程度が具体的に示されていない
・MRIや神経学的検査による客観的所見が不足している
・事故と症状との因果関係が弱いと判断されてしまう
・日常生活や労務への影響が十分に伝わっていない
といった点が重なると、実際には重い症状が残っていても、後遺障害非該当や、低い等級にとどまってしまうケースがあります。
そのため、正当な補償を請求するためには、必要な検査を適切な時期に受け、症状や生活上の支障が診断書に正確に反映されているかを確認することが重要です。
また、保険会社からの提示をそのまま受け入れず、内容が妥当かどうかを慎重に判断する姿勢も欠かせません。
(5) 弁護士に相談することでできること
交通事故・脊髄損傷に詳しい弁護士に相談することで、
- 自賠責保険への適切な後遺障害申請
- 保険会社との交渉・示談対応
- 認定結果に納得できない場合の異議申立て
- 裁判基準を前提とした賠償請求
といったサポートを受けることができます。
保険会社の提示額が適正かどうかを判断するためにも、一度専門家に相談することを強くおすすめします。
6.交通事故による脊髄損傷の慰謝料・逸失利益|請求額が変わる分岐点
なぜ後遺障害等級によって「数百万円変わる」と言われるのか。
その理由は、後遺障害慰謝料の基準と、後遺障害逸失利益の計算方法にあります。
⑴ 脊髄損傷で認定される後遺障害慰謝料・損害賠償金の相場と算定基準
交通事故の慰謝料には、大きく分けて3つの基準があります。
・自賠責基準:最低限の補償。
・任意保険基準:保険会社が独自に定める基準。
・弁護士基準(裁判基準):裁判所が採用している基準(最も高額)。
例えば、後遺障害の等級が12級である場合、自賠責基準では慰謝料が94万円ですが、弁護士基準では290万円と、基準が違うだけで金額が跳ね上がります。
脊髄損傷のような重い障害では、その差はさらに広がります。
⑵ 後遺障害逸失利益の計算の考え方|等級・年収・年齢ごとの増減額例
逸失利益とは、「事故がなければ将来得られたはずの収入」のことです。
計算式は以下の通りです。
逸失利益 = 基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(原則67歳まで)に対応する係数
ここで重要なのが「労働能力喪失率」です。
次のとおり、このパーセンテージは等級によって大きく異なります。
・第1級~3級:100%喪失(全く働けない)
・第9級:35%喪失
・第12級:14%喪失
例えば、36歳で年収500万円の方で、労働能力喪失期間に対応する係数を便宜上20とした場合,次のとおり,等級によって後遺障害逸失利益の金額には大きな差が生じます。
・第1級~3級:500万円×100%×20=1億円
・第9級:500万円×35%×20=3500万円
・第12級:500万円×14%×20=1400万円
⑶ 等級の分岐点:賠償が数百万円変わる認定・症状の境界線
争点になりやすいのが、9級(労務が相当制限される)と12級(頑固な症状)の境界線です。
画像上の明確な損傷所見の有無や、神経学的検査の結果が分岐点となります。
また,介護が必要か否か(1・2級かそれ以外か)の境界線は、(非常に高額となる)将来の介護費用が認定されやすくなるか否かに関わるため、極めて重要です。
7.交通事故の脊髄損傷は弁護士に相談すべき理由|法律事務所選びのポイント
脊髄損傷の事案は専門性が高く、保険会社との交渉を被害者自身で行うのは非常に困難です。
⑴ 弁護士に依頼するタイミングと費用|無料相談・事務所選び
依頼のタイミングは、事故直後または治療中の早い段階がベストです。
適切な検査を受けるアドバイスができるからです。
多くの法律事務所や弁護士法人では、交通事故の無料相談を実施しています。
費用についても「弁護士費用特約」を利用すれば実質0円になる場合が多く、特約がない場合でも、着手金無料で賠償金獲得後の後払い(成功報酬)とする事務所が増えています。
⑵ 交通事故・バイク事故対応で弁護士が行う交渉や裁判サポート事例
弁護士は、被害者の代理人として以下のサポートを行います。
・医師に対して診断書の作成を依頼する際のアドバイス等
・保険会社からの治療費打ち切りへの対応
・適正な後遺障害等級の申請手続き
・弁護士基準を用いた賠償金の増額交渉
⑶ 弁護士による高額解決事例
実際、弁護士が介入することにより、高額で解決できた事例は珍しくありません。
弊所においても、弊所弁護士が解決した「交通事故により脊髄損傷を負ってしまった方の高額解決事例」を紹介していますので、ご参照ください。
8.脊髄損傷後の生活|介護・歩行困難・将来に必要な補償と支援
賠償金の問題だけでなく、被害者とその家族は、これからの生活にどう向き合うかという課題も抱えます。
⑴ リハビリテーション・治療法と回復の可能性
脊髄の神経は一度損傷すると完全な修復は難しいとされていますが、近年の再生医療の研究や、専門的なリハビリによって、機能の改善が期待できるとされています。
残された機能を最大限に活かすためのリハビリは非常に重要です。
具体的な治療方針やリハビリ計画については、必ず主治医の先生とよく相談してください。
⑵ 介護・車椅子・生活補償|被害者と家族の悩みへの対応策
車椅子生活になる場合、自宅のバリアフリー化や、介護用ベッドの購入などが必要になります。
これらの費用も、必要性・相当性が認められれば損害賠償として請求可能です。
また、家族の悩みを軽減するためにも、利用できる公的支援や補償内容も把握しておくことが大切です。
⑶ 病院・専門医の選び方と将来の生活設計
脊髄損傷の治療・リハビリに特化した病院や専門医を選ぶことは、その後の回復に影響します。
また、獲得した賠償金を将来の生活費や治療費としてどう管理していくかも含めた生活設計が求められます。
9.まとめ|バイク事故の脊髄損傷被害にどう向き合うか
バイク事故による脊髄損傷は、被害者の方の人生を一変させる重大な出来事です。
身体的な苦痛に加え、将来への不安は計り知れません。
しかし、適切な等級認定を受け、正当な賠償(慰謝料・逸失利益・介護費用など)を獲得することで、今後の生活の基盤を整えることは可能です。
保険会社の提示額を鵜呑みにせず、弁護士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。
優誠法律事務所では、脊髄損傷を含めた交通事故被害の相談を随時受け付けております。
無料相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
交通事故で脊髄損傷を負った方へ|後遺障害等級の認定基準と慰謝料相場を弁護士が解説
今回は、「脊髄損傷」に関する後遺障害等級について、解説いたします。
脊髄損傷は、交通事故や転落事故などによって引き起こされる重篤な損傷であり、その後の生活に重大な影響を及ぼします。
適切な後遺障害等級が認定されることは、正当な賠償を受ける上で非常に重要です。
しかし、「どのような基準で後遺障害等級が認定されるのか」「後遺障害等級認定の申請をするためには、どのような書類が必要なのか」など、脊髄損傷に関する後遺障害等級は難しいと感じる方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
交通事故により脊髄損傷を負った被害者の方は、手足の麻痺や感覚麻痺など、日常生活に大きな制限が残る「後遺症」を抱える可能性があります。
こうした後遺症が残った場合には、自賠責保険や相手方保険会社に対して「後遺障害等級」の認定請求を行うことが極めて重要です。
適切な等級が認められれば、後遺障害慰謝料や将来にわたる介護費・生活補償など、相当額の賠償金を受けられる可能性があります。
しかし、認定される等級によって金額は大きく変わるため、認定の段階での対応が非常に重要となります。
この記事では、脊髄損傷に関する後遺障害等級の認定基準と、申請に必要な書類について詳しく解説します。
特に、画像所見の重要性についても掘り下げて解説しますので、現在、脊髄損傷による後遺障害でお困りの方、またはその可能性のある方は、ぜひご一読いただき、適切な補償を獲得するための一助としていただけますと幸いです。
【関連記事】
1.脊髄損傷とはどんな状態?後遺障害の基礎知識を深掘り
⑴ 脊髄損傷のメカニズムと症状の多様性
そもそも脊髄とは何かについて、ご説明いたします。
脊髄とは、脳から連なる中枢神経系の一部をいいます。
脊髄は神経であり、直径わずか1cmほどの細い組織の中に、運動神経や知覚神経の繊維が詰まっています。
脊柱管によって守られてはいますが、わずかな病変が生じても四肢麻痺などの症状が出現し得るため、脊髄は非常に繊細なものです。
そして、脊髄損傷とは、交通事故などによる外力が脊髄に加わって、脊髄が損傷された状態のことをいいます。
脊髄損傷は、脊椎(いわゆる背骨)の脱臼や骨折を伴って生じることが多いです。
このうち、脊髄全横断面にわたって神経回路が断絶したものを完全損傷、一部でも保たれたものを不完全損傷といいます。
脊髄損傷の症状は、「完全損傷」と「不完全損傷」で大きく変わります。
完全損傷の場合、脳からの命令が断たれるため、四肢・体幹の運動機能が失われるだけでなく、感覚機能も失われ、体温調節機能や代謝機能も困難になってしまいます。
一方、不完全損傷の場合、神経が完全には断裂していないため、症状の有無や程度には広範囲の差異があるとされています。
脊髄損傷によって生じる症状は、損傷した脊髄の「部位」によって大きく異なります。
・頚髄(首の脊髄)を損傷した場合:手足(上肢・下肢)の麻痺、呼吸機能低下など
・胸髄を損傷した場合:体幹の保持が困難になり、歩行障害や姿勢保持が困難になる場合がある
・腰髄を損傷した場合:下肢の運動障害や感覚障害が生じやすく、歩行に支障が出ることが多い
このように、損傷部位と神経の走行が深く関係しているため、症状の「程度」や「残る後遺症」は個人によって大きく異なります。
⑵ 後遺障害等級とは何か
後遺障害等級は、自賠責保険会社や裁判所等において認定がなされます。
等級が認定されることは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった適正な賠償の支払いに向けた大きな前進です。
一方、等級が認定されない場合、後遺障害が残っていても基本的には賠償対象にならないことから、等級認定の重要性は極めて高いです。
2.脊髄損傷の後遺障害は「等級」がカギ! 具体的な認定基準と分類
このように、脊髄損傷に関する後遺障害の等級認定は、その後の賠償額を大きく左右します。
ここでは、どのような基準で等級が判断されるのかを具体的に見ていきましょう。
⑴ 「神経系統の機能または精神の障害」としての評価
脊髄損傷の後遺障害は、主に「神経系統の機能または精神の障害」として評価されます。
その等級ですが、症状の程度や日常生活への影響、介護の必要性などによって細かく分類されています。
具体的には、別表第1と別表第2に分かれており、重度な麻痺を伴う場合、別表第1の等級(第1級、第2級)が認定される可能性があります。
これは、常時介護や随時介護が必要な状態を指し、非常に重いものとされています。
後遺障害の等級認定がされるのか、されるとしても等級は何かを判断する要素としては、麻痺の程度(徒手筋力テストの数値など)、麻痺の範囲(四肢、対麻痺)、感覚障害の範囲・程度、排泄機能の障害の有無・程度などが挙げられます。
⑵ 脊髄損傷で認定される等級の目安
【常時介護が必要な状態:別表第1の第1級1号】
広範囲な麻痺により、日常生活のほぼ全ての動作(食事、入浴、排泄、着替えなど)に常時介護が必要となる状態です。
【随時介護が必要な状態:別表第1の第2級1号】
運動能力や感覚機能が著しく低下し、歩行が困難で、日常生活の重要な動作に随時介護が必要となる状態です。
【労働能力に支障が生じた状態:別表第2の第3級~第9級】
脊髄損傷により、手足の麻痺や体幹機能の障害が残ることで、仕事に大きな制限がかかったり、今後仕事に就くことが困難になったりする状態です。
具体的な等級は、麻痺の程度や、どの程度の労働能力が失われたか等によって判断されます。
【局部に頑固な神経症状を残している状態:別表第2の第12級13号】
例えば、筋緊張の亢進が認められるもの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの等が挙げられます。
・後遺障害等級認定までの流れ
① 医師による診断書作成と画像検査(MRI・CT)
② 症状と画像所見に整合性があるかの確認
③ 自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請
④ 認定された等級に応じ、慰謝料・逸失利益・将来介護費などの損害賠償を請求
この「流れ」を正しく踏むことで、適正な賠償の獲得に繋がります。
3.等級認定の成否を分ける「画像」の全貌
脊髄損傷に関する後遺障害の等級認定においては、医師の診断書や各種証明書のほか、特に重要なのがMRIやCTなどの「画像」所見です。
これらが認定の成否を分けると言っても過言ではありません。
その理由ですが、脊髄損傷は、外からは分からない神経の損傷であるものの、MRIやCTといった画像検査によって、この損傷を客観的かつ視覚的に捉えることができるためです。
画像は、骨折や脱臼の有無だけでなく、脊髄そのものの損傷部位、損傷の程度、脊髄がどの程度圧迫されているかといった重要な情報を提供します。
そのため、等級認定の審査にあたっては、MRIやCTなどの「画像」所見と、症状の内容や程度等との間に整合性はあるか否かが重要になります。
ここで、「画像」所見が重要であることを示す裁判例(京都地裁平成16年6月16日判決)をご紹介いたします。
この裁判例は、「画像」所見について次のとおり判示するとともに、結論として原告の頚髄(脊髄の一部)損傷を否定しました。
「頸髄損傷は、頸髄に対する器質的な損傷があり、頸髄実質内に出血や浮腫を伴い、事故直後から重度の麻痺を呈する傷害であって、その診断はMRI検査で頸髄に輝度変化があること、事故直後から四肢麻痺などの神経症状のあることが重要であり、さらに電気生理学的検査を総合して判断することになる(弁論の全趣旨、当裁判所に顕著な頸髄損傷の病態)が、(ア)原告には、受傷直後に四肢麻痺が発生したかについては、前記のとおり、事故の翌日に左上肢痛、挙上不可及び指尖の知覚異常を訴えたが、他の部位の知覚はあったのであり、上記麻痺があったとは窺えず、(イ)病的反射はみられず、エックス線写真、CT、MRI検査上頸髄損傷を疑わせる異常所見もみられず、(ウ)その他、頸椎第4・第5間、第5・第6間に突出部があったとしても、これが片麻痺の原因とはなり難く、麻痺、知覚異常を訴える部位は上記変性部の神経支配域とも一致しないことからすれば、原告が本件事故により頸髄損傷を受傷したと認めることはできず、この点の原告の主張は採用できない。」
保険会社は、被害者にとって「最も有利な等級」が認定されるように動いてくれるわけではありません。
むしろ、後遺障害が「軽い」と判断されることで、支払う慰謝料や逸失利益が低額で済むため、保険会社側としては被害者にとって不利な等級が認定される方が都合が良いともいえます。
そのため、後遺障害の等級認定は「保険会社任せにしないこと」が非常に重要です。
特に脊髄損傷は、画像所見の読み取りや診断書の記載内容、神経症状の証明など、医学的・法的な観点での整理が必要となるため、適切なサポートを受けずに申請すると本来認められるべき等級よりも低く評価されてしまうケースがあります。
当事務所では、脊髄損傷に関する後遺障害認定について
・診断書の記載内容の確認
・MRI/CTなどの画像所見の分析
・必要資料の収集
・自賠責保険への申請手続き
までを一貫してサポートいたします。
無料相談も随時承っておりますので、おひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
4.まとめ:脊髄損傷による後遺障害は、お一人で悩まず専門家にご相談ください
脊髄損傷に関する後遺障害の等級認定は、賠償額を大きく左右する極めて重要なものです。
このとき、MRIやCTなどの画像所見は、あなたの症状を客観的に証明する強力な証拠となります。
しかし、その内容を適切に評価し、等級認定に繋げるための主張立証は、一般の方には難しいものと思われます。
優誠法律事務所では、脊髄損傷による後遺障害でお困りの方をサポートいたします。
無料相談も可能ですので、まずは一度ご相談ください。
専門知識を持つ弁護士が、これまでの解決事例も踏まえて親身に寄り添い、解決へと導きます。
弁護士費用についても、ご依頼いただく際に明確にご説明いたしますのでご安心ください。
【関連記事】
投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
交通事故におけるむち打ちとその症状
交通事故に遭われた際、身体には大きな衝撃が加わり、事故直後には自覚症状がなくても、時間が経ってから様々な不調が現れることがあります。
中でも「むちうち」は、交通事故被害者に特に多く見られる症状です。
むち打ちは、交通事故の衝撃で首に負担がかかることで生じる神経症状のことで、「外傷性頚部症候群」や「頚椎捻挫」とも呼ばれます。
主な症状は、首やその周辺の筋肉、靭帯、神経などの損傷によって引き起こされます。
被害者自身が軽傷だと考えていても、少し時間が経過してから症状が現れるケースも少なくないため、早めの受診と継続的な通院が非常に重要です。
この記事では、むち打ちの主な症状とその影響、慰謝料の種類と計算方法、そして診断書の重要性とその記載内容について詳しく解説します。
【関連記事】
1.むち打ちの主な症状と影響
むち打ちとは、交通事故などの衝撃により首に負担がかかって生じる神経症状のことを指します。
むち打ちの症状は多岐にわたり、人によって現れ方が異なります。
最も典型的な症状は、首や肩の痛み、こり、違和感です。
これは、事故の衝撃で首が前後左右に激しく揺さぶられ、頚部の筋肉や靭帯が過度に伸展したり、損傷したりすることによって生じます。
寝違えのような軽い症状から、頭を動かすことが困難になるほどの強い痛みまで、その程度は様々です。
また、痛みやこりだけでなく、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気といった症状を伴うことも珍しくありません。
これらは、頚部の損傷が自律神経に影響を与えたり、脳への血流に影響を及ぼしたりすることによって引き起こされると考えられています。
さらに、腕や指のしびれ、脱力感が生じることもあります。
これは、頚部から腕へと伸びる神経が圧迫されたり、損傷を受けたりすることによるものです。
場合によっては、集中力の低下や不眠といった精神的な症状が現れることもあり、日常生活に大きな影響を及ぼします。
これらの症状は、事故直後には現れず、数時間後、あるいは数日経ってから徐々に現れるケースも少なくありません。
そのため、「事故に遭ったけれど、特に痛いところはないから大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは非常に危険です。
被害者自身は軽傷だと思っても、後に症状が悪化することもあり、通院の継続や専門医による診断が重要です。
症状が軽いうちに適切な治療を開始しないと、慢性化して後遺症として残ってしまう可能性もあります。
また、事故直後に通院を行わないことによって、後の示談交渉の際に、事故と症状の因果関係を争われることにもなりかねません。
むち打ちは、レントゲン検査では異常が認められにくいことも多く、その診断が難しいとされています。
骨折や脱臼のように骨そのものに異常がないため、レントゲン画像では異常が見つかりにくいのです。そのため、症状の訴えと医師の診察が診断の重要な要素となります。
交通事故によるむち打ちは、単なる身体的な不調にとどまらず、精神的な苦痛や経済的な負担も伴います。
仕事に支障が出たり、趣味の活動ができなくなったりすることで、精神的なストレスも大きくなるでしょう。
また、治療費や休業による収入減など、経済的な負担も無視できません。
このような状況において、適切な治療を受けることはもちろんのこと、慰謝料や損害賠償といった法的な側面についても理解しておくことが重要です。
特にむち打ちの場合、その症状の特性から、適正な慰謝料の算定が争点となることも少なくありません。
2.慰謝料の種類と計算方法の違い
⑴ 慰謝料の種類と算定基準
交通事故の慰謝料には、大きく分けて以下の3種類があります。
- 入通院慰謝料:治療のために入院・通院した期間・日数を元に計算
- 後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合に発生
- 死亡慰謝料:死亡事故に該当する場合
慰謝料の計算方法には”基準の違い”があります。
- 自賠責基準(国の最低限保障)
- 任意保険基準(各保険会社の独自基準)
- 弁護士(裁判)基準(過去の裁判結果に基づく)
適正な金額を得るには、弁護士基準での請求が最も有利とされています。
慰謝料の内訳として「入通院慰謝料(入院・通院日数ベース)」や「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があり、例えば【自賠責】では通院1日あたり4,300円(2023年4月以降の基準)、また弁護士基準では1ヶ月:約15〜20万円、3ヶ月:約53〜73万円、6ヶ月:約89〜116万円が目安です(すべて一例で、症状や日数、固定のタイミングにより増減)。
詳細な金額は表などで示されることも多く、被害者側の過失割合によって減額される場合があり、賠償金の計算には通院日数、症状固定日、後遺障害の有無など多くの要素が影響します。
また、保険ごとの対応の違いとして、
- 【自賠責保険】:最低限の補償として入院・通院慰謝料、交通費、休業損害など
- 【任意保険】:示談代行サービスや契約内容で補償範囲や金額に違いあり、自分に過失がある場合も一定額がもらえるケースあり
- 【人身傷害特約】:自分が加害者でも一定の保険金を請求できる
といった特徴があります。
⑵ 実際の事例における任意保険基準と弁護士基準の慰謝料の差~当事務所の依頼者の事例~
各基準による慰謝料金額の具体的な違いについて、当事務所で実際に取り扱った事案から以下のAさんの事例をご紹介いたします。
Aさんは、北海道札幌市在住で、タクシー乗車中に後方からの追突を受け、頚椎捻挫・腰椎捻挫のいわゆる「むち打ち」と言われる症状を発症しました。
その後、コルセット着用や病院でのブロック注射、リハビリ等を経たうえで、事故から約6か月半が経過した時点で症状固定となりました。
症状固定となって間もなく相手損保から示談金額の提示がありましたが、慰謝料金額については60万円程度の提案でした。
この相手損保の慰謝料の提案額が低いのではないかとお考えになったAさんは、当事務所にご相談され、当事務所の弁護士が相手損保に対する示談交渉を行うことになりました。
幸いAさんは、ご自身が所有されている自動車の保険に弁護士費用特約を付けていましたので、弁護士費用のご負担なくご依頼いただくことができました(今回のように、弁護士費用特約は、保険契約している車両での事故でなくても使えるケースが多いです。)
本件をお引き受けした後、当方から、相手損保に対して最初に弁護士(裁判)基準の満額である93万円程度を提示したところ、相手損保からはその8割の金額である74万円程度の再提案がありました。
なお、相手損保が弁護士に対しても弁護士基準の8割の金額を提案してくることはよくあります。
この時点で、既にご依頼前の約60万円から約74万円に増額できていましたが、担当弁護士は増額交渉を継続しました。
そうしたところ、休業損害等の慰謝料以外の争点もあったため多少時間を要しましたが、1か月程度の交渉にて、最終的に慰謝料については90万円程度を獲得することができました。
この事案では、ご依頼前の約60万円から約90万円まで増額できましたが、このように任意保険基準と弁護士基準では30万円以上も金額の違いがあったことになります。
⑶ 症状固定前の治療費打切りには要注意!
交通事故の治療を続けていると、相手損保が治療の打切りを打診してくることが多いですが、この任意保険による「症状固定前の打切り」には注意が必要で、保険会社の治療費打切りの時点で通院をやめてしまうと、治療費や慰謝料などの賠償範囲がその時点までとなってしまいます。
適切な賠償金を得るためには、たとえ保険会社から打切りの打診があっても、医師が治療の必要性を認めている間は病院を継続受診することが必要です。
また、医師が症状固定の診断をするまでの治療費を認めてもらえるよう延長の交渉をするなどの対応も必要です。
交通事故の被害に遭った場合、弁護士への早期相談が勧められていますが、弁護士に相談すると、治療終了後の慰謝料や賠償金の増額交渉だけでなく、治療費の延長交渉や必要な診断書の取得の代行など多くのメリットがあります。
「弁護士費用特約」で弁護士費用が実質無料となる場合もありますし、着手金無料や成功報酬型の法律事務所も増えていますので、気軽に弁護士の活用を検討してみてください。
3.診断書の重要性と書き方
交通事故に遭い、むち打ちの症状が現れた場合、最も重要となるのが「診断書」です。
診断書は、ご自身の症状が交通事故によって引き起こされたことを医学的に証明する、場合によっては唯一の書類であり、加害者側や保険会社に対して損害賠償請求を行う上で不可欠な証拠となります。
⑴ 診断書の重要性
診断書の重要性は、以下の点に集約されます。
- 因果関係の証明:診断書は、交通事故とご自身の症状との間に医学的な因果関係があることを証明します。これがなければ、「事故とは関係のない症状ではないか」と加害者側や保険会社に主張され、適切な補償を受けられない可能性があります。
- 治療の必要性の証明:診断書には、医師が診断した傷病名や症状、それに対する治療方針が記載されます。これにより、行われる治療が交通事故による症状に対するものであることが明確になり、治療費の請求根拠となります。
- 後遺障害認定の基礎:むち打ちの症状が長期化し、後遺症として残ってしまった場合、後遺障害の等級認定を申請することになります。その際、診断書の内容は後遺障害の有無や等級を判断する上で極めて重要な資料となります。症状の推移や治療経過が詳細に記載されていることが、適切な等級認定につながります。
- 慰謝料算定の根拠:交通事故における慰謝料は、入通院期間や症状の程度によって算定されます。診断書に記載された傷病名、症状、治療期間などが、慰謝料の金額を決定する上で重要な要素となります。
⑵ 診断書に記載されるべき主要な項目
- 傷病名:「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」など、医師が診断した具体的な病名が記載されます。
- 初診日:交通事故後、初めて医療機関を受診した日が記載されます。事故発生から初診までの期間が短いほど、事故との因果関係が認められやすくなります。
- 負傷の原因:「交通事故による」と明確に記載されていることが重要です。
- 主要な症状:患者が訴える症状(首の痛み、頭痛、しびれなど)が具体的に記載されます。医師が客観的に確認できる所見(可動域制限、圧痛など)も記載されます。
- 治療内容と期間:どのような治療が行われているか(投薬、リハビリ、物理療法など)や、今後の治療方針、治療期間の見込みなどが記載されます。
- 全治の見込み:症状が完全に回復するまでの見込みが記載されます。症状が残存する可能性がある場合は、その旨も記載されます。
⑶ 医師への症状の伝え方と注意点
診断書の内容は、患者自身の訴えに基づいて医師が作成します。
特に、むち打ちの場合には、自覚症状が主となり、他覚的に確認できる可動域制限等の所見がないことも珍しくありません。
そのため、医師に正確かつ具体的に症状を伝えることが非常に重要です。
- 発生時の状況を正確に伝える:交通事故がどのように発生し、ご自身の身体にどのような衝撃があったのかを具体的に伝えます。例えば、「追突されて首がガクンとなった」「横からぶつかられて身体が横に振られた」など、状況を詳細に説明しましょう。
- すべての症状を具体的に伝える:痛みだけでなく、しびれ、めまい、吐き気、耳鳴り、不眠、集中力の低下など、自覚するすべての症状を具体的に伝えます。痛みの程度(ズキズキする、重い、ピリピリするなど)、頻度、症状が現れる時間帯なども詳しく伝えましょう。
- 症状の変化を記録する:毎日、ご自身の症状の変化を記録することをお勧めします。痛みの強さ、症状が出た時間、改善したこと、悪化したことなどを記録し、診察時に医師に提示することで、医師はより正確な診断を下しやすくなります。
- 遠慮せずに伝える:医師に遠慮して症状を軽めに伝えたり、伝え忘れてしまうことがないようにしましょう。ご自身の身体のことですから、気になる症状はすべて正直に伝えてください。
- 既往歴や持病も伝える:以前からの持病や既往歴がある場合は、それがむち打ちの症状に影響を与える可能性もあるため、医師に伝えておきましょう。
- 複数の医療機関を受診しない:原則として、診断書は一つの医療機関で作成されるべきです。複数の医療機関を受診すると、診断書の内容に矛盾が生じたり、治療の一貫性が失われたりして、保険会社から不当な評価を受ける可能性があります。ただし、専門医のセカンドオピニオンが必要な場合は、主治医と相談の上で検討しましょう。
⑷ 診断書が作成された後の確認
診断書が作成されたら、必ず内容を確認しましょう。
ご自身が訴えた症状がすべて記載されているか、病名や初診日、負傷の原因が正確に記載されているかなどを確認します。
もし、誤りや不足している点があれば、すぐに医師に申し出て訂正してもらいましょう。
交通事故の被害に遭われた方が、適切な慰謝料や補償や後遺障害等級の認定を受けるためには、正確で具体的な診断書が不可欠です。
4.弁護士に依頼するメリット
交通事故に関する手続きは、上でご説明した診断書の内容だけでなく、その後の示談交渉や後遺障害の申請など、非常に複雑で専門的な知識が求められます。
そして、多くの場合、加害者側の保険会社はできるだけ支払う慰謝料や賠償額を抑えようとします。
提示された金額が相場と比較して適切かどうか、ご自身で判断することは非常に困難です。
特にむち打ちの場合、自覚症状が中心となるため、その程度や慰謝料の相場を巡って争いになることも少なくありません。
そのような時に頼りになるのが、弁護士です。弁護士は、法律の専門家として、被害者の方の権利を守り、適正な慰謝料や賠償額を獲得できるようサポートします。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 示談交渉の代行:保険会社との煩雑な交渉を弁護士が全て代行します。これにより、精神的な負担が軽減され、治療に専念することができます。
- 適切な慰謝料の算定:裁判例に基づく適切な慰謝料の相場を把握しているため、保険会社が提示する金額が不当に低い場合には、増額交渉を行います。弁護士基準といわれる高い基準で慰謝料を請求できます。
- 後遺障害認定のサポート:後遺障害の等級認定は、非常に専門的な知識が必要です。弁護士は、適切な資料収集や申請手続きをサポートし、適正な等級認定が受けられるよう尽力します。
- 訴訟対応:交渉が決裂した場合でも、民事訴訟を提起して適切な賠償を得られるよう尽力します。
- 法律相談:疑問や不安な点をいつでも弁護士に相談できるため、安心して手続きを進めることができます。
5.まとめ
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、これまで数多くのむち打ち事案を解決して参りました。
被害者の方々が抱える痛みや不安に寄り添い、適正な解決へと導きます。
もし、交通事故に遭われてむち打ちの症状でお悩みの場合、また、保険会社との交渉でお困りの場合は、一度、当法律事務所にご相談ください。
初回の相談は無料で行っております。
早期にご相談いただくことで、より有利な解決に繋がる可能性が高まります。
ご自身の権利を守り、事故の被害から一日も早く回復するためにも、弁護士のサポートをぜひご検討いただければと思います。
投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。
突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
【弁護士が解説】むち打ち慰謝料の相場と交通事故後に取るべき正しい対応とは?(後遺症・通院・慰謝料増額のポイント)
交通事故に遭い、むち打ち症(頚椎捻挫、頚部挫傷)と診断された場合、多くの方が気になるのは、今後どのように治療を進めたら良いかという点やその慰謝料の相場などでしょう。
後遺症が残る可能性や、通院にかかる負担への不安、そして被害に遭った訳ですから慰謝料を増額したいという思いは当然です。
慣れない交通事故の手続きや、今後への不安から、適切な判断ができずに悩んでしまう方も少なくありません。
本記事では、交通事故におけるむち打ちの慰謝料の相場について、多くの交通事故被害者の方のサポートをしてきた弁護士が詳しく解説いたします。
さらに、相場程度の慰謝料を得るために必要な通院日数や、交通事故後に取るべき正しい対応、そして慰謝料を増額するためのポイントについてもご紹介します。
むち打ちの症状にお悩みで、今後の対応に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。
【関連記事】
1.むち打ちとは?|事故後すぐに症状が出ないケースも
「むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)」とは、追突事故などで首がムチのようにしなることで起こる外傷です。主な症状は以下の通りです。
・首や肩の痛み
・頭痛、めまい、吐き気
・手足のしびれや脱力感
事故直後は症状が軽くても、数日後に悪化するケースもあります。
放置せず、事故後は速やかに整形外科などの病院を受診しましょう。
2.慰謝料とは?|精神的苦痛に対する金銭的補償
交通事故における慰謝料とは、怪我によって被った精神的な苦痛に対して支払われる金銭のことです。むち打ちの場合、以下の2つが主に該当します。
①入通院慰謝料:通院期間や治療日数に応じて支払われる
②後遺障害慰謝料:後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に支払われる
3.むち打ち慰謝料の算定基準を理解する(自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の違い)
交通事故によるむち打ちの慰謝料は、一律に決められているわけではありません。
慰謝料の金額は、交通事故の状況、被害者の負傷の程度、治療期間、実通院日数など、様々な要素を基に検討します。
一般的に、慰謝料を算定する基準として、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つが存在します。
それぞれの基準によって慰謝料の金額は大きく異なるため、その違いを理解しておくことが重要です。
(1)自賠責保険基準:最低限の補償
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、すべての自動車に加入が義務付けられている保険です。被害者の救済を目的としており、最低限の補償を行うための基準が定められています。
自賠責保険基準による慰謝料は、治療期間や実通院日数に応じて算出されますが、最低限の補償を目的にしていますので、その金額はどうしても低額になります。
具体的には、「4300円×実治療日数×2」、または「4300円×総治療期間」のいずれか少ない方が慰謝料として支払われます(2020年4月1日以降の事故の場合)。
なお、後遺障害等級が認定された場合には、別途後遺障害慰謝料(後遺障害保険金)が支払われます。
(2)任意保険基準:保険会社独自の基準
任意保険は、自賠責保険では賄えない部分を補填するために、自動車の所有者が任意で加入する保険です。
各保険会社が独自に慰謝料の算定基準(任意保険基準)を設けていますが、一般的には自賠責保険基準よりも高額になることが多いです。
ただし、その算定方法は公開されておらず、保険会社によって金額が異なる場合があります。
保険会社から提示される慰謝料は、この任意保険基準に基づくものですが(最低限の自賠責保険基準で提示してくる担当者もいます)、あくまで保険会社の都合で決められている基準ですから、被害者にとって適正な金額とは言えません。
被害者側が弁護士に依頼しなければ、保険会社は、この自社の基準である任意保険基準に基づいて示談交渉を進めてきます。
(3)裁判基準(弁護士基準):適正な賠償を目指す
裁判基準(弁護士基準)は、過去の裁判例に基づいて確立された慰謝料算定基準です。
3つの中で最も高額になる可能性が高い基準となります。交通事故に強い弁護士が示談交渉を行う際や、裁判になった場合に用いられます。
裁判基準では、基本的にむち打ちの症状の程度や治療期間に応じて慰謝料を算定しますが、慰謝料の目安としては、例えば、他覚所見のない神経症状の場合、3ヶ月の治療期間で53万円程度、6ヶ月の治療期間で89万円程度となります。
これはあくまで目安であり、個別の事案によって増減する可能性があります。
また、関西地方の裁判所では独自の基準があり、これより低い金額となることが多いなど、地方によっても若干の違いが出ることがあります。
後遺障害等級が認定された場合には、さらに後遺障害慰謝料が加算されます。
例えば、むち打ちで後遺障害等級14級9号が認定された場合、裁判基準の後遺障害慰謝料の相場は110万円、12級13号の場合は290万円となります。
このように、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高額になりますので、慰謝料を増額するためには、この裁判基準で交渉することが重要になります。
ただし、弁護士に依頼せずに被害者ご自身が保険会社に裁判基準で慰謝料を要求しても、応じてもらえないことが多いようです。
4.慰謝料相場と相場程度の慰謝料を得るために必要な通院日数(適切な通院頻度と期間)
(1)むち打ち慰謝料の相場
交通事故被害者の方からご相談をお受けすると、「慰謝料の相場はどのくらいですか?」というご質問をよくお受けします。
交通事故の慰謝料は、お怪我の症状の程度や治療期間などを基に算定されますので、「慰謝料の相場」がどのくらいか?というのは一概には言えませんが、むち打ちの場合、一般的には治療期間が3ヶ月から6ヶ月の間の方が多いです。
そして、その場合の裁判基準の通院慰謝料(傷害慰謝料)は、53万円~89万円ですので、このくらいがむち打ちの慰謝料の相場と言えるかもしれません。
ご参考までに月10日程度通院した場合の自賠責基準と裁判基準の慰謝料の目安も載せておきます。
むち打ち慰謝料の金額例(目安)
| 通院期間 | 通院日数 | 自賠責基準の慰謝料 | 裁判基準の慰謝料 |
| 1ヶ月 | 10日 | 8万6000円 | 19万円 |
| 3ヶ月 | 30日 | 25万8000円 | 53万円 |
| 6ヶ月 | 60日 | 51万6000円 | 89万円 |
(2)必要な通院日数
自賠責保険基準の場合は、「4300円×実治療日数×2」、または「4300円×
一方、裁判基準で慰謝料を算定する場合、基本的には治療期間(通院期間)で算定します。
そのため、通院日数は慰謝料の計算にそれほど影響せず、週に2~3回通院した場合でも、週に4~5回通院した場合でも、慰謝料の金額は変わらないということになります。
なお、以前は、裁判基準でも、通院頻度が少ない場合、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とするとされていました(「3倍ルール」などと呼ばれていました。)。
例えば、通院期間は6ヶ月間でも、週1回(月4回)程度の通院で、合計の実通院日数が24回だった場合、通常の裁判基準では通院6ヶ月で慰謝料89万円になりますが、実通院日数の3倍程度とされてしまうと、「実通院日数24回×3=72日」で2ヶ月半程度の通院という評価になり、慰謝料が約43万円になってしまいます。
このように、以前の基準では、通院頻度が週2回以下の場合には通常の裁判基準よりも慰謝料が減額されてしまうことがありました。
これは、加害者側の保険会社にとっては有利な基準ですので、未だに年配の担当者が、この3倍ルールを持ち出して慰謝料を減額させようとするケースもあります。
しかし、現在の基準では、この3倍ルールが適用されるのは、「通院が長期にわたる場合」(概ね1年以上)に限定されることになっており、例えば加害者側が6ヶ月程度の通院期間の場合に3倍ルールの主張をしても、基本的には裁判所が認めていない印象です。
このように、特に裁判基準では、慰謝料算定の上で、必要な通院日数というものはありません。
また、そもそも慰謝料のために通院する訳ではなく、治療の必要に応じて通院したことの結果として通院を強いられた慰謝料を算定するということですから、医師の指示の下で必要な治療を受けていただくということが原則になります。
ただ、むち打ちの場合、一般的に他覚所見がないことが多いため、適切な頻度での継続的な通院が、症状の存在や治療の必要性を客観的に示す要素になり得ますので、自己判断で通院を中断したり、回数を減らしたりすることは避けるべきです。
特に、急に通院頻度が減ると、症状が改善したと認識されてしまう場合もありますので、注意が必要です。
そして、上でご説明した3倍ルールなども考えると、一般論としては、週に2~3回程度の通院が適切と言えるように思います。
なお、整骨院や接骨院への通院も、慰謝料の算定においては整形外科への通院と同様に扱われますが、事前に医師に相談して指示(同意)を得ておくことが必要です。
5.慰謝料額が変動する要因
むちうち事故における慰謝料額は、以下の要因で大きく変わります。
- 通院日数・通院期間:実際に通った期間や日数によって算定される
- 通院頻度:毎月の通院回数も考慮される可能性がある
- 後遺障害等級の認定有無:14級9号などに該当すれば増額
- 事故の状況(過失割合):過失があれば減額される
6.交通事故後に取るべき正しい対応(初期対応が重要)
交通事故に遭ってしまった場合、適切な初期対応を取ることが、その後の慰謝料請求や損害賠償請求において非常に重要になります。以下の点に注意して、冷静に対応しましょう。
- 警察への連絡:交通事故が発生した場合は、速やかに警察に連絡し、事故状況の確認と届け出を行いましょう。また、お怪我をされた場合は、診断書を提出して人身事故に切り替える手続きをした方が無難です。
- 加入保険会社への連絡:ご自身が加入している自動車保険会社にも、事故の状況を速やかに報告しましょう。保険会社からのアドバイスやサポートを受けることができます。弁護士費用特約が付いている場合は、弁護士費用を保険でまかなうことができますので、弁護士特約の使用の可否も確認しましょう。
- 医療機関での受診:事故直後は症状がなくても、後からむち打ちなどの症状が現れることがあります。速やかに医療機関を受診し、医師の診断を受けましょう。交通事故から時間が経過してしまうと事故との因果関係を争われる場合がありますから、とにかく早く受診することが重要です(原則として、事故から2週間以内に受診しないと自賠責保険が適用できません。)。また、通院の際には、医師に症状を詳しく伝え、適切な治療を受けるようにしてください。事故直後に医師に症状を伝えていないと、カルテや診断書に記載されません。診断書に記載のない症状は、事故との関連性を認めてもらえませんので、全ての症状を伝えることが重要です。治療期間中も、医師にはなるべく症状を詳しく伝えることが重要です。後遺障害認定や裁判でカルテが提出されることもありますが、日々の診察で症状を訴えていないと症状が改善されているなどと捉えられてしまうこともあります。
- 弁護士への相談:交通事故後の手続きや、相手方との交渉に不安を感じた場合は、早めに交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
7.弁護士による交渉のメリット(慰謝料増額と手続きの負担軽減)
(1)専門知識と交渉力:慰謝料増額の可能性
交通事故の被害者が、保険会社と直接交渉を行う場合、提示される慰謝料の金額が自賠責保険基準や任意保険基準に基づいたものになりますから、裁判基準と比較して低額になります。
一方、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士は裁判基準で慰謝料の交渉をしますので、慰謝料を増額できる可能性が高く、大きなメリットがあります。
特に、交通事故に強い弁護士は、交通事故に関する豊富な知識と経験がありますから、適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
(2)手続きの負担軽減:治療に専念できる環境
交通事故後の手続きは煩雑で、精神的な負担も大きいものです。
弁護士に依頼することで、保険会社との連絡や書類作成、示談交渉など、一切の手続きを代理してもらうことができます。
これにより、被害者は治療に専念することができ、精神的な負担も軽減されます。
(3)後遺障害等級認定のサポート:適切な等級認定を目指して
むち打ちの症状が長期間にわたり、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。
しかし、後遺障害等級の認定手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。医師に適切な内容で後遺障害診断書を作成してもらうことも重要です。
事前認定という手続きで加害者側の保険会社に手続きを任せることもできますが、交通事故に強い弁護士に依頼すれば、後遺障害等級の認定についてもサポートを受けることができ、保険会社に任せるよりも適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まるといえます。
(4)裁判になった場合の対応:適正な賠償金の獲得
示談交渉がうまくいかず、裁判になった場合でも、弁護士に依頼していれば、基本的に裁判所での主張・立証活動は弁護士が行いますので、被害者が裁判に出席する場面は少なく、弁護士に裁判対応を任せることができます。
逆に、保険会社としては、弁護士が付いていると、裁判を提起される可能性があることも考えて示談交渉を行わざるを得ず、慰謝料増額などの被害者側の要求を受け入れやすいという側面もあります。
弁護士に依頼する最大のメリットは、やはり適正な賠償金を獲得できる可能性が高まることです。
保険会社から提示された慰謝料に納得がいかない場合や、今後の手続きに不安を感じている場合は、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
無料相談を実施している法律事務所も多くありますので、まずは気軽に相談してみましょう。
8.むち打ちの被害者が弁護士に示談交渉を依頼したことで大幅に慰謝料が増額した事例
さて、ここからは当事務所にご依頼いただいた依頼者様の具体的な事例をご紹介します。
⑴ 事案の内容~むちうちの治療終了後に保険会社基準で示談提示を受けた事例~
鳥取県在住のMさんは、自宅近くの道路を自動車で走行中、右折するために交差点内で停止して対向車の通過を待っていた際に、後方から走行してきた後続車に追突される事故に遭いました。
加害者は、事故当時、仕事中で急いでいてスピードを出していましたが、衝突の直前にカーナビを確認したため、Mさんが交差点内で停止していることに気が付くのが遅れ、相当なスピードで追突してしまい、Mさんの車両の後部は大きく損傷しました。
この交通事故で、Mさんはむち打ち(頚椎捻挫)の怪我を負い、整形外科で治療をしましたが、事故から5ヶ月強で加害者側保険会社から治療費を打切りの打診を受け、それを了承して治療を終えました。
そして、Mさんは、その後しばらくして加害者側保険会社から慰謝料などの示談提示を受けました。
このときの提示された示談金の金額は、総額で約42万円となっていました。
しかし、Mさんは、治療終了後も完全にむち打ちの症状が治った訳ではなく、首の痛みなどを感じていたこともあり、保険会社の提示額では少ないと感じました。
そこで、インターネットで交通事故の示談金の相場を調べていたところ、当ホームページを見つけていただき、当事務所にお問合せをいただきました。
⑵ 示談交渉で約2倍に増額
Mさんからご依頼を受け、担当弁護士は、加害者側保険会社からMさんの診断書や診療報酬明細書などの資料を開示してもらい、裁判所基準で慰謝料等を算定しました。
そうしたところ、裁判所基準では総額約82万円を請求できる計算となり、この金額を保険会社に請求して示談交渉を行いました。
なお、当初保険会社が提示していた約42万円の金額は、上で説明した任意保険基準だと思われますが、自賠責保険基準とほとんど変わらないような金額でした。
弁護士との示談交渉では、保険会社は裁判所基準の8割程度の金額を主張していましたが、交渉を続けた結果、最終的に80万円まで増額させることができ、示談が成立しました。
このように、Mさんの事例では、慰謝料を裁判所基準で交渉することで、当初の保険会社の示談提示から大きく増額させることができました。
また、Mさんは弁護士費用特約を使用できましたので、弁護士費用は全てご自身の保険会社に負担してもらうことができ、示談金全額を受け取ることができました。
9.まとめ(弁護士への相談が解決への近道)
交通事故でむち打ち(頚椎捻挫)の怪我を負ってしまった場合、少しでも症状が改善するよう医師の指示の下で適切な頻度で通院して治療を行うことが重要です。
それが結果的に適正な慰謝料を得ることにもつながります。
後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定を受けることも検討しましょう。
また、交通事故によるむち打ちの慰謝料は、算定基準によって大きく異なります。
適正な慰謝料を得るためには、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉をする必要があります。
保険会社から早期解決を促され、免責証書(示談書の代わりになるもの)が送られてくることがありますが、一度署名してしまうと示談のやり直しはできませんので、安易にサインしないよう注意してください。
もし、交通事故後の手続きに不安を感じている場合や保険会社から提示された慰謝料に納得がいかない場合は、迷わず弁護士にご相談ください。
当事務所では、交通事故のご相談は無料でお受けしております。
投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
交通事故で腱板損傷|慰謝料相場・後遺障害等級・示談交渉の注意点
今回は、「肩腱板損傷の示談交渉で気をつけたい慰謝料金額の落とし穴」について、ご紹介いたします。
交通事故で腱板損傷(肩腱板断裂など)を負った場合、日常生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。
治療を終え、いざ保険会社との示談交渉が始まると、「提示された慰謝料が適正な金額なのか?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
このケガは、慰謝料や示談金の金額が後遺障害等級の認定によって大きく変わるため、早い段階で正しい知識と対策が必要です。
この記事では、交通事故による肩腱板損傷の被害者が、示談交渉で損をしないために知っておくべき慰謝料のポイントを解説します。
後遺障害の認定基準から、保険会社の提示額の落とし穴、そして弁護士に相談するメリットまで、被害者の方の解決に必要な情報が満載です。
適切な慰謝料を受け取り、安心して治療後の生活を送るためにも、ぜひ最後までお読みください。
1.交通事故における肩腱板損傷の慰謝料と示談金の基礎知識
⑴ 腱板損傷とは何か
肩の関節は、「上腕骨」「肩甲骨」「鎖骨」という3つの骨で構成されていますが、覆っている骨の部分が少なく非常に不安定です。
この安定性を保つ上で、腱板が非常に重要な役割を担っています。
腱板は、「棘上筋」「棘下筋」「肩甲下筋」「小円筋」という4つの筋肉の腱で構成され、上肢の複雑な可動を可能にする重要なものです。
腱板損傷とは、これらの腱の一部、または全てが損傷したり、裂けたりする症状を指します。
交通事故の強い衝撃によって、肩が不自然にひねられたり、直接的な打撃を受けたりすることで、腱板に過度な負荷が生じ、損傷することがあります。
損傷の程度は、部分的なものから完全に断裂するものまで様々です。骨折や脱臼を伴うケースもあります。
⑵ 肩腱板損傷の主な症状と事故による受傷例
腱板損傷の主な症状は、次のとおりです。
①肩の痛み:特に腕を上げたり、特定の動きをしたりする際に痛みが強まります。夜間に痛みが悪化することも少なくありません。
②腕が上がらない:腕を上げる動作が制限されたり、まったくできなくなったりすることがあります。
③可動域の制限:肩の動き全体が制限され、日常生活に支障をきたすことがあります。
交通事故による受傷例としては、バイク事故や自転車事故で肩を地面に強打したケースなどが挙げられます。
事故直後から肩の痛み等の症状が出たという被害者の方も多いですが、事故直後には「むちうち」による首の痛みと混同されやすく、腱板損傷が認められないまま見過ごされてしまう可能性もあります。
見過ごされている期間が長ければ長いほど不利になってしまうので、事故後、少しでも肩に違和感がある場合は、速やかに整形外科を受診し、MRI検査など精密な検査を受けた方が良いでしょう。
⑶ 慰謝料の計算方法と示談金の相場
腱板損傷に直接関連する慰謝料として、以下の2種類が挙げられます。
①入通院慰謝料(傷害慰謝料):事故による怪我の治療のために病院に通院・入院したことに対する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
②後遺障害慰謝料:治療を継続しても完治せず、後遺障害が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。請求にあたっては、予め自賠責保険会社によって後遺障害等級の認定がなされていることが重要です。
腱板損傷の場合、治療期間や後遺障害の有無によって、これらの慰謝料が算定されることになります。また、慰謝料の計算には、以下の3つの基準があります。
①自賠責保険基準:自賠責保険会社が定める最低限の基準で、最も低い金額になります。
②任意保険会社基準:各任意保険会社が独自に定めている基準で、自賠責保険会社基準よりは高いものの、裁判所基準より低いことが殆どです。
③裁判所基準(弁護士基準): 過去の判例・裁判例に基づいており、最も適正な金額とされる基準です。弁護士に依頼した場合に適用されることが多く、示談の金額も高額になる傾向があります。
示談金は、これらの慰謝料に加えて、治療費、休業損害、後遺障害逸失利益などが含まれた総額となります。
腱板損傷の示談金の相場は、損傷の程度、治療期間、後遺障害等級、そしてどの慰謝料基準で計算するかによって大きく変動します。
⑷ 腱板損傷の後遺障害慰謝料相場早見表(等級別)
※この表は目安額です。実際の金額は症状・交渉内容で変動します。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
| 10級 | 187万円 | 550万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
2.後遺障害認定:肩腱板損傷で注意すべきポイント
腱板損傷の治療を続けても症状が改善せず、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害として認定される可能性があります。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった補償が受けられますが、その認定には注意すべきポイントがいくつかあります。
⑴ 後遺障害等級と可動域制限の関係
後遺障害は、その症状の重さによって1級から14級までの等級に分類されます。
腱板損傷の場合、肩関節の可動域制限が問題となることが多いです。
肩関節の可動域が、健常な方の可動域と比較してどの程度制限されているかによって等級が診断されます。
例えば、「肩関節の機能に著しい障害(可動域が健常の方の2分の1以下に制限される状態)」を残した場合は10級10号、「肩関節の機能に障害(可動域が健常の方の4分の3以下に制限される状態)」を残した場合は12級6号が認定される可能性があります。
後遺障害の等級認定には、医師の作成する後遺障害診断書が非常に重要です。
この診断書には、肩の痛みだけでなく、具体的な可動域の測定値などを正確に記載してもらう必要があります。
⑵ 後遺障害が非該当になるケースとその対策
腱板損傷による後遺障害について後遺障害等級の申請を行っても、残念ながら非該当となるケースはあります。非該当となる主な理由としては、以下のようなものが考えられます。
①症状の一貫性がない:事故直後から症状が出ていなかったり、治療を中断していたりする場合。
②医師の意見書が不十分:後遺障害の症状を裏付ける客観的な所見や詳細な記載がない場合。
③他覚的所見の不足:MRIなどの画像検査で腱板損傷が確認できない場合や、神経学的検査で異常が認められない場合。
④事故との因果関係が不明確:事故以外の要因(加齢など)による腱板損傷であると診断される場合。
後遺障害等級が認定される確率を上げるためには、以下の対策が重要です。
・事故後、すぐに医療機関を受診し、継続して治療を受ける。
・医師に症状を正確に伝え、記録に残してもらう。
・MRI検査など客観的な画像検査を必ず受ける。
・後遺障害診断書の内容を精査し、不足がないか確認する。
⑶ 後遺障害等級の判例・事例紹介
裁判では、腱板損傷の後遺障害等級について様々な判例が出されています。
例えば、可動域制限が器質的損傷によるとは認められないが痛みの症状は医学的に証明しうる神経症状(12級13号)だと判断した事例や、明確な器質的損傷が認められないが機能障害(12級6号)として判断した事例などがあります。
これらの事例は、個別の症状や治療経過、提出された証明などによって判断が異なります。
自分のケースがどの等級に相当するかを知るためには、交通事故に詳しい弁護士に相談し、過去の事例を踏まえたアドバイスを受けることが有効です。
3 示談交渉で損をしないための保険会社対応術
交通事故の被害に遭い、治療が終わると、加害者側の保険会社から示談金の提示があります。
しかしながら、この提示額は、必ずしも適正な金額であるとは限りません。
損をしないためには、保険会社との交渉術を身につけることが重要です。
⑴ 保険会社が提示する慰謝料の落とし穴
保険会社が最初に提示する慰謝料は、多くの場合、任意保険会社基準または自賠責保険会社基準に基づいて計算されており、裁判所基準(弁護士基準)よりも低く設定されています。
保険会社は営利企業であるため、できるだけ支払う金額を抑えようとします。
特に注意すべきなのは、治療期間が長引いてしまったり、後遺障害が残ったりした場合です。
保険会社は、治療の必要性や症状固定の時期について異議を唱えたり、後遺障害の認定を否定したりして、低い金額を提示することがあります。
⑵ 適切な対応・主張・立証の方法
保険会社との交渉を有利に進めるためには、以下の点に注意して適切な対応をとることが重要です。
①医療機関での適切な治療:事故直後から症状が改善するまで、担当医の指示に従い治療を継続し、中断しないようにしましょう。
②症状を伝える:問診の際、痛みや可動域の制限などを適切に伝えましょう。
③客観的な証明の収集:診断書、診療報酬明細書、画像データ(MRI、X線など)など、怪我の状況を裏付ける全ての書類を取り寄せ、保管しておきましょう。
④保険会社とのやり取りの記録:電話や書面でのやり取りは、日時、内容、担当者名を記録しておくか、書面で行うようにしましょう。
これらの情報が、示談交渉におけるあなたの主張を裏付ける重要な証明となります。
⑶ 増額交渉のためのポイントと流れ
保険会社からの提示額に納得できない場合は、増額交渉を行うことになります。
増額交渉の主なポイントは以下の通りです。
①裁判所基準(弁護士基準)の適用を主張する:保険会社の提示額が低い場合は、裁判所基準での計算を求めましょう。ただ、弁護士に依頼していないケースでは、保険会社が裁判所基準を認めることは少ないのが実情です。
②後遺障害の適正な評価:後遺障害が残っているにもかかわらず認定されなかった場合や、等級が低いと感じる場合は、異議申立てを検討しましょう。
③具体的な根拠の提示:増額を求める際には、ただ「もっとほしい」と主張するのではなく、治療の必要性、症状の重さ、日常生活への影響などを具体的に示し、必要があれば証拠を提示しましょう。
④専門家への相談:示談交渉は専門的な知識が必要となるため、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。
示談交渉は、通常、治療終了後または後遺障害認定後に行われます。
納得できない場合は安易に示談書にサインせず、専門家である弁護士のアドバイスを仰ぎましょう。
⑷ 示談交渉を有利に進める3つのチェックリスト
交通事故で腱板損傷を負い、慰謝料や示談金をできるだけ有利に獲得するためには、交渉の前段階での準備が何より重要です。
この3つを押さえるだけで、慰謝料増額の可能性が大幅に上がります。
1.治療継続
なぜ必要か:保険会社は「治療期間が短い=症状が軽い」と判断する傾向があります。途中で通院を中断すると、適切な期間継続した場合と比べて慰謝料額が大幅に下がる恐れがあり、後遺障害等級の認定も難しくなります。
そのため、痛みが軽くなっても自己判断で通院をやめず、医師が「症状固定」と判断するまで治療を継続しましょう。
2.診断書確認
なぜ必要か: 後遺障害等級の認定は、医師が作成する「後遺障害診断書」の内容に大きく左右されます。
しかし、医師は自賠責の認定要件までは熟知していないことも多く、重要な計測値や症状の記載が漏れるケースがあります。
診断書を受け取ったら、
・肩関節の可動域(健側との比較角度)が正確に記載されているか
・MRIやレントゲンの所見が反映されているか
を必ず確認し、必要なら追記依頼を行いましょう。
3.証拠保全
なぜ必要か:示談交渉では、口頭での主張よりも客観的な証拠の有無が金額に直結します。
腱板損傷の場合、以下の証拠をそろえておくと有利です。
- MRIやレントゲン画像データ
- 通院記録(診療明細書)
- 日常生活での不自由さを示すメモや写真(例:家事・仕事ができない様子)
- 保険会社とのやり取り記録(メール・書面・通話メモ)
これらは後遺障害等級の申請や増額交渉の際、強力な裏付け資料となります。
4 弁護士に依頼するメリットと選び方
相手方保険会社との示談交渉は、専門知識が必要な上、精神的な負担も大きいです。
そのため、交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼することは、多くのメリットをもたらします。
⑴ 法律事務所選びの基準
弁護士に依頼する最大のメリットは、裁判所基準(弁護士基準)での示談金獲得の可能性が高まることです。
また、保険会社との煩わしい交渉を全て任せることができるため、精神的な負担が軽減し、治療に専念できます。
弁護士を選ぶ際には、以下の基準を参考にしましょう。
①交通事故案件の実績:交通事故、特に人身傷害案件の取り扱い実績が豊富であるかを確認しましょう。腱板損傷のような専門的な知識が必要なケースでの経験があるかどうかも重要です。
②専門性と得意分野:交通事故に注力している法律事務所を選びましょう。
③費用体系:弁護士費用特約が利用できるか、着手金や報酬料が明確かを確認しましょう。無料相談を受け付けているかも重要なポイントです。
④担当弁護士との相性:実際に面談や電話などで話してみて、親身になって相談に乗ってくれるか、信頼できると感じるかを確認しましょう。
⑵ 無料相談・初回面談時のチェックポイント
多くの法律事務所では、交通事故の無料相談を実施しています。この機会を有効活用し、以下の点をチェックしましょう。
①質問への明確な回答:疑問に思っていることに対して、分かりやすく具体的な回答がもらえるか。
②見通しの解説:慰謝料の見込み額、後遺障害認定の可能性、今後の手続きの流れなどについて、具体的な見通しを解説してくれるか。
③費用に関する解説:弁護士費用について、分かりやすい説明がなされているか。追加費用が発生する可能性についても確認しましょう。
④契約を急がせないか:相談だけで終わり、考える時間を与えてくれるか。無理に契約を勧めないかどうかも重要です。
交通事故による腱板損傷は、その後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
適切な損害賠償を受けるためにも、早期に交通事故に強い弁護士に相談し、解決に向けた対応をとることを強くおすすめします。
⑶ 弁護士法人優誠法律事務所について
当事務所(弁護士法人優誠法律事務所)では、交通事故のご相談は無料です。
所属している全ての弁護士が、交通事故事件について豊富な経験を有しており、その経験や知識を生かし、治療中のフォローから、後遺障害の申請、相手方との示談交渉、ADRや裁判まで、各場面で適切なサポートを致します。
弊所は全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。
【関連記事】
投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
交通事故でむち打ち被害!後遺症が残った時の慰謝料請求ポイント
交通事故に遭って怪我をした被害者の多くが、むち打ち(むちうち)の症状を負っています。
むち打ちは、レントゲンやMRIでは異常が見つかりにくいことも多いですが、その症状や後遺症が深刻なケースもあります。
また、MRIなどで自覚症状の客観的裏付けとなる所見が得られることが少ないため、加害者の保険会社が早期に治療費を打ち切ることもあり、適切な補償(慰謝料など)を受け取るためには、正しい知識と手続きが不可欠です。
この記事では、むち打ちによる後遺症が残ってしまった場合に、どのように慰謝料を請求すれば良いのか、そのポイントを詳しく解説します。
今回の記事が、むち打ちの被害に遭われた方の助けになれば幸いです。
1.後遺障害認定と等級別の慰謝料・逸失利益
交通事故によるむち打ちで症状が長引き、後遺症として残ってしまった場合、適切な慰謝料や逸失利益を受け取るためには「後遺障害認定」を受けることが非常に重要になります。
後遺障害認定とは、交通事故によって負ってしまった症状が、これ以上治療しても改善の見込みがないと判断された場合に、その症状を「後遺障害」として認定する制度です。
この認定を受けることで、精神的苦痛に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)や、後遺障害によって将来得られるはずだった収入の減少分(逸失利益)を請求できるようになります。
後遺障害には、その症状の重さによって1級から14級までの等級が定められており、それぞれの等級によって慰謝料の金額や逸失利益の算定方法が異なります。
むち打ちの場合、一般的には14級9号が認定されるケースが多いですが、症状によっては上位の12級13号の等級が認定されることもあります。
なお、症状が残っていれば必ず後遺障害等級が認定されるという訳ではなく、非該当と判断されるケースも多いです。
後遺障害認定を受けるためには、医師による適切な診断書やカルテ、検査画像などの医学的な証拠を揃えることが不可欠です。
また、医師に適切な診断書等を作成してもらうためには、治療期間中に自覚症状を具体的に、かつ、継続的に伝えることも重要になります。
後遺障害の申請手続きは複雑で、適切な証拠を揃えるためには専門的な知識が必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。
弁護士は専門家として、適切なサポートと助言を行い、後遺障害申請の手続きだけでなく、示談交渉や訴訟においても、被害者が適切な賠償を受けられるよう尽力します。
2.後遺障害申請・認定の流れと症状固定のタイミング
後遺障害の申請・認定は、治療の経過と密接に関わっています。
ここでは、一般的な後遺障害申請・認定の流れと、「症状固定」という重要なタイミングについて解説します。
⑴ 治療の継続と症状の経過観察
交通事故後、まずは医療機関で適切な治療を受け、症状の改善に努めます。
この期間中は、定期的に医師の診察を受け、症状の変化や痛みの状態などを具体的に伝えることが重要です。
治療経過の記録は、後遺障害申請の際に重要な証拠となります。
また、症状によって整形外科でリハビリや投薬治療が行われますが、整形外科だけでなく、必要に応じて脳神経外科やペインクリニックの受診を検討すべき場合もあります。
病院での治療費は、通常、加害者側の任意保険会社が負担しますが(これを「一括対応」といいます)、保険会社が対応してくれない場合には、健康保険の利用も可能です。
⑵ 症状固定の判断
一定期間治療を継続した後、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断する時点を「症状固定」と言います(症状固定と判断された時点までが交通事故の賠償範囲となりますので、治療費や慰謝料の支払いはこの時点までとなります。)。
この症状固定の判断は、後遺障害申請において非常に重要なタイミングです。
症状固定と判断された時点で、残ってしまった痛み・しびれなどの症状が「後遺障害」として評価される対象となります。
むち打ちの場合、症状固定の時期には個人差がありますが、一般的には事故から6ヶ月程度が目安とされています。
しかし、改善が見込めるのであれば、無理に症状固定とせず、症状が改善するまで治療を続けるという判断もあり得ます。
医師と十分に話し合い、ご自身の症状を考慮して症状固定のタイミングを判断してもらうようにしましょう。
⑶ 後遺障害診断書の作成
症状固定後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
この診断書は、後遺障害の有無や等級を判断する上で最も重要な書類となります。
後遺障害診断書には、自覚症状、他覚所見(神経学的所見、画像所見など)、今後の緩解の見通しなどが詳細に記載されます。
医師には、ご自身の症状を正確に伝え、具体的な記載をお願いすることが重要です。
特に、神経症状の検査結果や治療経過が詳細に記されていることが望ましいです。
⑷ 後遺障害の申請手続き
後遺障害診断書が作成されたら、いよいよ後遺障害の申請を行います。
申請方法は大きく分けて以下の2種類があります。
- 事前認定(加害者側の保険会社による申請): 加害者側の任意保険会社が、被害者に代わって自賠責保険に申請を行う方法です。手間はかかりませんが、保険会社が主体となるため、被害者にとって不利な認定になる可能性もゼロではありません。保険会社からの連絡や示談交渉は、この認定後に本格化します。
- 被害者請求(被害者側による申請):被害者自身や代理人の弁護士が、自賠責保険に直接申請を行う方法です。必要な書類を全て被害者側で集める必要がありますが、ご自身で有利な証拠を提出できるため、より適切な認定を受けられる可能性が高まります。弁護士に依頼すれば、書類収集や申請手続きのサポートを受けられます。
⑸ 損害保険料率算出機構による審査
自賠責保険に提出された書類は、「損害保険料率算出機構」に送られ、専門家による審査が行われます。
審査では、提出された書類に基づき、場合によっては医療機関に医療照会を行うなどして、残存する症状が後遺障害に該当するか、該当するとして何級に相当するかを判断します。
機構は中立な立場で、提出された医学的資料から客観的に判断を行います。
⑹ 後遺障害等級の認定
審査の結果、後遺障害に該当すると判断されれば、後遺障害等級が認定されます。
認定された等級は、書面で被害者に通知されます。
もし、認定された等級に不服がある場合は、「異議申立て」を行うことも可能です。
そして、この後遺障害申請の結果通知を受けた後、加害者側の任意保険会社との本格的な示談交渉に入ります。
賠償金の計算もこの後遺障害等級を基に行われます。
この一連の流れの中で、特に重要なのが「症状固定のタイミング」と「後遺障害診断書の記載内容」です。
適切な後遺障害認定を受けるためには、これらの段階で慎重に対応し、必要であれば専門家である弁護士の助言を仰ぐことが賢明です。
3.等級(14級・12級)別の慰謝料金額と判例
後遺障害等級は、交通事故による精神的苦痛を金銭的に評価する際の重要な基準となります。
ここでは、むち打ちで認定される可能性のある主な等級(14級、12級)について、それぞれの慰謝料の目安と、関連する判例の傾向を解説します。
⑴ 後遺障害慰謝料の算定基準
後遺障害慰謝料には、主に以下の3つの算定基準があります。
- 自賠責保険基準:自賠責保険が定める最低限の基準です。他の基準より低額ですが、被害者側に過失がある場合でも、7割未満であれば減額されることなく、被害者が全額を受け取れます。過失が7割以上になると、重過失減額が適用されます。
- 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定めている基準です。自賠責基準よりは高額になることが多いですが、保険会社によって金額に差があります。保険会社からの提示額は、この基準に基づいていることが多いです。
- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づいて算定される基準で、最も高額になる傾向があります。弁護士が交渉する際や、裁判になった場合に適用される基準です。適正な賠償金を受け取るには、この基準を目指すことが重要です。
【後遺障害等級別の慰謝料目安(弁護士基準)】
以下に示す慰謝料額は、弁護士基準の目安です。
自賠責保険基準や任意保険基準では、これよりも低額になることが多い点にご留意ください。
後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)
- 慰謝料目安:約110万円
- 特徴:むち打ちでは多くの場合、この等級が認定されます。神経症状が残存していることが要件となり、客観的な画像所見などがない場合でも、医学的に説明がつく場合に認定されます。例えば、頚部や肩の痛み、しびれなどが断続的に続くケースなどが該当します。頚椎捻挫、腰椎捻挫といった診断名が多く、外傷性頚部症候群もこれに該当します。
- 判例の傾向:14級9号の認定には、自覚症状の一貫性、治療経過、神経学的所見(例えば、ジャクソンテスト、スパーリングテストの陽性反応など)や画像所見(椎間板の変性など)などが考慮されます。明確な他覚所見がなくても、一貫した自覚症状と治療の継続性が認められれば認定される可能性があります。通院期間や通院頻度も重要な要素となります。
後遺障害12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
- 慰謝料目安:約290万円
- 特徴:14級9号よりも症状が重く、神経症状が「頑固」に残存していると認められる場合に認定されます。14級9号と異なり、画像所見や神経学的所見など、客観的な医学的所見による裏付けが求められます。
- 判例の傾向:12級13号の認定には、MRIやCTなどの画像診断で神経根の圧迫や損傷が明確に確認できること、神経伝導速度検査(NCV)や針筋電図(EMG)などの検査で神経症状の裏付けがあること、あるいは神経学的な所見(筋力低下、反射異常、感覚障害など)が明確であることが重視されます。これらの客観的な証拠が不足している場合、12級の認定は極めて困難になります。
⑵ 判例から見る慰謝料額の傾向
慰謝料の金額は、上記目安をベースに、個別の事案によって増減することがあります。
例えば、以下のような要素が考慮されます。
- 治療期間と内容:長期間の治療や、手術などの侵襲的な治療を受けた場合は、慰謝料が増額される可能性があります。
- 症状の重篤性:痛みの程度や日常生活への影響が大きいほど、慰謝料は高額になる傾向があります。
- 就労への影響:後遺障害によって仕事に大きな支障が出た場合、逸失利益とは別に慰謝料が増額されることがあります。
- 過失割合:被害者にも過失がある場合、その過失割合に応じて慰謝料が減額されます。
- 増額事由の有無:ひき逃げや飲酒運転など、加害者側に問題が大きい場合などは、慰謝料が通常よりも増額される傾向があります。
⑶ 慰謝料の種類と違い(通院・入院・後遺障害)
交通事故で請求できる慰謝料には、次の3種類があります。
・入通院慰謝料(傷害慰謝料):治療のために通院・入院を強いられた精神的苦痛に対する補償
・後遺障害慰謝料:治療後も症状が残った場合の精神的苦痛への補償
・死亡事故慰謝料:被害者が亡くなった場合に支払われる慰謝料
これらの慰謝料は、治療期間や後遺障害の等級に応じて大きく異なります。
重要なのは、裁判所基準の慰謝料もあくまで目安・相場であり、個別の事案によって判断が異なるということです。
特に、高額な慰謝料を請求するためには、弁護士に依頼し、適切な証拠を揃え、交渉を進めることが非常に重要になります。
4.後遺症が残った場合の逸失利益の請求方法
後遺障害が残ってしまった場合、精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、「逸失利益」も請求することができます。
逸失利益とは、後遺障害によって、将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償のことです。
むち打ちの後遺症によって、仕事に支障が出たり、以前のように働けなくなったりした場合に重要となります。
⑴ 逸失利益の計算方法
逸失利益は、以下の計算式で算出されます。
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
- 基礎収入
- 原則:事故前年の年収を基礎とします。源泉徴収票や確定申告書などで証明します。
- 個人事業主:原則としては、事故前年の確定申告の所得額を基礎として算定されます。
- 主婦・学生など:収入がない場合でも、賃金センサス(厚生労働省が発表する賃金に関する統計データ)の平均賃金を基礎収入とすることができます。主婦の場合、女性の全年齢平均賃金が用いられることが多いです。学生の場合、卒業後の就労状況を考慮して算定されます。休業損害の計算にもこの基礎収入の考え方が適用されます。
- 労働能力喪失率
後遺障害によって、どれだけ労働能力が失われたかを示す割合です。それぞれの後遺障害等級に応じて設定されます。むち打ちで認定される可能性のある等級の目安は以下の通りです。
・後遺障害14級9号:5%程度
・後遺障害12級13号:14%程度
※これはあくまで目安であり、実際の職業や業務内容、残存する症状が仕事に与える影響などを総合的に考慮して判断されることもあります。減収の実態を客観的に示すことも重要です。 - 労働能力喪失期間
後遺障害によって労働能力が喪失する期間です。原則として、症状固定時から67歳までの期間とされます。ただし、むち打ちによる後遺障害の場合、症状の経過や年齢によって、喪失期間が限定されるケースもあります。例えば、14級9号の場合、症状の継続期間が短いと判断され、5年間程度に限定されることが多いです。 - ライプニッツ係数
将来の収入減少分を現在の一括払いに換算するための係数です。将来受け取るはずだった金銭を前倒しで受け取るため、その期間の利息分を割り引くためのものです。労働能力喪失期間に応じて係数が決まっています。
⑵ 逸失利益請求のポイント
- 正確な基礎収入の証明
事故前年の収入を証明する書類を確実に準備しましょう。
転職したばかりの場合や、個人事業主の場合は、複数年の収入実績を示すことでより正確な基礎収入を算定できます。 - 労働能力喪失率の適正な主張
労働能力喪失率は、等級によって目安はありますが、個々のケースで実際の労働への影響を具体的に主張することが重要です。
医師の診断書や、仕事内容の詳細、実際に支障が出ている業務内容などを具体的に説明できるように準備しましょう。 - 労働能力喪失期間の交渉
むちうちのケースでは、将来にわたる症状の継続性について争われることがあります。
医師の意見書や治療の継続状況、症状の一貫性などを示すことで、より長い期間の喪失期間を主張できる可能性があります。 - 弁護士への相談
逸失利益の計算は複雑であり、保険会社との交渉においても専門知識が不可欠です。
特に、将来の収入減少をどのように評価するかは、個別の事情によって大きく異なります。
弁護士に相談することで、適正な逸失利益の算定と、有利な交渉を進めることが可能になります。
弁護士費用は着手金や報酬金などがありますが、多くの弁護士事務所で無料相談を行っており、弁護士費用特約がある場合は、自己負担なく依頼できることも多いです。
5.被害者請求による異議申立てで14級9号が認定された頚椎捻挫の事例
さて、ここからは当事務所にご依頼いただいた依頼者様の具体的な事例をご紹介します。
⑴ 事案の内容~事前認定で後遺障害を申請するも非該当~
Hさんは、地元の北海道で自動車を運転中、信号待ちで停車している際に、後方から走行してきた後続車に追突される事故に遭いました。
加害者は、よそ見をしていて衝突の直前まで赤信号に気が付いておらず、かなりのスピードで追突したため、Hさんの車両の後部は大きく損傷しました。
この交通事故で、Hさんはむち打ち(頚椎捻挫)の怪我を負い、整形外科と整骨院で治療をしていましたが、事故から6ヶ月で加害者側保険会社が治療費を打ち切ったため、主治医もそのタイミングで症状固定の診断をしました。
しかし、その時点でも首の痛みや手のしびれなどの症状が残っていました。
そのため、Hさんは、加害者側保険会社の説明を受けて、主治医に後遺障害診断書を作成してもらった上で、そのまま保険会社に任せて事前認定で後遺障害の申請をしました。
ところが、非該当の結果となり、それを前提に加害者側保険会社から示談金として約120万円を提示されました。
これに納得できなかったHさんは、インターネットで検索して、当ホームページの異議申立てで後遺障害等級が認定された事案の記事をご覧になったとのことで、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。
⑵ 異議申立てで14級9号を獲得
Hさんからご依頼を受け、担当弁護士は、主治医にカルテ開示の依頼や医療照会を行って、Hさんの治療状況や症状経過に関する証拠を収集し、Hさんからも事故後からの症状の推移や残存している痛みやしびれの症状などについて聞き取りを行いました。
そして、自賠責保険に対して被害者請求で異議申立てをしました。
その結果、異議が認められ、頚椎捻挫について14級9号が認定されました。
⑶ 保険会社と裁判所基準で示談交渉
後遺障害等級の認定後は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などを計算して、加害者側保険会社と示談交渉を行いました。
Hさんの症状固定までの治療期間は約6ヶ月でしたので、裁判所基準で入通院慰謝料は約89万円、後遺障害慰謝料は14級の110万円を請求しました。
逸失利益については、Hさんが専業主婦でしたので、平均賃金(賃金センサス)を基礎収入として、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年間の計算で、約91万円を請求しました。
そして、交渉の結果、通院交通費や家事従事者の休業損害なども加え、総額で約420万円(治療費を除く)での示談となりました。
この示談金約420万円のうち、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計約200万円は、後遺障害等級が認定されていなければ受け取ることができなかったものになります。
また、入通院慰謝料や休業損害などの後遺障害以外の部分についても、当事務所へのご依頼前に保険会社が提示していた金額は約120万円でしたので、弁護士が裁判所基準で交渉したことによって100万円ほど増額できたことになります。
このように、Hさんの事例は、後遺障害等級の認定と慰謝料を裁判所基準で交渉することで、最終的な示談金を大きく増額させることができました。
6.まとめ
むち打ちは、一見軽微に見えても、後遺症が残ると日常生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。
そして、適切な慰謝料や逸失利益を受け取るためには、適切な後遺障害認定を受ける必要があります。
そのためには、医師に治療段階から症状を正確に伝え、医師との連携を密にし、適切な書類を準備することが不可欠です。
また、交通事故の被害に遭い、むち打ちによる後遺症で悩まれている方は、決して一人で抱え込まず、交通事故問題に強い弁護士に早めに相談することをお勧めします。
弁護士は、後遺障害認定のサポートから保険会社との交渉、そして万が一の訴訟まで、あなたの権利を守るために最善を尽します。
結果的に、損害賠償額についても、弁護士が間に入ることで適正な金額(裁判所基準)での解決が期待できます。
当事務所では、交通事故のご相談を無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【関連記事】
投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
むち打ち慰謝料が低くなる理由と保険会社との交渉術まとめ
交通事故でむちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)と診断され、適切な治療を受けているにもかかわらず、治療途中で保険会社から治療の打切りを打診されたり、低い慰謝料が提示される場合があります。
むち打ちの慰謝料の計算は、その症状や治療期間、通院頻度などによって大きく変動します。
また、保険会社とどのように交渉するかという点も慰謝料の金額に影響を与える重要な要素です。
そこで、今回は、むち打ちの慰謝料が相場より低くなりがちな理由を解き明かし、さらに保険会社からの治療打切り打診への対応策、慰謝料や治療費の減額リスクを回避する方法、保険会社に治療・通院期間の延長を認めさせるための交渉術などについて詳しく解説します。
【関連記事】
1.治療打切りや減額への対処法と治療期間延長のコツ
交通事故によるむち打ち治療において、最も多くの被害者の方が直面するのが、保険会社からの治療打ち切り打診です。
保険会社は、治療が一定期間に達すると「症状固定」と判断し、治療費の支払いを打ち切ろうとすることがあります。
保険会社としては、早期に治療費を打ち切ることで治療費の支出を抑えることができるというメリットがある上に、通院慰謝料も低額で抑えることができます。
これは、通院慰謝料が治療期間や通院回数によって算定されることから、早めに治療費を打ち切って治療期間を短くできれば、その分慰謝料の支払いも少なくすることができるためです。
ですから、保険会社にとっては、賠償金を少なくするためには治療費の打切りは早ければ早い方が良いということにはなります。
逆に、被害者にとっては、症状が改善していないにもかかわらず治療を打ち切られてしまうと、後遺症として症状が残り、その後の治療費が自己負担となってしまいます。
さらに、慰謝料の算定期間も短くなってしまうため、結果的に受け取れる慰謝料が、一般的な期間の通院をした場合と比べて大幅に減額される可能性があります。
被害者側が適切な補償を受けるためには、このような場面でも冷静に対処し、必要な治療期間の治療費を確保することが重要となります。
また、治療終了後に保険会社から提示される入通院慰謝料は、入院・通院日数も考慮して算定されるため、通院頻度が少ないと同じ期間通院した場合でも減額される可能性がありますので、適切な通院頻度で通院することも重要となります。
以下では、治療費打切りの打診があった場合の基本的な考え方と、それにどう対処していくべきか、また治療期間の延長を認めさせるための具体的な方法・流れについて解説していきます。
2.保険会社からの治療打切り打診への対応策
保険会社から治療の打切りを打診された場合、まず焦らずにその理由を確認することが重要です。
一般的には、診断書の内容や通院頻度などを基に、任意保険の保険会社として「これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない」と判断した場合などに打診されます。
特に、事故態様が軽微な場合は、保険会社が事故の賠償としてはこれ以上払えないと判断してしまい、早期に打切りを打診されることが多いです。
しかし、まだ症状が残っている、または、まだ改善の余地があると感じる場合は、安易に打切りを受け入れてはいけません。以下の対応策を参考に、適切な治療継続を目指しましょう。
⑴ 医師との綿密な連携
担当医には、診察のたびに現在の症状や改善の具合などを具体的に説明しておきましょう。
そうすることによって、診断書に「治療の継続が必要」といった内容を記載してもらいやすくなります。
また、保険会社が医師に対して医療照会をすることもありますが、基本的に事前に被害者に対して医療照会をすることを予告してきますので、予告された場合には、予め医師に保険会社から医療照会があることを知らせて、治療を継続して症状を改善させたいという希望をしっかり伝え、回答書や意見書に「症状固定には至っていない」ことやまだ治療の必要性があることを記載してもらいやすくしておきましょう。
医師の医学的見解は、保険会社との交渉において最も重要な証拠となります。
加害者側の保険会社からの連絡があった際も、医師から説明されている内容・治療の見込みなどの医師の意見を伝えることも大切です。
⑵ 通院頻度の見直し
むち打ちの治療は継続が重要ですが、あまりにも通院頻度が少ないと、保険会社に「治療の必要性がない」と判断されることがあります。
また、治療途中で急に通院頻度が少なくなると、改善したと解釈される場合があります。
適切な通院頻度を医師と相談し、維持するようにしましょう。
⑶ 症状の詳細な記録
毎日の症状の変化や、日常生活での支障などを細かく記録しておくことで、治療の必要性を具体的に説明できます。
これは、後に損害賠償の示談交渉が決裂してしまって裁判になった際、加害者側に治療期間の妥当性などを争われることもありますので、これに反論する場面でも有効です。
特に、主婦の方は、家事に支障があったことに対して家事従事者としての休業損害を請求できますが、これについても、どの時期にどのような家事にどの程度の支障があったかという点は重要になりますので、記録を残しておくと良いでしょう。
⑷ 自賠責へ被害者請求
被害者や医師が治療の必要性を訴えているにもかかわらず、保険会社が一方的に治療打切りを決定し、強行することもあります。
そのような場合には、一旦打切り後の治療費を立て替えた上で、自賠責保険に被害者請求をして打切り後の治療費を回収することも可能です。
ただ、自賠責保険は120万円が上限になりますので、枠が残っていない場合には自賠責保険には請求できません。
⑸ 弁護士への相談
保険会社との交渉が難航する場合や、専門知識が必要となる場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、あなたの代理人として保険会社と交渉し、適切な治療期間の治療費や慰謝料を獲得するためのサポートをしてくれます。
弁護士費用特約が利用できる場合には、弁護士費用の心配もありませんから、積極的に依頼することを検討しましょう。
法律事務所によっては無料相談を行っている事務所もあり、全国から電話やメールで相談できる事務所もあります。
3.慰謝料や治療費の減額リスクを回避する方法
むち打ちの慰謝料や治療費が不当に減額されるリスクを回避するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
⑴ 適切な医療機関での受診と継続的な治療
事故後すぐに医療機関を受診し、医師の指示に従って適切な治療を継続することが重要です。
自己判断で治療を中断したり、通院を怠ったりすると、治療の必要性が低いと判断され、早期に治療費を打ち切られたり、通院頻度が低いという理由で慰謝料が減額される可能性があります。
MRIの設備がない整形外科の場合、大きな病院を紹介されて検査を受ける場合もありますが、そのように新たな医療機関を受診する場合には、事前に保険会社に連絡しておく必要があります。
また、整形外科以外にも、接骨院や整骨院での治療費も検討してもらえることもありますが、医師の同意を得ておくことが大切です。
⑵ 診断書の正確な記載
診断書には、症状の内容、治療期間、今後の見込み、症状固定の目安などが正確に記載されていることが重要です。
特に、痛みや痺れなどの自覚症状は、できるだけ具体的に医師に伝え、診断書に反映してもらいましょう。
医師が作成するカルテも裁判になった場合には重要な証拠になります。
⑶ 後遺障害診断の検討
治療を続けても症状が改善しない場合、後遺障害に該当する可能性があります。
後遺障害と認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになり、受け取れる金額が大幅に増える可能性があります。
後遺障害の申請は、自賠責保険に対する請求となりますが、加害者側保険会社に任せて申請してもらう「事前認定」と被害者側で申請する「被害者請求」の方法があります。
基本的に、加害者側保険会社が後遺障害等級認定のために尽力してくれることは期待できませんので、被害者請求の方が望ましいですが、後遺障害の種類や等級は専門的な知識が必要なため、弁護士に相談しながら手続きを進めるのが賢明です。
⑷ 交通事故を得意とする弁護士への依頼
保険会社は営利企業であり、できるだけ支払う金額を抑えようとします。
弁護士は、法律の専門家としてあなたの正当な権利を主張し、過去の裁判例(判例)に基づいて適切な慰謝料額を算定しますので、被害者本人が交渉するよりも、保険会社との交渉を有利に進めることができます。
弁護士費用特約に加入している場合は、自己負担なく弁護士に依頼できるケースが多いです。
⑸ 示談交渉の知識を持つ
示談交渉は、一度成立すると原則としてやり直しができません。
提示された慰謝料の金額に納得できない場合は、安易に示談に応じず、内容を十分に検討し、ご自身のお怪我についていくらくらいが適切な金額か弁護士に相談するようにしましょう(例えば、むち打ちで治療期間が3ヶ月の場合、裁判所基準では慰謝料が53万円程度になります。)。
過失割合も慰謝料に影響する重要な要素ですので、安易に保険会社の提示を受け入れずに、妥当な過失割合か調べてみると良いでしょう。
4.治療・通院期間の延長を勝ち取るための交渉術
むち打ちの慰謝料は、治療・通院期間の長さに大きく影響されます。
そのため、適切な期間の治療と通院を継続することは、結果的に適正な慰謝料を獲得することにもつながります。
⑴ 医師との協力体制の構築
医師は治療の専門家であり、あなたの症状を最も理解している存在です。
現在の症状、治療の進捗、今後の治療方針について医師と密にコミュニケーションを取り、治療の必要性を客観的に示してもらいましょう。
診断の内容や検査の結果を確認することも大切です。
⑵ 症状の継続的な訴えと記録
痛みが残っているにもかかわらず、「もう大丈夫だろう」と我慢してしまうと、治療の必要性がないと判断されかねませんので注意が必要です。
医師や保険会社に対し、症状が続いていることを明確に伝え、日常生活における支障なども具体的に記録しておきましょう。
⑶ 通院の継続と頻度
むち打ちの治療は、継続的な通院が原則です。
適切な頻度で通院し、治療への意欲を示すことも重要です。
ただし、過剰な通院は不必要と判断される可能性もあるため、医師と相談して適切な頻度を保ちましょう。
加害者側の保険会社から通院や診察を促されるケースもあります。
⑷ 客観的証拠の収集
MRIやレントゲンなどの症状の原因の裏付けとなる画像診断の結果、神経学的所見、医師の診断書や意見書など、客観的な証拠は交渉において非常に強力な武器となります。
事故の状況を証明する書類として、交通事故証明書や実況見分調書も必要になる場合もあります。実況見分調書は、弁護士に依頼して取得してもらうと良いでしょう。
⑸ 現実的な治療期間の提示
保険会社から治療費打切りの打診があった場合、まだ治療を継続したいと伝えると、保険会社はあとどのくらい治療が必要か聞いてくることが多いですが、「あと1ヶ月続けたい」など具体的な期限を伝えると延長を認めてもらいやすい傾向があります。
もちろん、あとどのくらいで改善するかということは予想できない人も多いと思いますが、「治るまで治療したい」などと伝えてしまうと、保険会社としては対応しきれないと判断され、早期打切りの可能性が高まりますので、「もう1ヶ月様子を見て相談したい」などと現実的な期限を伝えて交渉するのもよいと思います。
⑹ 弁護士の活用
保険会社は、弁護士が介入することで、訴訟に発展するリスクを考慮し、より柔軟な対応をする傾向があります。
弁護士は、被害者のお怪我の症状や治療の実績に基づいて、保険会社基準より高額な裁判所基準に近いところで解決できるよう交渉を進めます。
また、難しい保険会社とのやり取りは弁護士に任せることができ、安心して治療に専念できるはずです。
弁護士費用特約がない場合でも、示談交渉で慰謝料を増額できて弁護士費用をカバーできる(弁護士費用をかけても増額メリットが大きい)可能性も高いですから、示談する前に一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
5.まとめ
むち打ちの治療と慰謝料に関する交渉は、専門知識が必要な場面が多く、精神的な負担も大きいものです。
一人で抱え込まず、信頼できる医療機関の医師や、交通事故に強い弁護士と連携しながら、ご自身の権利をしっかりと主張していきましょう。
適切な知識と準備があれば、適正な慰謝料を獲得できるはずです。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、全国から無料でご相談をお受けしておりますので、この記事をご覧になった方はぜひお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
肩腱板損傷で認定されやすい後遺障害等級~具体的な事例を踏まえて~
今回は、交通事故による肩腱板損傷の後遺障害について、裁判例を交えて解説いたします。
肩腱板損傷は、肩の腱板(棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋という4つの筋肉の腱)が傷ついたり、部分的に、あるいは完全に断裂したりする損傷を指します。
この損傷は、日常生活において様々な苦労をもたらすことがあります。具体的には、痛み、可動域制限、筋力低下や脱力感等です。
このように、腱板損傷は、日常生活において大きな苦労を伴う損傷といえます。
したがって、交通事故や労災事故等によって肩腱板損傷を負った場合、その苦労に見合った適正な賠償額が保険会社から支払われなければなりませんし、そのための知識をつけておくこと重要です。
1.過去の裁判例から学ぶ~後遺障害認定の傾向と注意点~
冒頭で触れたように、交通事故によって負った肩腱板損傷は、その後の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
適切な補償を受けるためには、後遺障害の認定が極めて重要ですが、その判断は非常に複雑です。
特に、事故前から存在した加齢による変性との区別が争点となるケースが多く、この争点について判断している裁判事例もあるところです。
後遺障害の等級は、症状の程度、治療経過、そして医学的所見等に基づいて総合的に判断されます。
肩腱板損傷の場合、主に以下の等級が検討の対象となります。
<8級6号>
肩関節の可動域が健側の10%程度以下に制限されている場合。
「関節の用を廃したもの」とされ、重度の機能障害が認められるケースに適用されます。
<10級10号>
肩関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されている場合。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とされ、比較的重度の機能障害が認められるケースに適用されます。
<12級6号>
肩関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されている場合。
「関節の機能に障害を残すもの」とされ、10級10号ほどではないものの、機能制限が存在する場合に該当します。
<12級13号>
痛みが「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められる場合。
他覚的所見(MRIなど)で痛みの原因となる腱板損傷が確認でき、その痛みが継続している場合に認定されます。
<14級9号>
痛みが「局部に神経症状を残すもの」と認められる場合。
他覚的所見(MRIなど)で痛みの原因となる腱板損傷が確認できないものの、その痛みが継続している場合に認定されます。
これらの等級認定をするにあたり、裁判所が重視しているポイントをいくつかピックアップいたします。
① 肩腱板損傷と交通事故との因果関係に関する立証
肩腱板損傷は、外傷以外にも加齢による変性や日常生活での負荷によっても発生し得るため、事故によって生じた損傷であることの証明が最も重要です。事故直後からの症状の一貫性、事故態様と受傷内容の整合性、そして事故以前に同様の症状がなかったことの証明が重要です。
② 医学的所見の存在
特にMRI画像は、腱板損傷の有無、断裂の程度、損傷の新鮮さ、筋萎縮や脂肪浸潤の有無などを客観的に示す上で決定的な証拠となります。医師による診断書だけでなく、画像所見そのものが後遺障害認定に大きく影響します。そのため、事故直後にMRI検査を行うことが重要です。
③ 治療経過の一貫性と適切性
これは特に、神経症状に関する後遺障害等級において関連しますが、受傷直後から症状固定に至るまでの治療内容、治療効果、そして症状固定の時期の適切性です。漫然とした治療や、症状の訴えに一貫性がない場合は、認定が難しくなることがあります。
2.腱板損傷の慰謝料相場は?
慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。以下にそれぞれの目安を紹介します。
・入通院慰謝料の目安
入院や通院日数・期間に応じて計算されます。
- 例えば、6か月通院した場合:約50万円〜116万円(自賠責基準・弁護士基準で異なります)
- 慰謝料の計算は治療の必要に応じて通院をした結果に基づくものではありますが、自賠責基準では通院回数が少ないと慰謝料が低く算定されるため、その点からも継続的な通院は大切です。
・後遺障害慰謝料の目安(等級別)
腱板損傷が後遺障害と認定されれば、慰謝料の金額は一気に上がります。
| 等級 | 慰謝料(弁護士基準) | 逸失利益の考慮 |
| 10級 | 約550万円 | 収入の27% |
| 12級 | 約290万円 | 収入の14% |
| 14級 | 約110万円 | 収入の5% |
3.慰謝料請求の流れと損害賠償の注意点
事故後は以下のような流れで進めるのが一般的です。
- 事故後すぐに通院:初診が遅れると事故との因果関係を疑われます。
- 診断書の取得:腱板損傷の診断が明記されたものが必要です。
- 症状固定の判断:ある程度(一般的には6ヶ月程度)治療を続けた後、医師により”これ以上の回復が見込めない”と判断された時点です。
- 後遺障害等級の申請:自賠責保険(損害保険料率算出機構)に申請します。
- 示談交渉:保険会社との間で慰謝料などを決定。専門家がいないと過少評価されるリスクが高いです。
4.裁判例に基づく後遺障害認定の可能性の評価~あなたのケースはどうなる?~
ご自身の肩腱板損傷が後遺障害として認定される可能性を評価する際には、裁判事例から見えてくる基準とご自身の状況を照らし合わせることが有効です。
裁判事例を踏まえ、後遺障害が認められる可能性が高いと考えられるケースの一般的な特徴は、次のとおりです。
① 受傷直後からの明確な症状
これは特に、神経症状に関する後遺障害等級において関連しますが、事故後、速やかに医療機関を受診し、その後も一貫して肩の痛みを訴えて症状が継続していること。
② 客観的な画像所見の存在
MRI画像において、明らかな腱板の断裂(完全断裂、部分断裂を問わず)や損傷が確認できる場合。新鮮な損傷を示す所見(出血、浮腫など)があれば、事故との因果関係がより強く裏付けられます。
③ 可動域制限の正確な測定
医師による正確な計測によって、肩関節の自動運動(自分で動かせる範囲)だけでなく、他動運動(他人に動かしてもらう範囲)にも明らかな制限が認められる場合。これにより、痛みのために動かせないだけではない器質的な問題があることが裏付けられます。
④ 主治医の積極的な意見
主治医が、後遺障害診断書に具体的に症状や他覚的所見を記載するとともに、事故との因果関係や症状の程度について医学的な見地から肯定的な意見を示している場合。
一方、後遺障害が認められる可能性が低いと考えられるケースの一般的な特徴は、次のとおりです。
① 事故から医療機関の受診までに時間が空いたケース
そもそも事故との因果関係が問題視されてしまうリスクが高いです。
② 事故前に肩に何らかの症状があった、または加齢による変性が顕著なケース
事故による新たな損傷か、既存の症状の悪化かを区別することが難しくなります。
③ 他覚的所見が確認できないケース
他覚的所見が無いため、可動域制限に関する後遺障害等級の認定は難しくなります。もっとも、神経症状に関する後遺障害等級14級9号については、他覚的所見が無くても認定される可能性が残ります。
④ 後遺障害診断書において、因果関係や症状の程度等が曖昧にされているケース
後遺障害診断書は、後遺障害等級を判断するにあたり非常に重要な書類であるため、その記載内容が不十分であると不利に影響します。
ご自身の状況がこれらのいずれに該当するかを確認し、特に「事故との因果関係の証明」と「客観的な医学的所見の提示」に力を入れることが、後遺障害認定の可能性を高める上で重要です。
5.事例紹介とその解説~具体的な裁判例から学ぶ~
それでは具体的な裁判事例を通して、肩腱板損傷の後遺障害認定がどのように判断されているかを見てみましょう。
これらの事例は、実際の裁判所での判断基準を理解する上で非常に参考になります。
【事例1:可動域制限の後遺障害を主張したものの14級9号が認定されたケース】
<事案概要>
50代男性(原告)がタクシーを運転して交差点を右折しようとしたところ、対向車線を直進してきた相手車両と衝突したことにより交通事故が発生しました。原告は、右肩腱板損傷に基づく可動域制限を主張し、その後遺障害等級に該当することを主張しました。
<裁判所の判断(東京地裁平成30年11月20日判決)>
「右肩甲部から右上肢の疼痛に関しては、①原告は、本件事故後から右肩関節部の疼痛、圧痛、運動時痛を一貫して訴えており、本事故以前にそのような痛みが生じていたものとはうかがわれないこと、②平成24年7月10日に実施された右肩のMRI検査の結果、右肩関節棘上筋腱に脂肪抑制T2WIにて高信号域が見られ、損傷の所見があるものとされ、右肩関節腱板損傷との所見が示されており、丁山四郎医師の意見書や戊田五郎医師による鑑定報告書においても、右肩棘上筋の損傷や関節唇の損傷がみられるとの所見が示されていること、③本件事故態様や衝撃の程度等からすると、原告には、本件事故により、右肩に腱板損傷が生じ、右肩の疼痛が生じたものと推認される。もっとも、右肩の可動域は、自動値については制限がみられるものの、他動値では大きな制限はみられず、右肩関節の機能障害が生じたものとまでは認めるに足りない。」、「原告には症状固定後も、①右肩甲部から右上肢の疼痛・・が残存したものと認められるところ、①については後遺障害等級14級9号・・に該当・・したものと認めるのが相当である。」
<解説>
この事例から、自動運動が制限されていても、他動運動が制限されていなければ、可動域制限に関する後遺障害等級が認定されることは難しいことが分かります。
【事例2:被告からの反論を退けて12級6号が認定されたケース】
<事案概要>
50代男性(原告)が自動二輪車に乗車して直進していたところ、対向車線から転回してきた相手車両に衝突されたことにより交通事故が発生しました。これにより、原告は、左肩腱板損傷等の傷害を負い、自賠責保険会社から、左肩関節機能障害について12級6号の認定を受けていました。これに対し、被告側は、左肩関節の可動域制限と本件事故との因果関係について反論をしていました。
<裁判所の判断(神戸地裁令和元年6月26日判決)>
「原告はE自賠責損害調査事務所によって後遺障害等級併合12級と認定されているところ、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、原告には、本件事故によって受傷した左肩腱板損傷後の左肩関節について、健側(右肩関節)の可動域と比較して3/4以下の可動域制限が残存するという機能障害とともに、右足関節外果部に瘢痕があり・・原告には、後遺障害等級12級6号及び14級5号にそれぞれ該当する後遺障害が残存し、これを併合12級と評価するのが相当である。」、「この点、被告らは、原告の左肩関節の可動域制限と本件事故との因果関係に疑問を呈するとともに、その実質は疼痛という神経症状の範疇に止まる旨主張するところ、なるほど、事故から約7ヶ月が経過した平成30年2月26日のC整形外科の診療録において初めて左肩可動域制限に関する記載があると認められ、それまでのB病院の診療録では可動域制限なしとされ、他に上記日時までは可動域制限に関する記載がC整形外科の診療録にも見当たらず、また原告は事故後2ヶ月余が経過した平成29年9月ころに左肩の痛みがやや軽減し、又はほぼない旨医師に告げていることが認められる。」、「もっとも、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件事故から2日後の平成29年7月13日にC整形外科においてMRI検査を受けた結果、左肩、肩甲下筋腱に損傷があると診断されており、そのころ相当程度の疼痛を訴えていたこと、腱板損傷による疼痛等のため、原告は左肩をできるだけ動かさず、安静にする必要があったこと、医学的知見として、①腱板損傷が生じると時間の経過とともに断裂は拡大し、筋の萎縮が進行する、②関節可動域の制限には発生進行に関節の不動が影響するものであり、関節の不動によって拘縮が発生し、不動期間が長期化するほど拘縮が進行する、とされていること等の事実が認められ、これらの事実に徴すると、原告には、損害保険料率算出機構が認定したとおりの左肩関節の機能障害が残存し、その程度は後遺障害等級12級6号に該当するとの認定は覆らない。」
<解説>
この事例は、診療録に可動域制限なしと記載されていても、左肩関節の機能障害が残存していると評価された点が重要です。このように、裁判所は、様々な事情を総合考慮した上で、可動域制限の後遺障害等級について判断していることが分かります。
6.まとめ
このように、肩腱板損傷の後遺障害等級認定は、様々な事情を総合考慮した上で審査が行われます。
そのため、肩腱板損傷を負った被害者としては、後遺障害等級認定に有利な事情を主張立証しなければなりません。
一般の方が、これらの主張立証をすることは難しいと思われるため、適切な主張立証をされたい場合には、交通事故を専門とする弁護士に相談するべきであるといえます。
弁護士法人優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。
全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事が、肩腱板損傷でお困りの被害者の皆様の解決に少しでもお役に立てれば幸いです。
投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
交通事故による肩腱板損傷でお悩みの方へ
突然の交通事故は、私たちの日常を奪い、心身に大きな負担を強いることがあります。
特に、肩関節を構成する重要な腱の集まりである腱板の損傷は、その後の生活や仕事に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
上肢の機能障害にもつながる肩腱板損傷は、痛みだけでなく、肩の可動域制限を引き起こし、時に後遺障害を残すことも少なくありません。
もしあなたが交通事故で腱板損傷を負い、今後の治療や保険会社との交渉、そして適切な慰謝料の獲得について不安を感じているのであれば、この記事が解決への糸口になると思います。
弁護士法人優誠法律事務所は、交通事故の専門知識と豊富な解決事例に基づき、被害者の方々を全力でサポートしています。
この記事では、交通事故における肩腱板損傷の基礎知識から、後遺障害認定の必要性、保険会社との交渉のポイント、そして弁護士に依頼するメリットまでを詳細に解説します。
1.交通事故における肩腱板損傷とは
交通事故によって肩に強い衝撃が加わると、肩腱板を損傷する可能性があります。
ここでは、肩腱板の構造と機能、主な損傷の原因、そして交通事故における症状と影響について解説します。
(1)肩腱板の構造と機能
肩腱板とは、肩関節を構成する4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)の腱が集合したものです。
これらの腱は、上腕骨頭(腕の骨の先端)を肩甲骨の関節窩に安定させ、腕を上げたり、回したりする際の滑らかな動きを支える重要な役割を担っています。
腱板が正常に機能することで、私たちは日常生活における様々な動作をスムーズに行うことができるのです。
(2)主な損傷の原因
肩腱板損傷の主な原因は、加齢による腱の変性、使いすぎ(オーバーユース)、転倒やスポーツなどによる急激な外力などが挙げられます。
交通事故においては、衝突時の衝撃や、体を支えようとした際の無理な力が肩関節に加わることで、腱板が断裂したり、部分的に損傷したりすることがあります。
特に、直接的な打撃だけでなく、予測できない体勢での衝撃は、腱板に大きな負担を与える可能性があります。
(3)交通事故での症状と影響
交通事故による肩腱板損傷の症状は、損傷の程度によって様々です。
軽度の場合には、肩の痛みやわずかな可動域制限が見られる程度ですが、重度の場合には、激しい痛みで腕を上げることが困難になったり、夜間に痛みが強くなったりすることがあります。
具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- 肩の痛み(安静時痛、運動時痛、夜間痛)
- 腕を上げる際の痛みやひっかかり感
- 肩関節の可動域制限(特に腕を上げる、外に開く、内側に回す動作が困難になる)
- 肩の力が入りにくい、脱力感
- 特定の動作での肩の不安定感
これらの症状は、日常生活における様々な動作、例えば着替え、入浴、食事、車の運転などを困難にするだけでなく、睡眠障害を引き起こし、精神的な負担となることもあります。
また、受傷当日には症状が軽度でも、数日経過してから悪化することもあるため、注意が必要です。
鎖骨の骨折など、肩腱板の損傷に加えて骨折を伴うケースもあります。
2.交通事故における証明の重要性
交通事故によって腱板損傷を負った被害者が適切な損害賠償を獲得するためには、その怪我が交通事故によって生じたものであり、かつ後遺障害が残っていることを医学的に証明することが極めて重要です。
ここでは、医師の意見書の役割、証明に必要な書類、そして立証に向けた準備について解説します。
(1)医師の意見書の役割
医師が作成する後遺障害診断書や意見書は、後遺障害認定において非常に重要な役割を果たします。
これらは、被害者の症状が交通事故に起因するものであること、治療の経過、症状固定時の状態、そして将来にわたって残存する後遺症の程度や内容を医学的な見地から客観的に記載するものです。
特に、腱板損傷による可動域制限や痛みが後遺障害として認められるためには、医師が作成する詳細な診断書や意見書が不可欠となります。
弁護士は、医師との連携を通じて、後遺障害認定に必要な情報を的確に診断書や意見書に反映させられるようサポートします。
(2)証明に必要な書類
後遺障害認定の申請や損害賠償請求を行う際には、以下のような書類が必要または有効となります。
これらの書類は、被害者の怪我の状況、治療の経過、そして後遺症の存在を客観的に証明する根拠となります。
- 交通事故証明書:事故の事実を公的に証明する書類です。
- 診断書:初診時からの診断、怪我の部位や内容、症状などが記載されます。
- 診療報酬明細書:治療費の詳細が記載された書類です。
- レントゲン画像、MRI画像、CT画像など:腱板損傷の有無や程度を客観的に示す画像検査のデータです。特にMRIは腱板の損傷状況を詳細に評価する上で重要です。
- 各種検査結果:関節の可動域測定結果など、機能障害の程度を示すデータです。
- 後遺障害診断書:症状固定時に医師が作成する書類で、後遺症の内容や程度が詳細に記載されます。後遺障害認定の申請に不可欠な書類です。
- 意見書:医師が作成する、症状や治療に関する詳細な意見が記載された書類です。
- 診療録:入院していた場合に、身体の状況や介護の必要性などが記載されます。
これ以外の書類も状況に応じて必要になる場合がありますが、被害者自身で全てを収集するには負担が大きいため、弁護士に依頼してスムーズに収集できるようサポートしてもらうことをお勧めします。
(3)立証に向けた準備
後遺障害の立証に向けた準備は、治療中から始まります。
- 早期の受診と継続的な治療:事故後、肩に痛みや違和感を感じたら、速やかに整形外科を受診しましょう。そして、医師の指示に従い、中断することなく治療を継続することが重要です。事故発生から2週間以上経過した段階での受診や、治療中1か月以上の治療の中断は、交通事故と怪我の因果関係を否定される可能性があるため注意が必要です。
- 医師との密な連携:症状の変化や治療の経過について、医師に詳細に伝え、診断書や意見書に正確に反映してもらうよう依頼しましょう。
- 症状の記録:日々の痛みの程度、可動域制限の状況、日常生活での支障などをメモに残しておくことが有効です。これは、後遺障害認定の際の参考資料となり得ます。
- 専門医への紹介:必要に応じて、腱板損傷の専門医や高次医療機関への紹介を受け、より専門的な診断や治療を受けることも検討しましょう。
これらの準備が十分になされていないと、後遺障害が認められなかったり、適切な等級が認定されなかったりする可能性があります。
3.保険会社とのやり取り
交通事故の被害者にとって、保険会社とのやり取りは精神的な負担が大きく、専門知識が必要となる場面が多々あります。
ここでは、保険会社の対応と注意点、交渉のポイント、そして保険金請求の流れについて解説します。
(1)保険会社の対応と注意点
交通事故の後、加害者側の保険会社から連絡が入り、治療費の支払いや休業損害・慰謝料に関する提示が行われます。
しかし、保険会社は営利企業であり、自社の基準で損害額を提示してくることがほとんどです。
この提示額は、弁護士が交渉して獲得できる金額よりも低い場合が多く、特に示談交渉の最終段階で提示される示談金は、被害者にとって不利な内容である可能性があります。
注意点としては、以下が挙げられます。
- 安易に署名・捺印をしない:保険会社から送られてくる書類には、安易に署名・捺印をしないように注意しましょう。
- 安易に症状固定の打診に応じない:保険会社は、治療期間が長引くと、治療費の支払いを打ち切るために「症状固定」を打診してくることがあります。しかし、症状固定の判断は、医師が行うべきものであり、保険会社の都合で決定されるものではありません。
- 安易に示談を了承しない:保険会社からの初期の示談提案は、自賠責保険の基準や任意保険の独自基準(いわゆる相場)に基づくことが多く、裁判基準(弁護士基準)と比較して大幅に低い金額である可能性が高いです。
(2)交渉のポイント
保険会社との交渉を有利に進めるためには、慰謝料の増額も視野に入れた戦略が重要です。以下のポイントを押さえることが重要です。
- 適正な損害額の算定:治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など、発生した損害の総額を正確に算定することが不可欠です。特に後遺障害が残った場合には、後遺障害等級に応じた逸失利益の計算が重要となります。
- 後遺障害等級の認定:肩腱板損傷の後遺障害は、肩関節の可動域制限などによって10級10号などの等級が認定される可能性があり、12級6号が認定される事例もあります。適切な等級認定を受けることが、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益の獲得に直結します。
- 裁判基準(弁護士基準)の適用:保険会社が提示する金額は、自賠責保険基準や任意保険基準であることがほとんどです。しかし、弁護士が介入することで、過去の裁判例に基づいた最も高額な基準である裁判基準(弁護士基準)で交渉を進めることが可能になります。
- 専門家による交渉:弁護士は、法的な知識と交渉経験を活かし、保険会社の主張に対して的確に反論し、被害者の権利を守るために粘り強く交渉します。
(3)保険金請求の流れ
交通事故の損害賠償請求は、一般的に以下のような流れで進行します。
- 事故発生・警察への連絡:事故が発生したら、速やかに警察に連絡し、事故状況の確認を行ってもらいます。
- 病院での診察・治療:痛みや違和感がなくても、必ず病院で診察を受けましょう。腱板損傷などの怪我は、後になって症状が現れることもあります。診断書は必ず保管してください。
- 保険会社への連絡:自身の保険会社と相手方の保険会社に事故が発生したことを連絡します。
- 治療の継続:医師の指示に従い、症状が固定するまで治療を継続します。症状や状況に応じて、整骨院等での治療を検討できる場合もあります。
- 症状固定・後遺障害診断:医師がこれ以上の治療による改善が見込めないと判断した時点で「症状固定」となります。この時点で後遺症が残っていれば、後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害認定の申請を行います。
- 後遺障害等級の認定:損害保険料率算出機構(自賠責保険調査事務所)が提出された書類に基づき、後遺障害等級の審査を行います。等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能になります。
- 示談交渉:後遺障害等級が認定された後、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などの損害賠償額について、保険会社と示談交渉を行います。
- 示談成立・賠償金支払い:示談が成立すれば、示談書を締結し、保険会社から賠償金が支払われます。
この流れの中で、弁護士は被害者の立場に立ち、各段階で適切なアドバイスとサポートを提供します。
4.交通事故後の弁護士の役割
交通事故による肩腱板損傷は、被害者に大きな精神的・経済的な負担を与えます。
弁護士は、被害者の権利を守り、適切な賠償を得るために様々なサポートを行います。
ここでは、弁護士の選び方と相談方法、無料相談の活用方法、そして弁護士に依頼するメリットについて解説します。
(1)弁護士の選び方と相談方法
交通事故問題を専門とする弁護士を選ぶことが重要です。
当弁護士法人のように、交通事故の解決実績が豊富で、専門知識を持つ事務所を選ぶことが重要です。
ホームページや紹介などを通じて、弁護士の専門性や実績を確認しましょう。
また、実際に相談してみて、親身になって話を聞いてくれるか、説明が丁寧で分かりやすいかなども判断材料となります。
弁護士への相談方法としては、電話、メール、オンライン相談、面談などがあります。
多くの法律事務所では、初回相談を無料で行っているため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
相談の際には、事故の状況、怪我の状況、治療の経過、保険会社とのやり取りなど、できるだけ詳しく伝えることが大切です。
(2)無料相談の活用方法
無料相談は、弁護士に依頼するかどうかを検討する上で非常に有効な手段です。
無料相談を最大限に活用するために、以下の点に注意しましょう。
- 事前に相談内容を整理しておく:聞きたいことや伝えたいことをメモにまとめておくと、限られた時間を有効に使えます。
- 関係書類を持参する:事故証明書、診断書、保険会社の提示書など、関連する書類を持参すると、より具体的なアドバイスを受けることができます。
- 弁護士の経験や実績を確認する:交通事故事件の解決経験や、特に肩腱板損傷のような事例の経験があるかなどを質問してみましょう。
- 費用体系について確認する:弁護士に依頼した場合の費用(着手金、報酬金など)やその理由について、明確に説明を受けるようにしましょう。
複数の弁護士に相談してみることも、自分に合った弁護士を見つけるためには有効な方法です。
(3)弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害者が弁護士に依頼することには、以下のような多くのメリットがあります。
- 適正な損害賠償額の獲得:弁護士は、法的な知識や過去の判例・裁判例に基づいて、適正な損害賠償額を算定し、保険会社との交渉を有利に進めます。
- 煩雑な手続きからの解放:示談交渉や後遺障害認定の手続きなど、複雑で時間のかかる作業を弁護士に任せることができます。これにより、被害者は治療に専念することが可能となります。
- 精神的な負担の軽減:保険会社とのやり取りや、今後の見通しなどについて弁護士に相談することで、精神的な不安や負担を軽減することができます。
- 裁判になった場合の対応:示談交渉が決裂し、裁判になった場合でも、弁護士が代理人として対応します。
交通事故による肩腱板損傷は、症状が重い場合、後遺障害として残る可能性も十分に考えられ、損害賠償額も高額になるケースが多くなります。
弁護士費用が気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士費用特約に加入していれば、費用は保険で賄われることがほとんどです。
特約がない場合でも、着手金無料や成功報酬型の料金体系を採用している事務所もありますので、まずは無料相談をご利用いただき、費用について確認してみましょう。
交通事故による肩腱板損傷でお困りの方は、一人で悩まず、まずは当弁護士法人にご相談ください。
経験豊富な弁護士が、あなたにとってより良い問題解決となるよう尽力いたします。
投稿者プロフィール

これまで、交通事故・離婚・相続・労働などの民事事件を数多く手がけてきました。今までの経験をご紹介しつつ、皆様がお困りになることが多い法律問題について、少しでも分かりやすくお伝えしていきます。
■経歴
2009年03月 法政大学法学部法律学科 卒業
2011年03月 中央大学法科大学院 修了
2011年09月 司法試験合格
2012年12月 最高裁判所司法研修所(千葉地方裁判所所属) 修了
2012年12月 ベリーベスト法律事務所 入所
2020年06月 独立して都内に事務所を開設
2021年3月 優誠法律事務所設立
2025年04月 他事務所への出向を経て優誠法律事務所に復帰
■著書
こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
交通事故で肩の腱板損傷に…慰謝料や後遺障害認定のポイントを弁護士が解説!
今回のテーマは、交通事故で肩腱板損傷を負ってしまった場合の損害賠償についてです。
交通事故は、予期せぬ瞬間に私たちの日常生活を大きく変えてしまう可能性があります。交通事故による負傷の中でも、肩関節周辺の痛みや機能障害を引き起こす「肩腱板損傷」は、その後の生活に大きな影響を与えることがあります。
今回は、交通事故による肩腱板損傷について、その基礎知識から、診断・治療、後遺障害の認定、損害論(慰謝料や逸失利益)、そして弁護士の役割までを詳しく解説します。
【関連記事】
弁護士に依頼することで示談金が増額した事例~右肩腱板損傷・異議申立て・後遺障害12級13号~
1.交通事故における肩腱板損傷とは
交通事故によって肩に強い衝撃が加わると、肩腱板を損傷する可能性があります。
ここでは、まず肩腱板の構造と機能、主な損傷の原因、そして交通事故における症状と影響について解説します。
(1)肩腱板の構造と機能
肩腱板とは、肩関節を構成する4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、肩甲下筋及び小円筋)の腱が集まったものです。
「腱」とは、筋肉の先端部で繊維が細くなって線維化して骨に付着している部分をいい、つまり筋肉と骨とを繋いでいる組織であると考えてください。
これらの腱は、上腕骨頭(腕の骨の先端)を肩甲骨の関節窩(関節を構成する凹状のくぼみ部分)に安定させ、腕を上げたり、回したりする際の滑らかな動きを支える重要な役割を担っています。
腱板が正常に機能することで、私たちは日常生活における様々な動作をスムーズに行うことができます。
(2)主な損傷の原因
肩腱板損傷の主な原因は、加齢による腱の変性、使いすぎ(オーバーユース)、転倒やスポーツなどによる急激な外力などが挙げられます。
交通事故においては、衝突時の衝撃や、体を支えようとした際の無理な力が肩関節に加わることで、腱板が断裂したり、部分的に損傷したりすることがあります。
特に、直接的な打撃だけでなく、予測できない体勢での衝撃は、腱板に大きな負担を与える可能性があります。
ただし、一般的にはいわゆるシートベルト損傷によって、靱帯や腱が切れるということは珍しいとされており、二輪車や自転車などで転倒しているかどうかなどの受傷機転が明確に存在することが重要です。
(3)交通事故での症状と影響
交通事故による肩腱板損傷の症状は、損傷の程度によって様々です。
軽度の場合には、肩の痛みやわずかな可動域制限が見られる程度ですが、重度の場合には、激しい痛みで腕を上げることが困難になったり、夜間に痛みが強くなったりすることがあります。
具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- 肩の痛み(安静時痛、運動時痛、夜間痛)
- 腕を上げる際の痛みやひっかかり感
- 肩関節の可動域制限(特に腕を上げる、外に開く、内側に回す動作が困難になる)
- 肩の力が入りにくい、脱力感
- 特定の動作での肩の不安定感
これらの症状は、日常生活における様々な動作、例えば着替え、入浴、食事、車の運転などを困難にするだけでなく、時には睡眠障害を引き起こし、精神的な負担となることもあります。
2.腱板損傷の診断と治療
交通事故による肩の痛みを感じたら、早期に整形外科を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。
ここでは、腱板損傷の診断方法と検査内容、治療法の選択肢、そして肩関節の可動域制限について解説します。
(1)診断方法と検査内容
腱板損傷の診断のためには、一般的にMRIによる画像検査が必要です。
なぜなら、いわゆるレントゲンやCTなどのX線画像では、骨の状態しかわからないため、骨折を伴わない場合にはそれ以上の説明ができません。
靱帯や腱の断裂や損傷については、MRIでなければ映らないため、靱帯や腱の断裂や損傷が疑われる場合には一般的にMRIによる画像検査が行われます。
なお、肩腱板に損傷や炎症がある場合には、MRIのT2強調画像で損傷や炎症部位が白く(高信号で)映ります。
MRI検査結果等を総合的に判断し、腱板損傷の有無、程度、損傷部位などが特定されます。
ただ、事故から時間が経過してしまうと、事故との因果関係を疑われることがありますので、早期にMRI検査を行う必要があります。
(2)治療法の選択肢
腱板損傷の治療法は、損傷の程度や患者さんの年齢、活動レベルなどによって異なります。
主な治療法としては、保存療法と手術療法があります。
【保存療法】
手術を行わずに、自然治癒力を促したり、症状の緩和を図る治療法です。
- 安静: 損傷した腱板の負担を軽減するため、肩関節を安静に保ちます。
- 薬物療法: 痛みや炎症を抑えるために、鎮痛薬や湿布、内服薬などが用いられます。
- 注射療法: 痛みが強い場合には、局所麻酔薬やステロイド薬を肩関節周囲に注射することがあります。
- リハビリテーション: 痛みが落ち着いてきたら、肩関節の可動域を改善し、周囲の筋肉を強化するための運動療法を行います。理学療法士の指導のもと、段階的に運動を進めていくことが重要です。
【手術療法】
保存療法で十分な改善が見られない場合や、腱板の完全断裂など重度の損傷の場合には、手術が検討されます。手術の方法は、関節鏡視下手術(内視鏡を用いた手術)や、より開放的な手術などがあります。手術の目的は、断裂した腱板を修復し、肩関節の機能を回復させることです。術後も、リハビリテーションを継続して行うことが、良好な回復のためには不可欠です。
(3)肩関節の可動域制限について
腱は筋肉の収縮を骨に伝える役割がありますので、腱に損傷が生じると、関節の可動域に制限が生じることがあります。
なお、先に述べたとおり肩腱板は、肩関節を構成する4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、肩甲下筋及び小円筋)の腱が集まったものですが、交通事故による損傷においては、そのほとんどが棘上筋腱損傷であると言われています。
腱板損傷によって生じる肩関節の可動域制限は、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
特に、腕を上げる、回すといった動作が困難になるため、着替えや洗髪、高い場所の物を取るなどの動作に苦労することがあるでしょう。
3.肩腱板損傷の後遺障害とその認定
交通事故による肩腱板損傷は、適切な治療を行っても、後遺障害が残ってしまうことがあります。
ここでは、後遺障害認定の必要性、後遺障害等級の説明、そして認定を受けるための条件について解説します。
(1)後遺障害認定の必要性
交通事故による怪我で後遺障害が残った場合、加害者の加入する自賠責保険に対して請求を行うことにより、その程度に応じて後遺障害等級が認定されることがあります。
後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償を請求することができます。
肩腱板損傷の場合、肩関節の機能障害の程度によって後遺障害等級が認定される可能性があります。
適切な賠償を受けるためには、後遺障害認定の手続きを行うことが重要です。
(2)後遺障害等級の説明
肩関節の機能障害に関する後遺障害等級は、主に以下の3つに分類されます。
【第8級6号】 肩関節の用を廃したもの
「肩関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 関節が強直したもの
「関節が強直した」とは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものとして、関節可動域が原則として健側(怪我をしていない側)の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものを言います。また、肩関節においては、肩甲上腕関節が癒合し骨製強直していることがX線写真により確認できるものを含みます。
- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
【第10級10号】 肩関節の機能に著しい障害を残すもの
「肩関節の機能に著しい障害を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 肩関節の可動域が健側の可動域確度の1/2以下に制限されているもの
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換し、上記第8級6号に該当しないもの
【第12級6号】肩関節の機能に障害を残すもの
・肩関節の可動域が健側の3/4以下に制限された場合をいいます。
これらの等級は、医師の診断書や関節の可動域測定の結果などに基づいて自賠責保険(損害保険料率算出機構の自賠責保険調査事務所)において判断されます。
(3)認定を受けるための条件
交通事故による肩腱板損傷で後遺障害の認定を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 交通事故と肩腱板損傷の因果関係が医学的に認められること: 事故の状況や受傷時の状態、その後の経過などから、肩腱板損傷が交通事故によって生じたものであると医学的に説明できる必要があります。
- 適切な治療を継続して行ったにもかかわらず、症状が改善せず、後遺症が残存していること: 漫然と治療を受けるのではなく、医師の指示に従い、必要な検査やリハビリテーションを継続して行うことが重要です。
- 残存した症状が、将来においても回復が見込めないと医学的に判断されること: 症状が一時的なものではなく、永続的なものであると医師が判断する必要があります。
- 後遺症の内容が、自賠責保険の後遺障害等級に該当するものであること: 提出された医学的な資料に基づいて、損害保険料率算出機構の自賠責保険調査事務所が各等級に該当するか否かを認定します。
後遺障害の認定を受けるためには、適切な診断書や検査結果などの医学的証拠を揃えることが重要です。
弁護士に相談することで、これらの手続きをスムーズに進めるためのアドバイスやサポートを受けることができます。
4.肩腱板損傷による後遺障害の損害賠償(慰謝料と逸失利益)
交通事故による肩腱板損傷で後遺障害が残った場合、慰謝料や逸失利益の請求を行うことができます。
ここでは、慰謝料の種類と実績、逸失利益とは何か、そして示談金の交渉と流れについて解説します。
(1)慰謝料の種類
交通事故における慰謝料には、主に以下の2種類があります。
- 入通院慰謝料: 怪我の治療のために、入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入院期間や通院期間、治療内容などに基づいて算出されます。
- 後遺障害慰謝料: 後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に支払われる慰謝料です。後遺障害等級に応じて金額が定められており、等級が高いほど慰謝料の金額も高くなります。
慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、一般的に弁護士基準が最も高額になる傾向があります。
過去の裁判例などを参考に、個々の事案に応じた適切な慰謝料額を算定することが重要です。
なお、上記肩関節の機能障害に関する各後遺障害等級に該当する場合の弁護士基準(裁判基準)の一例を記すと以下のとおりです(地域や個別の事情によって異なる場合がありますのでご留意ください)。
- 第8級6号: 830万円
- 第10級10号: 550万円
- 第12級6号: 290万円
(2)逸失利益とは何か
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、将来にわたって得られるはずだった収入が減少してしまう損害のことです。
肩腱板損傷による機能障害が、仕事に支障をきたし、収入の減少につながるとして逸失利益を請求することができます。
逸失利益の計算は、被害者の年齢、職業、事故前の収入、後遺障害等級などを考慮して行われます。
具体的には、「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式を用いて算出されることが一般的です。
労働能力喪失率や労働能力喪失期間は、後遺障害等級に応じて定められています。
なお、こちらも一概には言えませんが、労働能力喪失期間は、始期を症状固定日として、その終期は原則として67歳として計算するのが一般的です。
また、上記肩関節の機能障害に関する各後遺障害等級に該当する場合の労働能力喪失率は一般的には以下の基準によって計算されます。
- 第8級6号: 45%
- 第10級10号: 27%
- 第12級6号: 14%
(3)示談金の交渉と流れ
交通事故による損害賠償金(慰謝料や逸失利益など)の支払いは、加害者側の保険会社との示談交渉によって決まることが一般的です。
保険会社は、自社の基準に基づいて損害額を提示してきますが、その金額が必ずしも適正とは限りません。
なお、弁護士が対応する場合の示談交渉の流れは以下のようになります。
- 損害額の算定: 治療費、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など、発生した損害の総額を正確に算定します。
- 示談案の提示: 算定した損害額に基づいて、加害者側の保険会社に示談案を提示します。
- 交渉: 保険会社から提示された示談案(対案)に対して、増額交渉を行います。お互いの主張をぶつけ合い、合意点を探ります。
- 合意: 双方の合意が得られたら、示談書を作成し、示談が成立となります。
- 賠償金の支払い: 示談書に基づき、加害者側の保険会社から被害者へ賠償金が支払われます。
示談交渉は、法的な知識や交渉力が必要となるため、被害者自身で行うには負担が大きい場合があります。
弁護士に依頼することで、適切な損害額を算定し、有利な条件で示談を進めることが期待できます。
(4)解決の実績
ここでひとつ、解決事例をご紹介します。
【事案】
東京都内在住のAさん(40歳・会社員・年収約800万円)は、バイクで優先道路を走行中、路外から一時停止をせずに侵入してきた自動車と衝突しました。この事故により、Aさんは鎖骨骨折、肩腱板断裂などの重傷を負い、緊急搬送され手術を受けました。その後、約1年にわたりリハビリテーションを中心とした治療を継続されました。
【相談・依頼の経緯】
事故後、相手方保険会社から治療費や休業損害の支払いがありましたが、今後の後遺症や慰謝料について不安を感じたAさんは、当事務所の無料相談をご利用になりました。弁護士がAさんの状況を詳しくお伺いし、後遺障害等級認定の手続きや、適正な損害賠償額の請求についてサポートできることをご説明したところ、Aさんは正式に当事務所に依頼されました。
【弁護士の活動】
①後遺障害等級認定のサポート
Aさんの肩関節の可動域制限は著しく、日常生活や仕事にも支障をきたす可能性がありました。そこで、当事務所の弁護士は、Aさんの主治医と連携を取りながら、後遺障害等級認定に必要な医学的な資料を収集し、適切な等級認定を受けられるよう尽力しました。その結果、Aさんは後遺障害等級10級10号の認定を受けることができました。
②損害賠償請求と示談交渉
後遺障害等級が認定されたことを受け、当事務所は相手方保険会社に対し、以下の項目について損害賠償請求を行いました。※ただし、Aさんにも過失がありましたので、請求できたのは以下の損害に対する相手方の過失割合分となります。
- 治療費: 約200万円
- 交通費: 約20万円
- 入通院慰謝料: 約1年間の治療期間に対する慰謝料
- 後遺障害慰謝料: 後遺障害等級10級相当の慰謝料550万円
- 休業損害: 約3ヶ月の休業期間に対する損害
- 逸失利益: 後遺障害による将来の収入減少に対する損害(約3969万円)
相手方保険会社は当初、自社の基準に基づいた低い金額を提示してきました。しかし、当事務所の弁護士は裁判基準(弁護士基準)に基づいた適正な損害賠償額を算定し、粘り強く交渉を行いました。
特に、後遺障害慰謝料と逸失利益については、過去の裁判例やAさんの年齢、年収などを考慮し、詳細な主張を展開しました。
肩関節の機能障害がAさんの仕事に与える影響についても具体的に説明し、将来の収入減少の可能性を強く訴えました。
③最終的な示談成立
数回にわたる交渉の結果、最終的に相手方保険会社は当事務所の主張をほぼ全面的に認め、合計で約3000万円(自賠責保険金などの既払い金を除く)の示談金が支払われることで合意に至りました。
Aさんは、当初保険会社から説明を受けていた金額よりも大幅に増額された賠償金を受け取ることができ、今後の生活への不安を大きく軽減することができました。
5.交通事故被害者のための弁護士の役割
交通事故による肩腱板損傷は、被害者に大きな精神的・経済的負担を与えます。
弁護士は、このような被害者の被害に対して適切な賠償を得るために様々なサポートを行います。
ここでは、弁護士の選び方と相談方法、無料相談の活用方法、そして弁護士に依頼するメリットについて解説します。
(1)弁護士の選び方と相談方法
交通事故問題を専門とする弁護士を選ぶことが重要です。
ホームページや紹介などを通じて、交通事故の解決実績や専門知識を確認しましょう。
また、実際に相談してみて、親身になって話を聞いてくれるか、説明が丁寧で分かりやすいかなども判断材料となります。
弁護士への相談方法としては、電話、メール、オンライン相談、面談などがあります。
多くの法律事務所では、初回相談を無料で行っているため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
相談の際には、事故の状況、怪我の状況、治療の経過、保険会社とのやり取りなど、できるだけ詳しく伝えることが大切です。
(2)無料相談の活用方法
無料相談は、弁護士に依頼するかどうかを検討する上で非常に有効な手段です。
無料相談を最大限に活用するために、以下の点に注意しましょう。
- 事前に相談内容を整理しておく: 聞きたいことや伝えたいことをメモにまとめておくと、限られた時間を有効に使えます。
- 関係書類を持参する: 事故証明書、診断書、保険会社の提示書など、関連する書類を持参すると、より具体的なアドバイスを受けることができます。
- 弁護士の経験や実績を確認する: 交通事故事件の解決経験や、特に肩腱板損傷のような事例の経験があるかなどを質問してみましょう。
- 費用体系について確認する: 弁護士に依頼した場合の費用(着手金、報酬金など)について、明確に説明を受けるようにしましょう。
(3)弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害者が弁護士に依頼することには、以下のような多くのメリットがあります。
- 適正な損害賠償額の獲得: 弁護士は、法的な知識や過去の判例に基づいて、適正な損害賠償額を算定し、保険会社との交渉を有利に進めます。
- 煩雑な手続きからの解放: 示談交渉や後遺障害認定の手続きなど、複雑で時間のかかる作業を弁護士に任せることができます。
- 精神的な負担の軽減: 保険会社とのやり取りや、今後の見通しなどについて弁護士に相談することで、精神的な不安や負担を軽減することができます。
- 法的サポートによる安心感: 法的な専門家である弁護士がサポートすることで、安心して治療に専念することができます。
- 裁判になった場合の対応: 示談交渉が決裂し、裁判になった場合でも、弁護士が代理人として対応します。
交通事故による肩腱板損傷でお困りの方は、一人で悩まず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、あなたの権利を守り、一日も早い問題解決のために尽力します。
私たち優誠法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談を初回無料でお受けしております。是非お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

これまで、交通事故・離婚・相続・労働などの民事事件を数多く手がけてきました。今までの経験をご紹介しつつ、皆様がお困りになることが多い法律問題について、少しでも分かりやすくお伝えしていきます。
■経歴
2009年03月 法政大学法学部法律学科 卒業
2011年03月 中央大学法科大学院 修了
2011年09月 司法試験合格
2012年12月 最高裁判所司法研修所(千葉地方裁判所所属) 修了
2012年12月 ベリーベスト法律事務所 入所
2020年06月 独立して都内に事務所を開設
2021年3月 優誠法律事務所設立
2025年04月 他事務所への出向を経て優誠法律事務所に復帰
■著書
こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。
保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。
「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。
初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。
全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。